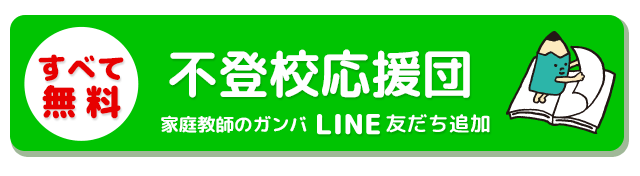近年増加傾向にある不登校や引きこもり。みなさんの周りでも不登校や引きこもりのお子さんやその問題について関心を持っている方も多いのではないでしょうか?
思春期に多い問題なので、一緒に住んでいる家族の対応がとても重要で、その対応次第では問題が深刻になったり長引いたりもします。今回は、不登校支援カウンセラー、メンタル心理カウンセラーの立場から、不登校や引きこもりを長引かせる接し方の特徴について、実例を交えながら深掘りしていきます。
1. 過度な干渉
まず最初に、過度な干渉についてお話しします。親御さんが子どもに対して過度に干渉することで、子どもの自立心が育たなくなります。例えば、私の友人Aさんは、母親が毎日学校の宿題をチェックし、勉強の仕方にまで細かく指示をしていました。彼女は自分で考える機会を失い、次第に「自分は何もできない」と思い込むようになってしまいました。
また、別の友人Bくんは、親御さんが彼の交友関係にまで口出しをするタイプでした。「あの子とは付き合わないほうがいい」「このグループに入らなければならない」などと指示されることで、彼は自分の人間関係を自由に選べないと感じ、次第に外出を避けるようになりました。結果的にBくんは不登校になり、家に引きこもる生活を続けています。
親御さんが子どもの生活全般に干渉しすぎると、子どもは自分で決断をする力を失いがちです。自分で考える力が育たないと、将来的に困難な状況に直面した時にどう対処して良いか分からなくなります。親御さんが適度な距離を保ちながら、子どもが自分で考え、決断する機会を与えることが重要です。
2. 完璧主義
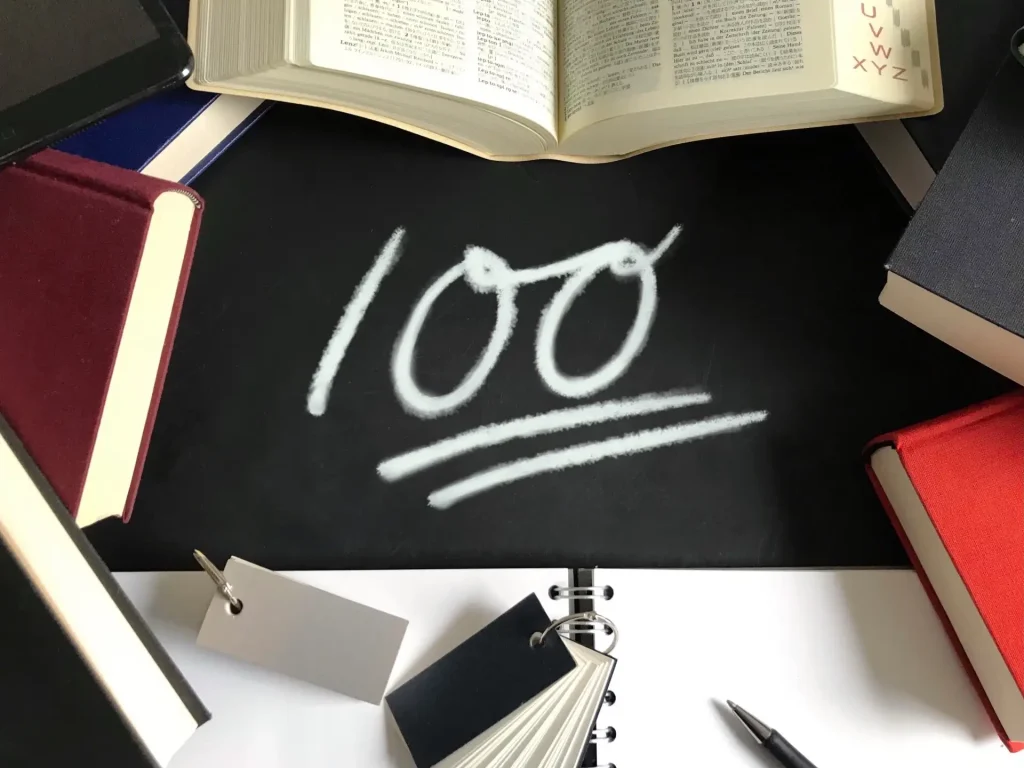
次に、完璧主義について考えてみましょう。親御さんが完璧を求めると、子どもに大きなプレッシャーがかかります。私の知り合いCさんは、親御さんから常に「100点満点を取ること」を求められていました。彼女は高い成績を維持するために必死になり、睡眠時間を削って勉強していましたが、次第に疲れ果ててしまいました。そして、ある日突然、学校に行けなくなり、部屋に閉じこもるようになりました。
親御さんが子どもの成績や成果に対して過剰に期待をかけると、子どもはその期待に応えられない自分を責めることがあります。Dくんの場合、親御さんが「お前はもっとできるはずだ」と言い続けた結果、彼は自分を追い詰め、不登校になりました。彼は「自分は親の期待に応えられないからダメな人間だ」と感じてしまい、自己評価が著しく低下しました。
子どもは失敗を通して成長するものです。しかし、完璧主義の親は失敗を許さず、常に最高の結果を求めます。これが続くと、子どもは失敗を恐れるようになり、新しいことに挑戦する意欲を失ってしまうことがあります。親は子どもの成長を見守り、失敗を含めて経験を積むことの大切さを理解する必要があります。
3. 感情のコントロール不足
親御さんが自分の感情をうまくコントロールできない場合、家庭内の雰囲気が悪化し、子どもも情緒不安定になりやすいです。Eちゃんの家では、母親がしょっちゅう怒りを爆発させ、家の中は常にピリピリした空気に包まれていました。Eちゃんはいつも母親の機嫌を伺い、家の中でリラックスすることができず、次第に学校にも行けなくなりました。
一方、Fくんの家では、お父さんが頻繁にストレスを抱えており、その影響で家庭内が不安定でした。お父さんが仕事のことでイライラすると、家族全員がその影響を受け、Fくんは自分の感情を表現することができなくなりました。彼は次第に内向的になり、友達とも距離を置くようになってしまいました。
親御さんが感情をぶつけることで、子どもは安心できる場所を失います。家庭は子どもにとって一番の安全地帯であるべきです。親御さんは自分の感情を適切にコントロールし、子どもの気持ちに寄り添う姿勢が求められます。例えば、子どもが何か問題を抱えていると感じたら、まずは冷静に話を聞くことが大切です。
4. 他人との比較
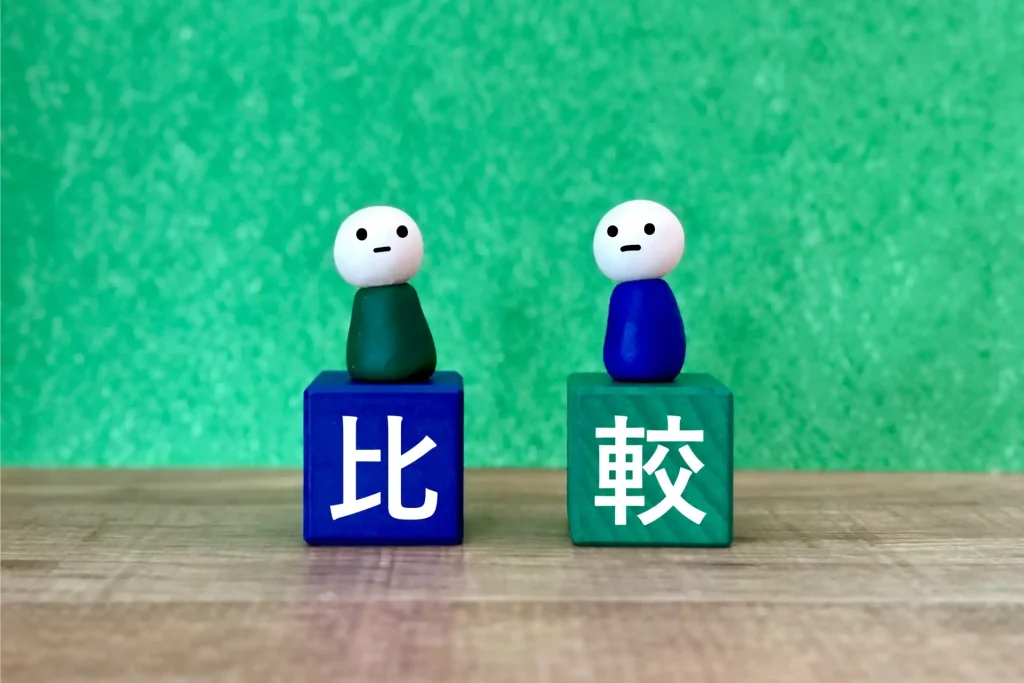
親御さんが他人の子どもと自分の子どもを比較することは、子どもの自尊心を傷つける原因になります。Gちゃんの親は、常に彼女を近所の優等生と比較していました。「あの子は勉強もできて、スポーツも得意なのに、どうしてあなたはできないの?」という言葉に、Gちゃんは自信を失い、自分には価値がないと感じるようになりました。
Hくんの場合、親御さんが彼を兄と比較することが日常的でした。「兄さんはこんなに優秀なのに、お前はなんでこんなにダメなんだ」という言葉を何度も聞かされ、Hくんは次第に自分に対する期待を捨て、学校に行くことを避けるようになりました。彼は兄との比較に疲れ果て、自分の居場所を見つけることができなくなってしまったのです。
他人との比較は、子どもにとって非常にストレスフルなものです。特に親御さんからの期待が高い場合、子どもはその期待に応えられない自分を責めてしまいます。親御さんは子どもの個性を尊重し、他人と比較せずに子ども自身の成長を見守ることが重要です。それぞれの子どもにはその子なりのペースと道があります。
5. サポートの不足
不登校や引きこもりの子どもに対して最も足りないのは、親の適切なサポートです。Iちゃんの親は、彼女が不登校になった時に、彼女の気持ちを理解しようとせず、「なんで学校に行けないの?」と責めました。Iちゃんは親に理解されない孤独感を抱え、ますます部屋に閉じこもるようになりました。
Jくんの場合、親が彼の不登校を「怠けている」と決めつけ、何もサポートしませんでした。彼は自分の気持ちを誰にも話せず、次第に心を閉ざしていきました。親が彼の気持ちに寄り添ってくれていたら、彼はもっと早く自分の問題を解決できたかもしれません。
親御さんが子どもの気持ちに寄り添い、理解しようとする姿勢が欠けていると、子どもは孤立感を感じます。家庭内でのサポートが不足すると、子どもは自分の問題を一人で抱え込むことになります。親御さんは子どもの話に耳を傾け、無条件の愛情を示すことが大切です。また、必要に応じて専門家の助けを借りることも検討しましょう。
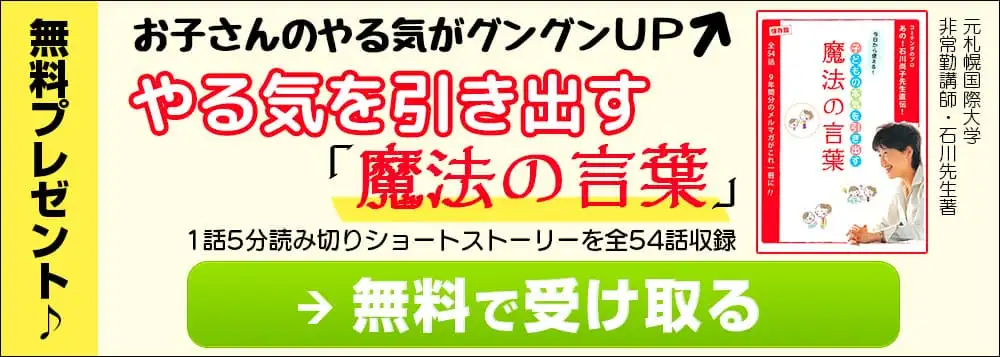
まとめ
不登校や引きこもりを長引かせる親の特徴について、5つのポイントを実例を交えて深掘りしました。親御さんが適切な対応を心がけることで、子どもは自信を取り戻し、自立への第一歩を踏み出すことができます。家庭内の環境を整え、子どもにとって安心できる場所を提供することが何よりも重要です。
また、親御さんも自分自身を大切にすることが大切です。子どもにとって良い環境を提供するためには、まず親御さん自身が健康で、心の余裕を持つことが必要です。ストレスや不安を感じたら、友人やカウンセラーに相談することも一つの方法です。例えば、私の友人Kさんは、子どもが不登校になった際にカウンセラーの助けを借りて、自分自身のストレスを軽減し、子どもに対して冷静に接することができました。
親御さんと子どもが一緒に成長し、お互いを理解し合える関係を築くことができれば、不登校や引きこもりの問題も少しずつ改善されていくでしょう。この記事が少しでも役に立つことを願っています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。私も日々、自分自身も成長しながらお子さんたちと向き合っていきたいと思っています。これからも一緒に頑張りましょう!
不登校支援・メンタル心理カウンセラー 有馬