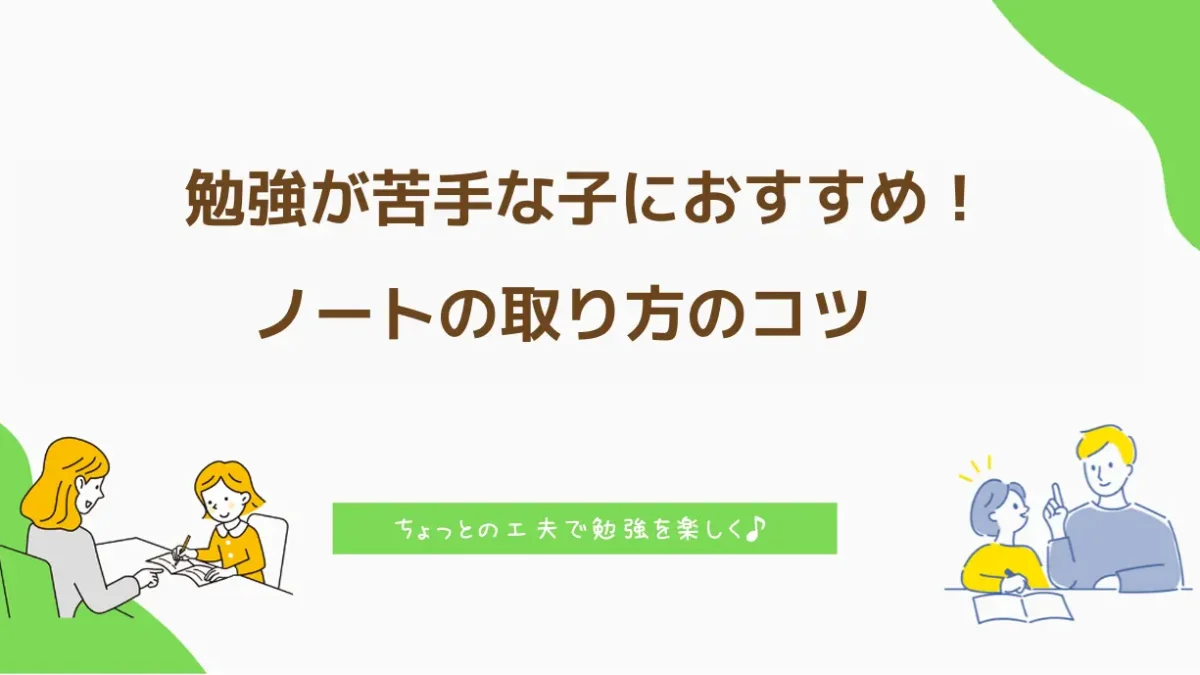勉強が苦手だと感じているお子さんにとって、ノートを取ることが苦痛になってしまうこともあるかもしれません。でも、ノートをうまく活用することで、授業の内容が理解しやすくなったり、復習もしやすくなったりします。ここでは、勉強が苦手な子でも実践できるノートの取り方のコツをご紹介します。
ノートを取ることの重要性は多くの研究でも示されているようです。例えば、米国コーネル大学のノート取りシステム(コーネルメソッド)は、情報を整理しやすくするための効果的な方法として有名です。
また、日本でもノート術に関する書籍が多数あることからも、ノートの取り方の工夫次第で、理解と記憶に重要な役割を果たすであろうことが伺えます。実際、自分のお気に入りのノートの取り方が見つかれば、ノートは見ていて楽しく、結果、見直しやすくなり復習の習慣につながりやすいです。
以下にノートの取り方に関して効果的と思われる方法を挙げてみます。少しでもご参考にしていただけると嬉しいです。
1. 目的をもって簡潔にまとめる
まず大切なのは、ノートを取る目的を持つことです。ただ先生が言ったことを書き写すだけではなく、授業の後に見返すために「どこが重要か」を意識してノートを取ることが大切です。
例えば、すべてを完璧に書く必要はありません。自分が理解できる言葉で、簡単に要点をまとめれば良いと思います。数学の授業なら、解き方のポイントだけを書くとか、理科の授業なら「なぜこうなるのか」というポイントを簡単にまとめる、という風にします。自分なりに簡単に書いて、後で見返した時に「ああ、こういうことだったな」と思い出せることを目指しましょう。
授業中に全てを写し取ることにこだわりすぎると、先生の説明に集中できなくなってしまい、授業の内容が理解できなかったということにもなりかねません。大切なのは、授業をしっかり聞いて、必要なことを必要なだけメモするという意識を持つことです。必要なポイントを押さえておくことが、成果を上げるためには重要です。
ノートを取る際の考え方としては、ノートは「授業を完璧に記録するもの」ではなく「自分に必要なことだけがギュッと詰まったお宝メモ」と捉えることが大事です。ノートを使って、授業内容を整理し、自分自身の考えをまとめていくことで、勉強がより効率的になると思います。
2. 見返したくなるノートをつくる工夫
ノートが見にくいと、復習するときにどこを見たらいいか分からなくなり、やる気がなくなってしまうことがあります。そこで、ノートを見やすく使いやすくする工夫をしましょう。
例えば、ノートを見やすくするために、「見出し」をつけたり、重要な部分を色分けしたりすることがおすすめです。赤ペンで「ポイント」と書いて、重要なことを書き足してみるとか、見出し記入や色分けをすることで、どこが重要か一目で分かるようになります。
また、ノートの余白を活用するのもおすすめです。ノートの右側や下側に少し余白を残しておいて、授業後に自分の感想や、わからなかったことをメモしておくと良いと思います。例えば、「ここがわからなかった」「次の授業で先生に聞く」などのメモを書き込むことで、次に何をすればいいかが分かり、復習が楽になり、しかも効果的になります。
色ペンや蛍光ペンを使うことも効果的です。重要な用語を赤で囲んで、次に覚えるべき公式を青でマークするなど、視覚的に情報を整理することができます。視覚的に整理されたノートは、後で見返したときに理解しやすく、自然と復習の効率が上がります。
3. 直後の見直し効果
授業が終わった直後にノートを見直すと、内容が頭に入りやすくなります。授業が終わったらすぐに自分のノートを見直してみましょう。ザっとでも構いませんので何が重要だったのかをおさらいする程度でも、後から大きな差を生むことがあります。
ノートを見返すときは、何が重要だったのかを確認するだけでなく、わからない部分のチェックもしましょう。「これ何だっけ?」と思ったら、その部分にマークをつけておき、後で調べたり先生に聞いたりすると効果的です。この方法を続けていくと、わからない部分が減っていき、少しずつ授業内容に自信が持てるようになります。
また、余裕があれば、授業後にノートを整理することもおすすめです。たとえば、書き足りなかった部分を補足したりすることで、ノートがより完成度の高いものになるのではないでしょうか。このプロセスで、改めて授業内容を自分の頭で整理し直すことができるため、理解が深まります。また、この短い見直しの時間を持つことで、次回の授業に対する準備も整いやすくなります。
4. 重要なことだけを箇条書きにしよう
授業中、全てを書こうとすると追いつかなくなってしまいます。そのため、ノートには「重要なこと」だけを箇条書きにすることもおすすめです。先生が「ここは覚えておいた方が良いよ」と言った部分や、教科書で太字になっている部分などが目印です。
例えば、歴史の授業では、年号と出来事、主要な人物名だけを書いておきます。英語の授業では、新しく出てきた単語とその意味、例文だけを書いておく、といった感じです。こうすることで、後からノートを見返したときに「ここが大事だったんだな」とわかるようになります。
箇条書きにするときのポイントは、短く簡潔に書くことです。長い文章は書かず、単語や短いフレーズでまとめることで、ノートがすっきりし、見返しやすくなります。また、情報を整理して書くことで、授業中に理解が追いつかない場合でも後で復習しやすくなります。
箇条書きにすることのメリットは、視覚的に情報を整理しやすくなることです。関連する情報をまとめて箇条書きにすることで、「これはこう繋がっているんだな」と直感的に理解しやすくなります。関連性がある情報をグループ化することで、学習内容が体系的に整理され、頭に入りやすくなります。
5. 自分なりの工夫を取り入れてみよう
勉強が苦手な子でも、少し工夫することでノートを取るのが楽しくなります。例えば、イラストを描いてみるのも良い方法です。特に理科や社会の授業では、図やイラストを使って覚えることで、より深く理解することができます。
植物の仕組みについて学ぶときには、自分で簡単な絵を描いてみたり、また、歴史の授業で人物について学ぶときには、その人物の特徴を自分なりにイメージして描いてみたりすると、記憶に残りやすくなるのではないでしょうか。
また、自分の好きなシールやカラーペンを使ってノートを彩ることもおすすめです。ノートがカラフルで見やすくなると、見返すこと自体が楽しくなり、勉強に対するやる気が少しずつ出てきます。好きなキャラクターのシールを使って、「ここを頑張った」部分に貼るなど、自分なりのご褒美として使うのも良いのではないでしょうか。
6. ノートを取ることに完璧を求めない
最後に大切なのは、ノートを取ることに完璧を求めないことだと思います。授業中に全部を完璧に書き写そうとすると、授業の内容を理解することが難しくなってしまいます。ノートは「自分が後で見て分かること」を目的にして取るものです。
例えば、書ききれなかった部分があったとしても、授業中に集中して先生の話を聞くことの方が大事です。ノートを取ることに気を取られて、肝心の授業内容を聞き逃してしまうよりも、少し簡単に書いておいて、後で必要な部分を補足するくらいの気持ちでいると楽になります。
また、自分が間違ったり、分からなかったりした部分をそのままノートに残すことも有効です。間違いも含めてノートに書いておくことで、後から「ここが分からなかった」と気づける材料になります。そして、次に同じような問題に出会ったときに「前にここでつまずいたな」と振り返ることができ、成長のきっかけとなります。
さらに、ノートを取る際には「完璧でなくてもよい」という心構えを持つことで、勉強に対するプレッシャーが軽減され、リラックスして授業に臨めるようになります。勉強が苦手な子にとって、プレッシャーが少ない環境で学ぶことは、理解力を高める上でとても大切だと思います。
まとめ
勉強が苦手な子でも実践できるノートの取り方のコツについてご紹介しました。ノートを取ることは、授業内容を整理し、後で復習するためにとても大切です。ただ、全てを完璧に書き取ることが重要なのではなく、自分にとって必要な情報を、理解しやすい形で残すことがポイントです。
目的を持って簡単に書き、見やすく整理し、授業後に少し見直すことを習慣にしてみてください。また、自分の好きな工夫を取り入れて、ノートを取ることを少しでも楽しいものにしていきましょう。そして何より、ノートを取ることに完璧を求めず、自分のペースで進めていくことが大切です。
少しずつ工夫を重ねていけば、ノートを取ることが楽になり、勉強の苦手意識も少しずつ減っていくはずです。自分に合った方法を見つけて、ノートを活用していきましょう。
また、勉強が苦手だと感じているお子さんは「やればできる」という気持ちを持つことが大切です。ノートを取ることも、最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ工夫をしていくうちに、自分にとってのベストな方法が見つかります。そして、その積み重ねが自信に繋がります。焦らず、毎日少しずつ取り組んでいけば、いつか必ず結果に結びつくはずです。
最後に、ノートを通じて自分の成長を感じることができたら、その喜びを大切にしてください。勉強が苦手でも、努力を続けることで必ず成長できます。ノートはその努力の証です。少しずつ成長を感じながら、これからの学びを楽しんでいきましょう。頑張ってください!
参考文献一覧:文部科学省「学習効果を高めるための学習指導」2021年
家庭教師のガンバでは無料の体験授業を行っています。
無理な勧誘は一切ありません。家庭教師がどんな感じか試されてみたい方はぜひ、お気軽にお問い合わせください。