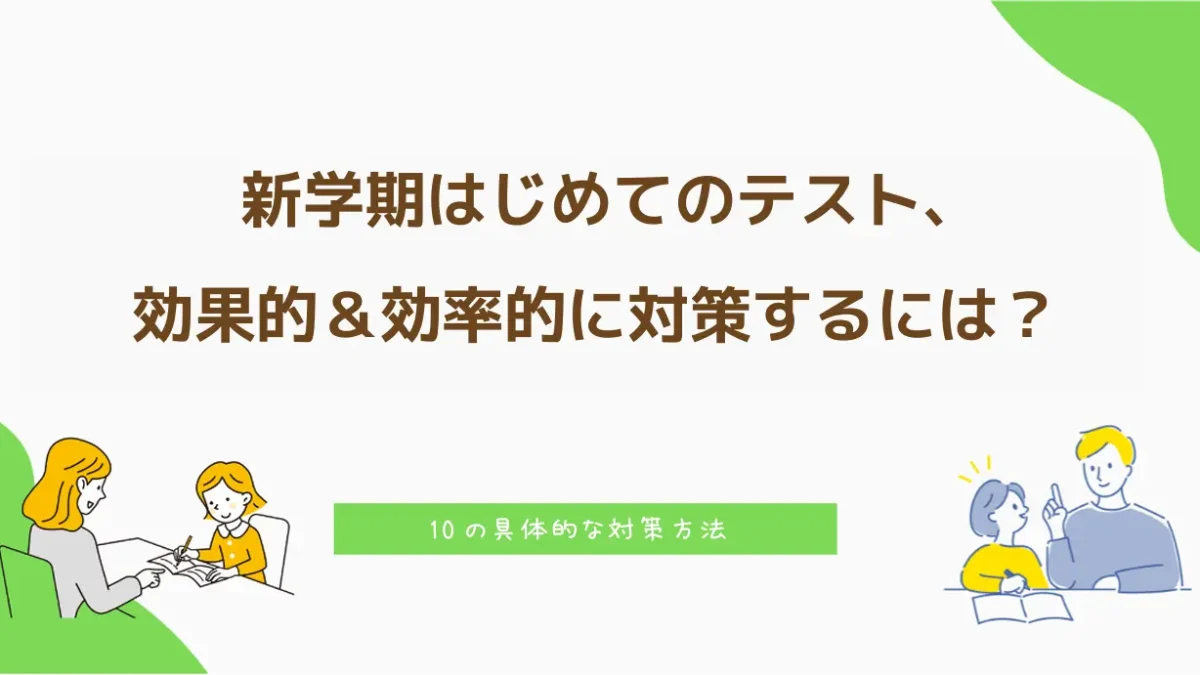新しい学年の始まりは、誰にとってもワクワクする一方で、不安もつきまとう時期です。クラス替え、担当の先生の変更、新しい教科書や学習内容など、環境の変化に戸惑いを感じるお子さんも少なくありません。そんな中、早くもやってくるのが「新学期はじめてのテスト」です。これは、新学年の勉強のスタートダッシュを決めるための大切な機会であり、その後の自信や成績に大きな影響を与えるかも知れません。
ただ、新学年のテスト対策は、前年と同じように取り組んでもうまくいかないことがあります。教科ごとの難易度が上がったり、学習範囲が広がったりするため、より計画的で効果的な勉強方法が必要になります。特に中学生・高校生の場合は、科目数も多く、生活のリズムが変わることから、早めに準備を始めることが成功の鍵となります。
今回は、新学期はじめてのテストで良いスタートを切るための「10の具体的な対策方法」をご紹介します。
1. テスト範囲の把握がすべてのスタート
テスト対策の第一歩は、テスト範囲を正確に把握することです。どれだけ頑張って勉強しても、テストに出ない部分を一生懸命やっていたら時間の無駄になってしまいます。まずは、先生から配られる試験範囲表や、授業中に伝えられる「ここは重要」とか、「ここは出るよ」といった情報をしっかりメモしましょう。また、教科書やワーク、配布プリントなど、使用教材がすべて試験対象となることもあります。先生によっては、授業で扱った内容すべてをテスト範囲とする場合もあるので、ノートの整理も怠らずに行いましょう。
また、テスト形式の情報も大切です。記述式か選択式か、穴埋め問題か、それとも作文や長文読解が出るのか。これによって勉強の仕方が大きく変わります。たとえば英語のテストで、リスニングが含まれる場合は音声を使った練習が必要になりますし、数学で記述式ならば途中式の書き方を重視する必要があります。このように、範囲と形式を把握することが、無駄のない効率的なテスト勉強の土台になります。
2. 教科ごとの「得意・苦手」を分析する
新学年が始まったばかりの頃は、自分の現在地を客観的に見る良いチャンスでもあります。ここで重要なのが、自分の得意科目と苦手科目を明確にすることです。すべての教科を同じように勉強するのは理想的ですが、実際には時間に限りがあります。限られた時間を有効に使うためには、例えば、得意教科はスピーディーに確認する程度にして、苦手教科には時間を多く割くなどの工夫が必要です。
英語が得意であれば、単語や文法の確認を中心に軽めに復習し、数学が苦手であれば、例題を繰り返し解くなどして基礎の定着に時間をかける、といった具合です。さらに、自分の中で「どうして苦手なのか」を分析してみると、より対策がしやすくなります。暗記が苦手なのか、計算ミスが多いのか、読解力が不足しているのか。その原因を突き止めることで、対処法も明確になります。
また、成績表や過去のテストを見直すのも有効です。どの分野で点数が取れていないのかを確認し、優先順位を決めましょう。感覚だけで「苦手」と思い込んでいる科目も、実は少しの工夫で伸びる可能性があります。自分自身を見つめ直すことが、テスト対策においてとても大切なプロセスなのです。
3. 勉強計画は「逆算」して立てる
効率的に勉強するには、計画性も重要です。テスト直前になって慌てて詰め込んでも、内容が頭に入らないことも多く、焦りからミスをしてしまうこともあります。だからこそ、テストまでの日数を逆算し、計画的に勉強することが大切です。まずはテストの日付をカレンダーで確認し、残りの日数を数えましょう。そして、その中で「何をいつまでに終わらせるか」「復習に何日使うか」など、細かくスケジューリングしていきます。
たとえば、テスト10日前には全教科の内容を一通り確認し、7日前からは苦手科目に重点を置いた勉強、3日前からは予想問題を解く演習、前日は暗記科目を最終確認する、といったように、フェーズを分けて勉強するのが理想です。また、1日単位での勉強スケジュールも考えておくと、無駄なく過ごせます。学校の授業後に何時間勉強できるのか、部活や習い事がある日は短めに設定するなど、無理のない計画にすることがポイントです。
4. 教科書・ノートの使い方を見直す
教科書やノートを有効に使うことも、テスト勉強の質を大きく左右します。ノートはただ板書を写すだけでなく、自分なりのまとめや気づきを加えることで、理解が深まり、復習もしやすくなります。ノートの見返し時に、赤シートを活用して暗記の確認をする、マーカーで重要語句を強調する、色分けで整理するなど、自分が「読みやすい」「覚えやすい」と感じる形に整えることも大切です。
理科や社会では図や表を活用して視覚的にまとめ、英語では新出単語や熟語の例文を自作するなど、教科ごとに工夫も変わってきます。教科書も「読むだけ」にせず、傍線を引いたり、欄外にメモを加えることで、自分のものにしていく意識を持ちましょう。ノートと教科書を連動させて使うことで、より効率的な学習が可能になります。
5. 問題演習は「質」と「量」のバランス
問題をたくさん解けば成績が上がる、というわけではありません。大切なのは「理解した上で解く」ことです。たとえば数学で公式を覚えていない状態で応用問題を解こうとしても、うまくいくはずがありません。まずは基礎をしっかり固め、それを活用する段階に進むようにしましょう。
また、問題を解いたら必ず答え合わせをして、間違えた問題は「なぜ間違えたのか」を分析します。ノートにまとめ直したり、再度同じ問題を解いたりすることで、自分の弱点が少しずつ克服されていきます。演習には時間を測って取り組むのもおすすめです。限られた時間内でどれだけ解けるかを意識することで、集中力も養われ、テスト本番での時間配分の練習にもなります。
6. わからないことは「すぐ聞く・調べる」
勉強を進める中で「これは何だったっけ?」と感じたら、その場で調べたり、先生に質問したりする習慣をつけましょう。「後でまとめて聞こう」と放置しているうちに、わからない箇所が積み重なり、手が付けられない状態になってしまうこともあります。わからないことは“今すぐ解決”が鉄則です。
質問するのが恥ずかしいと感じる人もいますが、先生は質問を歓迎しています。積極的に質問するお子さんは、先生からの印象も良くなりますし、自分自身もモヤモヤを解消することで自信がつきます。また、友達と教え合うのも良い方法です。教えることで自分の理解も深まり、相手の説明から新しい気づきを得ることもあります。
7. 家庭学習の環境を整える
集中できる環境が整っていないと、どんなにやる気があっても勉強ははかどりません。勉強部屋や机の上を整理し、不要なものは視界から排除しましょう。スマホやゲーム、マンガなどの誘惑は、思った以上に集中力を奪います。勉強する時間帯は電源を切るか、別の部屋に置いておくのがベストです。
また、机の高さや椅子の座り心地、照明の明るさなども意外と重要です。集中力が長時間持続できる環境を整えることは、成績アップにつながります。時間のメリハリをつけることで、だらだらとした学習から抜け出すことができます。
8. プリントなどを最大限活用する
学校で配られたプリントやワーク、確認テストなどは、先生が作る本番の試験に近い形で出題される傾向があります。だから、「プリントや小テストは重要」と考えてください。問題を解いたら放置せず、必ず見直し、間違えた問題は自分で再び解けるまで練習しましょう。
また、プリントに書き込みが多く見にくくなっている場合は、同じ問題をノートに解き直すことで整理ができます。友達とプリントを交換して出題し合ったり、問題を読み上げて答えるクイズ形式で学ぶのも面白く、飽きずに勉強を続ける工夫になります。
9. 生活リズムを整えることも立派な対策
睡眠不足は勉強の大敵です。新学期が始まったばかりの今こそ、早寝早起きの習慣をつけておきましょう。テスト本番の朝に眠くて頭が働かない、なんてことがないよう、生活リズムを整えておくことが大切です。
10. モチベーションを保つ工夫をする
やる気が出ないときでも、勉強を継続できる工夫が必要です。たとえば「テストで80点取れたら好きなスイーツを買う」「〇時間勉強したら10分動画を観る」といったように、ごほうびを用意することでやる気が出る人も多いです。モチベーションが自然に湧かない時は、作るのも大切です。
また、自分の頑張りを記録する「勉強日記」や、時間を可視化できるアプリを使って、成果を実感するのもおすすめです。努力が数字で見えるようになると、続ける意欲につながります。友達と一緒に進捗を共有し合うのもよい方法です。楽しみながら、目標に向かって努力できる環境を自分で整えていきましょう。
まとめ
新学年の最初のテストは、その後の学習意欲や学校生活の流れを大きく左右する可能性のある大切なイベントです。早い段階からしっかりと準備を進めることが、後の自分を助けることにつながると思います。今回ご紹介した10項目の対策を実践することで、効率的に、そして効果的にテスト勉強が進められるキッカケになれば嬉しいです。
完璧を目指す必要はありません。大切なのは「やるだけやった」と思えるような準備をすることです。その積み重ねが、将来の大きな成果へとつながっていきます。まずはできることから一歩ずつ、今日から取り組んでいきましょう。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。