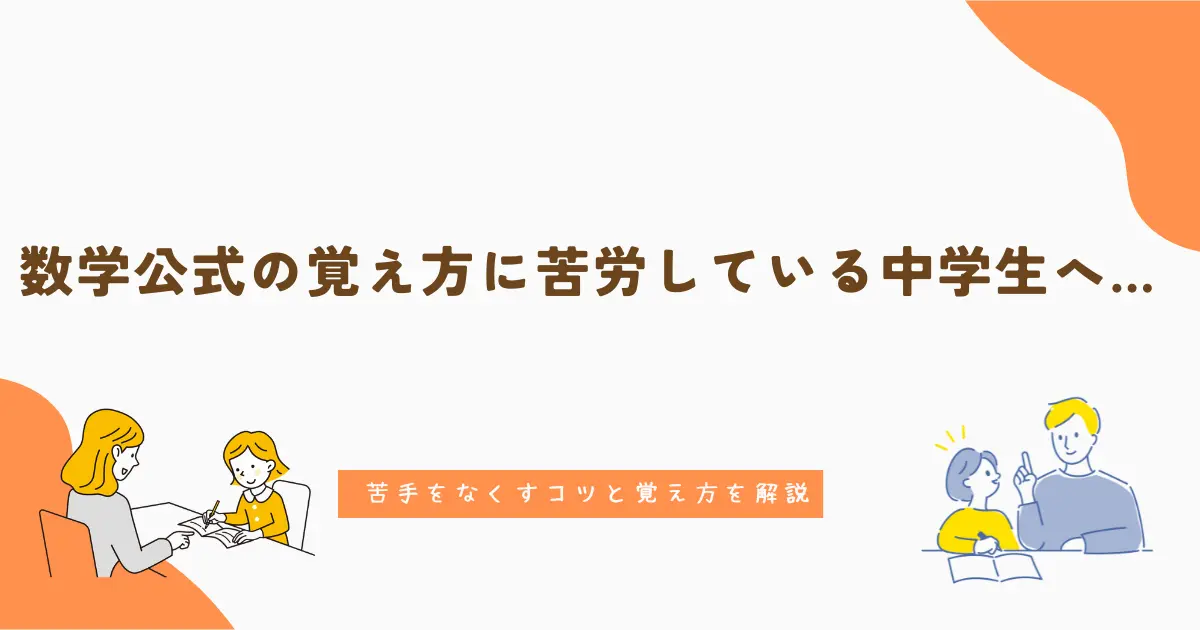「数学の公式、なかなか覚えられない…」
そんなふうに悩んでいる中学生も多いのではないでしょうか?たとえば、テスト勉強で公式を一生懸命覚えたのに、いざ問題を解こうとすると「あれ、どう使うんだっけ?」と迷ってしまったり。せっかく覚えたのに、すぐ忘れてしまって「私って暗記苦手かも…」と落ち込んでしまったり。
でも大丈夫。数学の公式は、ただ丸暗記するだけではなく、ちょっとしたコツや工夫を加えるだけで、しっかり頭に入って使えるようになるんです。
この記事では、数学の公式や定理の覚え方に悩む中学生に向けて、
・そもそも数学って暗記しないとダメ?
・覚えられない原因って?
・忘れにくくて、テストでも使える覚え方って?
などを、わかりやすく解説していきます。苦手な公式も「なんだ、こういうことだったのか!」とスッキリできるヒントがたくさん詰まっているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
数学の公式って、覚えないとダメ?
数学は「暗記科目じゃない」と言われることもありますよね。たしかに、数学はただ覚えるだけでなく、理解して使いこなすことが大切です。でも、公式を覚えておくこともとても重要なんです。
毎回公式を導いていたら時間が足りない
たとえば、「二次方程式の解の公式」を思い出してみましょう(まだ習っていない人は、何となく「そうかも」という感じで聞いてください)。本来は平方完成という考え方から導くことができますよね。でも、テストのたびにその導き方を一からやっていたら、とても時間が足りません。
公式の意味を理解したうえで、ちゃんと覚えておくこと。それがテストで安定して得点するための近道なんです。
大切なのは「使いこなせること」
覚えた公式は、実際の問題の中で「正しく使える」ことが大切です。たとえば、連立方程式の加減法や代入法も、名前と解き方だけを覚えても、うまく使いこなせませんよね。
それぞれの用法をどういう場面で使うのかは、ある程度問題演習で慣れる必要があります。使いどころがわかるようにならないと、逆に計算が難しくなり、ミスが増えるかもしれません。
「公式を覚える=ゴール」ではなく、「公式を使いこなせる」ことを目指しましょう。
公式が覚えられない3つの理由
「ちゃんと覚えたはずなのに、テストで出てこない…」そんな経験をしたことがある人も多いと思います。実は、覚えられないのにはちゃんと理由があるんです。代表的な原因を3つ紹介します。
①理屈を理解せず丸暗記している
公式の「なぜそうなるのか?」を理解せずに、ただ文字の並びだけを覚えていると、記憶として定着しづらく、すぐに忘れてしまいます。
たとえば小学校で習った台形の面積を求める公式は、丸暗記だと忘れやすいと思います。でも、横にもう一つ逆さにした台形を並べる説明を見て、「なるほど、だから公式の中に上底+下底があるんだ!」と納得していれば、記憶にとどまりやすくなりますよね。
仕組みから納得できた公式は、自然と記憶に残りやすくなるんです。
②問題で使う経験が足りない
公式を覚えただけで、演習問題に取り組んでいないと、「どの場面で使えばいいの?」と迷ってしまいます。たとえば中3の「特別な直角三角形」で習う辺の比率(公式みたいに暗記させられます…)は、角度との関係性をちゃんと理解していないと、ほかの直角三角形にまで使うミスをおかしがちです。点数が取れず、「あれ、なんで?」と首を傾げることになります。
<特別な直角三角形でミスをしないポイント>
・使えるのは三角定規の形と覚える
・問題から「30°、60°、90°」または「45°、45°、90°」だとわかるか確認する
・「三平方の定理を使うべきかもしれない」という意識を持つ
「えー難しい!」と思っても、心配はいりません。何度も演習していくうちに自然と身につきます。しっかり身につけるには、「覚える→使う→繰り返す」のサイクルが大事です。演習を通して使い方を体で覚えていきましょう。
③抽象的な内容がイメージできない
中学数学になると、文字を使った計算や、抽象的な内容がどんどん増えていきます。「π(パイ)って何?」「√(ルート)って何を表してるの?」といった疑問を放置したままにしておくと、理解が進まず、公式を覚えるのも一苦労になるかもしれません。
そんなときは、図や具体的な数字を使ってイメージしてみるのがgoodです。たとえば…
・πは「円の面積や周を出すときに必要で、だいたい3くらいの数」
・√は「16のルートが4みたいに、2回同じものをかけてその数字になるもの。整数にできないものは、しょうがなくルートのままなんだ」
などと考えます。難しい記号が少し楽に見えてきませんか?
忘れにくい!数学公式の覚え方・勉強法6選
では、実際にどうすれば公式をしっかり覚えられるのでしょうか?今日からすぐに実践できる、おすすめの勉強法をご紹介します。
①授業の中で「なぜそうなるのか」を意識する
授業では、先生が公式の成り立ちや使い方を丁寧に説明してくれますよね。板書をノートに写すだけでなく、「なぜそうなるのか?」「どんな場面で使えるのか?」を考えながら聞くと、理解がグッと深まります。
先生の話を聞いている時に感じる「なるほど」という納得こそが、記憶を定着させてくれます。心から納得したポイントが多いものほど、記憶に残るはずです。だからこそ、授業をきちんと聞くことが大切なんです。
②参考書で復習するときは「意味」を意識
公式を復習するときも、「暗記」ではなく「理解」を意識しましょう。どうしてこの式になるのか?どんな仕組みで導き出されるのか?
解説を読みながら、自分なりに納得できるように、かみくだいて考えてみるのがコツです。どうしても自分で意味がわかりづらいものは、早めに先生に質問してください。いろいろな角度から工夫して説明してもらえるはずです。
③練習問題で「使う場面」を身につける
覚えた公式は、実際の問題の中で使ってみることで身につきます。はじめは教科書の基本問題からでOKです。難しい問題にいきなり挑戦するより、徐々にステップアップするほうが定着します。
「この問題は、あの公式を使えば解けるな」と気づけるようになれば、記憶にどんどん定着していきます。
④関連する公式をセットで覚える
似ている公式や、つながりのある定理は、まとめて覚えると理解が深まります。たとえば、式の展開は乗法公式をセットで覚えるように言われますよね。一つひとつ単体で覚えるよりも、身につきやすくなるからです。
学校のテストや入試では、「乗法公式②を使って解きましょう」「こちらは④を使ってください」などと指示はしてくれません。その場で判断しなければ、正解できないんです。
だからこそ、公式同士のつながりを意識し、使用する場面の違いをよく理解しておく必要があります。セットで覚えて演習を重ねれば、スムーズに使い分けられるようになります。
⑤演習を繰り返して体にしみ込ませる
九九を覚えたときと同じように、数学の公式も何度も繰り返し使うことで自然と身についていきます。今は難しいと感じる「解の公式」や「三平方の定理」も、繰り返し使ううちに、だんだんと当たり前になるでしょう。
「使って、間違えて、直す」ことを繰り返すのが、一番の近道です!
⑥どうしても覚えられないものは語呂合わせもOK!
理屈で覚えにくい公式は、語呂合わせを使ってもOKです。たとえば、
・球の体積(4/3 π r³)→「みんな失敗あるさ」
・球の表面積(4 π r²)→「心配あるある」
・√2 →「一夜一夜に人見頃(1.41421356)」
・√3→「人並みにおごれや(1.7320508)」
・√5→「富士山麓オウム鳴く(2.2360679)」
など、クスッと笑える語呂で覚えてしまいましょう!
まとめ|理解と演習で「公式は味方」になる!
数学の公式は、ただの暗記ではなく、「意味を理解して」「実際に使って」「繰り返して身につける」ことが大切です。
ちょっとずつでもいいので、「なるほど」「できたかも」「なんとなくわかるかも」という小さな実感を積み重ねていくことで、苦手意識は自然と薄れていきます。
高校に進むと、さらに公式の数は増えていきます。でも中学のうちに「覚え方のコツ」「向き合い方」を身につけておけば、きっとその後の勉強もスムーズに進むはずです。今のうちから、数学の公式と“ちょっと仲良くなる”ことから始めてみましょう。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。