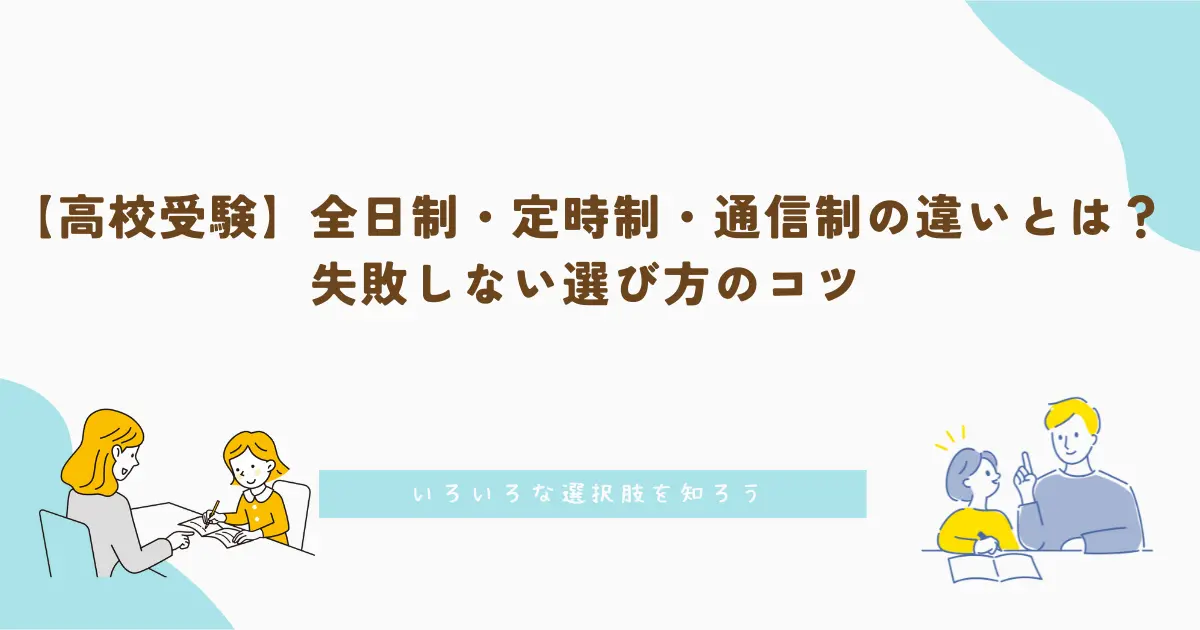高校受験の学校選びで重要な、全日制・定時制・通信制の違いを徹底解説します。各課程の入試方式や学校生活の特徴、選択するメリット・デメリットなどが少しでもお伝えできれば嬉しく思います。学校選択で迷いがちな事例への、失敗しないアドバイスも掲載してみました。
志望校選びは高校受験における大きな悩みの種です。さまざまな高校を調べる中で、「そもそも全日制で良いのだろうか…」と疑問を持ったことはありませんか?特に通信制高校がさまざまなメディアで取り上げられている昨今、各課程の特色が気になる保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、「全日制」「定時制」「通信制」の違いを明らかにし、それぞれの特徴を具体的に説明してみます。ぜひ学校選びの参考になさってください。
全日制・定時制・通信制の違いを知ろう
はじめに「全日制」「定時制」「通信制」の違いを、「必ず知って欲しい事項」に絞って説明します。
全日制・定時制・通信制の入試方式・入学制度の違い

全日制・定時制の違いは内申書の比重です。定時制の方が内申書を重視する傾向があります。定時制の入試は、全日制ほど難しくありません。試験で差がつきづらいため、内申点の比重を大きくせざるを得ないのです。
一方、通信制の多くは学力試験がありません。中学校に通えなかったり、勉強が極端に苦手な生徒も、広く受け入れるためです。内申書も選考基準にはなりません。入学や転入の時期に関しても柔軟性があり、個々の事情に配慮してもらえます。
全日制・定時制・通信制の学校生活の違い

定時制は主に夕方以降に通学します。これは働きながら通う生徒に配慮されているためです。長い時間を確保できないため、一日の授業は4時間に絞られます。その分在籍期間が長くなり、4年での卒業が一般的です。近年は全日制のように昼間通える学校や、「午前・午後・夜」の3部制の学校も増えています。
通信制の高校生活は、学校や選択するコースにより異なります。基本は自由な時間に自宅で学習する形態が多いものの、通学コースが設けられていることもあります。卒業には「年に数回のスクーリング」「レポートの提出」が必須です。
【全日制高校の特徴】豊富な選択肢と充実した学校生活
全日制は学校数が多く、定時制や通信制に比べ選択肢が豊富です。しかし良くも悪くも一日の大半を学校で過ごすことになるため、自分の適性に合うのかを見極めなければなりません。
都市部は全日制高校が多く選択肢が豊富
全日制最大の特徴は、学校数が多いことです。文部科学省によれば、令和元年度時点で、全高校に占める全日制の割合は84.1%です。定時制や通信制と比べ選択肢が豊富なことが分かります。
かつては学区制が当たり前だった公立高校も、学区撤廃の動きが広まったことで、生徒が本当に行きたい学校を多様な選択肢から選べるようになりました。「大学進学に強い」「企業への就職サポートが手厚い」といった将来のニーズから選ぶことも、「自由な校風」「部活動の実績」など学校生活の特色から選ぶことも可能です。
ただし地方では少子高齢化により学校の統廃合が進み、もともと少なかった選択肢がさらに減っている地域もあります。長時間の通学や下宿をしての高校生活を考えると、ひとえに全日制の魅力ばかりを強調できません。居住する地域の実情を十分に鑑みる必要があるかも知れません。
(参照:高等学校教育の現状について | 文部科学省)
仲間とともに学び成長する経験を積める
全日制は毎日同じ仲間と机を並べ、一日の大半を過ごします。勉強だけでなく学校行事や部活動などさまざまな出来事を通し、人間関係が深まります。社会では、多かれ少なかれ他人と協力し合うことが必要です。全日制での経験は、社会生活を円滑に進める上での良い経験となり得るのではないでしょうか。
塾や予備校に頼らずに難関大学を狙える高校も
難関大への進学を目指すなら、全日制が有利です。塾や予備校に頼らずとも、学校の授業だけで合格を狙える可能性もあります。たとえば特進クラスがある学校では、通常のカリキュラムに加え、受験対策や小論文講座が組まれることがあります。通常の授業では扱わないレベルの高い内容を扱い、受験に挑戦する力を培います。
【定時制高校の特徴】働きながら学べる柔軟な学習スタイル
定時制は全課程の中で最も学校数が少なく、生徒数も令和元年度時点で8万人強です。これは全高校生徒数の2.4%に過ぎません。しかし定時制には多様なバックグラウンドを持つ生徒を受け入れる強みがあります。特徴を知ることで、定時制ならではの魅力を正しく認識できるのではないでしょうか。
※この章では別途記載がない限り以下の資料を参照しています。
(参照:定時制課程・通信制課程の現状について | 文部科学省)
昼間通える定時制高校が増加中
定時制はかつて働く人に向けた学校でした。現在もその役割は変わってはいないものの、ニーズの幅は広がっています。文部科学省によると、定時制高校に在籍する生徒は「不登校経験がある生徒」が39.1%と最も多く、「ひとり親家庭の生徒」「特別な支援を必要とする生徒」と続きます。さまざまなバックグラウンドを持つ生徒たちの「学び直しの場」となっているのです。
近年は多部制を採用する学校も増えてきました。「午前」「午後」「夜間」に区分けし、取り決めた時間帯に通学する形式です。昼間学校に通えれば、通常設定されている時間以外にも授業を受ける余裕が生まれます。こうした学校では、3年で卒業できることもあります。
個性や多様な背景を持つ生徒に理解がある
定時制は「普通の高校生像」がつくられにくいため、個性への理解を得やすい環境だと言えます。「特別支援コーディネーター」を担う教諭が一名以上在籍している学校が90%近くを占めており、発達障がいへの対応も万全です。社会的な自立に向けた支援や、自己の課題解決に向けた個別支援を受けられる学校もあります。
社会人との交流で広がる視野
定時制は社会人の学び直しの場でもあるため、幅広い年齢層が通学しています。年の離れた社会人と対面で触れ合えるのは、大きなメリットにもなり得ます。年齢や生活環境が違えば、価値観も異なります。交流する中で、さまざまな気づきを得られ、人間的な成長につながるばかりでなく、自分のキャリアを考える上でもプラスになると思います。
少人数指導によるきめ細やかなサポート
定時制は全日制と比べ生徒数が少ないため、少人数で授業が行われます。集団授業の形を取りながらも、生徒一人ひとりの習熟度に合わせたきめ細やかな指導が可能です。中学の復習が必要な生徒へのフォロー、階級ごとの検定試験対策など、個別の事情にも配慮してもらえます。
登校や学校生活に問題を抱える生徒には、スクールカウンセラーや特別支援教育コーディネーターが寄り添います。発達障がいの専門医による生徒・保護者向けの相談会を定期的に行っている学校もあります。生徒が抱えるさまざまな問題に配慮しながら、卒業までの道のりを着実に歩むサポート体制が敷かれています。
就職支援が充実!手厚いキャリアサポート
定時制は全日制に比べ就職を希望する生徒の割合が高い傾向にあります。東京都の定時制高校での就職率は38.1%(全日制12.0%)です。(令和2年度)
就職に対するサポートも自ずと手厚くなり、多くの学校で地元企業による講話、求人票の分析と応募書類作成補助、面接練習などの支援を行っています。地元企業と密接に連携を図る学校も多く、企業訪問、インターンシップに注力する事例も見られます。
(参照:高等学校卒業者(全日制及び定時制)の進路状況 | 東京都教育委員会)
【デメリット】中途退学率が高い傾向がある
定時制高校のネガティブな面として認識しておきたいのが、中途退学者の多さです。令和5年度の中途退学率は8.0%で、全日制の1.1%、通信制の4.0%と比べ突出しています。特に1年生は12%を超えており、看過できない数字です。理由としては「学校生活・学業不適応」が最も多く、「入学はしたものの、こんなはずではなかった」と辞めてしまう状況がうかがえます。特色を正しく認識せずに入学する生徒が多いのかもしれません。
(参照:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について | 文部科学省初等中等教育局児童生徒課)
【通信制高校の特徴】自由な学び方で個性を大切に
通信制は学校数、生徒数ともに急増しており、躍進を続けています。生徒数は令和2年度時点で20万人を超えました。広域通信制高校が普及したことで、居住地に関わらず希望の学校で勉強できること、自由なカリキュラムで個性に則した学びができることなどが人気の理由です。
ただ、イメージだけで入学すると、理想の高校生活とかけ離れていたり、思うように学習が捗らない事態が生じることもあります。通信制についての正しい知識が必要です。
※この章では別途記載がない限り以下の資料を参照しています。
(参照:高等学校通信教育の現状について | 文部科学省)
「不登校者の受け皿」だけではなく多様な生徒が在籍
通信制は他人に会う必要がないことから、「不登校者の受け皿」として大きな役割を果たしてきました。「小中学校での不登校経験者」の割合は広域通信制高校で66.7%です。
しかし近年は大規模校を中心に通学コースが設置され、毎日通学できる「全日制型」をとる学校も増えています。こうした学校は「全日制高校で何らかの問題を抱えて転入せざるを得なかった」生徒のやり直しの場として機能しています。令和元年度時点で、通信制に通う28.9%は途中転入者です。
自分のペースで学力に応じた勉強ができる
通信制の授業は決まった時間に受講する必要がないため、都合に合わせて授業を受けられます。自分の活動で昼間の時間を確保できない人は、夜間や休日にまとめて受講することも可能です。単位制のため、勉強のプランニングは自由です。3年で卒業することを考えなければ、少しずつ無理のないペースで学んでいく手もあります。
高校の学習指導要領に基づく必修科目以外にも、学力レベルに応じたさまざまな講座が用意されているのも特長です。特に中学範囲の振り返りに力を入れている学校が多く、あまり学校に通えなかった生徒も基礎から復習できます。
ITや芸術など専門カリキュラムで個性を伸ばせる
学校によっては通常の勉強以外にも、プログラミング、動画編集、Web制作、ファッションなどさまざまな専門科目を用意しています。生徒たちは必修科目の傍ら、興味のある分野や将来に繋がる科目を自由に選択し、学びを深めることができます。これらの科目は自分の好きなもの、適性があるものを知り、自律的に学ぶきっかけをつくります。通信制に通う生徒の中には、勉強へのモチベーションを失っているお子さんも少なくありません。ですので、専門科目が学習の良い刺激となるのではないでしょうか。
サポート校や個別指導で学習やメンタルの不安を解消
通信制高校は自分のペースで勉強を進められる反面、自分をコントロールできないと卒業が危うくなります。通常の支援は、クラス担任や「メンター」と呼ばれる職員が行っています。しかし毎日対面で接するわけではないため、全日制や定時制ほどきめ細やかな支援は望めません。そこで、日常的な支援を目的に設置されたのがサポート校です。
サポート校は通信制高校の生徒を支援するための民間機関です。学校と提携している塾のような場所で、専門の職員がレポート補助から大学受験対策まで、幅広いニーズに応えるのが特色です。
学内でサポートを強化する動きも見られます。例えば、N/S/R高等学校(角川ドワンゴ学園)では個別指導コースを設置し、プロ講師が生徒を包括的にサポートしています。今後通信制高校の在り方が多様化することで、各学校の特色を活かした支援方法が確立されていくかもしれません。
高い評定平均により推薦系の大学入試に強みを発揮
通信制から大学を受験する場合、学校推薦型や総合型選抜などの推薦入試を利用すると強みを発揮できます。通信制のカリキュラムは難易度が高くありません。学力に自信があるお子さんなら、オール5に近い成績を狙うことも不可能ではないと思います。高い評定が期待できることから、推薦入試には有利ではないでしょうか。
まとめ〜自分の特性と未来を見つめた選択を
<全日制>
・自分に合った学校を探しやすい
・仲間と頑張る経験を積める
・難関大学への入試に対応できる学校もある
<定時制>
・さまざまなバックグラウンドを持つ生徒の学び直しの場
・個性が尊重されやすい
・社会人と交流する機会がある
・少人数できめ細やかな指導が受けられる
・就職支援が豊富
<通信制>
・不登校や全日制でトラブルを抱えた生徒など、さまざまな生徒が在籍
・自分のペースで勉強できる
・ITや芸術など個性を伸ばすカリキュラムが豊富
・サポート校や個別指導で支援を受けられる
・推薦系の大学入試に強い
高校入試はお子さんの未来のキャリアを形成する第一歩です。将来の夢はもちろん、個性や特性にも配慮しながら、自分に合った高校を選ぶことが大切です。具体的な学校選びに移る前に、課程別のポイントをしっかりと抑えておきましょう。この記事が少しでも参考になり、納得のいく学校選びを進めていただければ嬉しく思います。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。
また、受験対策をはじめとした、お子さんと保護者の方に役立つ様々な情報を発信しています。ご興味のある方はぜひ、ご参考にしてください。
家庭教師のガンバ 編集チーム ありま
こんにちは。家庭教師のガンバ編集チームです。日々の勉強やテスト、受験、不登校などのお悩みに役立つ情報を発信しています。