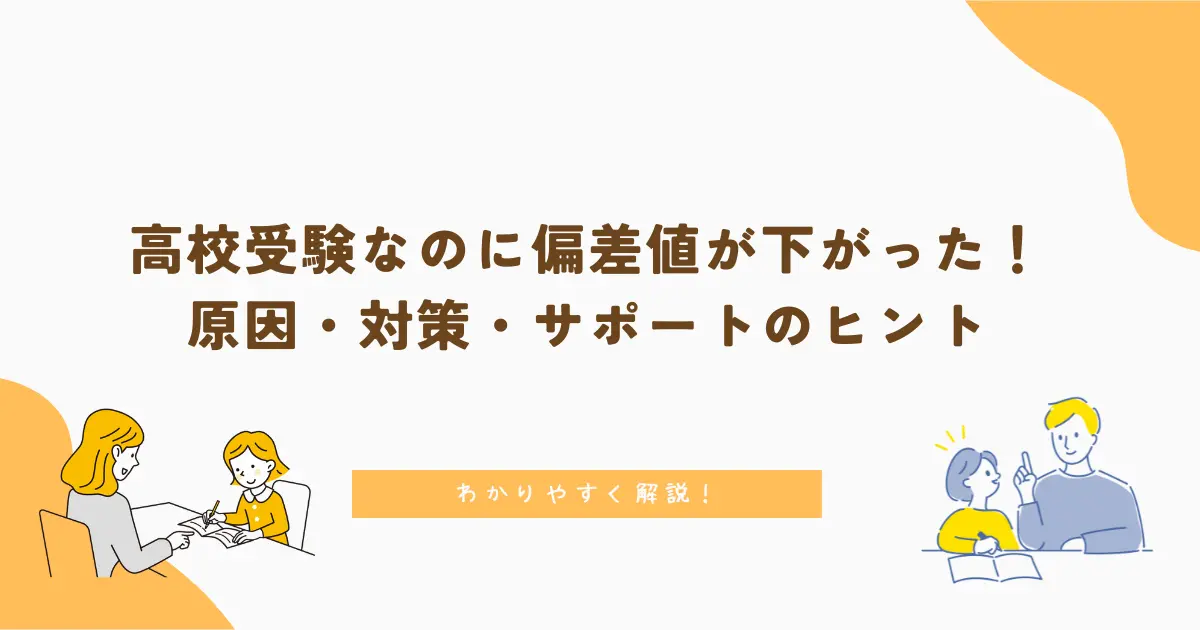高校受験を控えたお子さんやその保護者の方は、模試の結果で一喜一憂していませんか?特に偏差値を見ては、
「まずい、高校受験があるのに偏差値が下がった」
「中3になって偏差値が下がってしまった」
などのように、不安になっている保護者の方も多いのではないでしょうか。志望校の指標は偏差値で表されることがほとんどなので、偏差値が下がると焦る気持ちは自然なことと言えます。
もし偏差値が下がってしまったら、慌ててお子さんに勉強を促したり志望校を下げるのではなく、その原因を知り、適切な対策を行うことが大切です。
そこで今回の記事では、数多くの高校受験生をサポートさせていただいた私たちの経験を基に、
・偏差値が下がったときに考えられる原因
・今からできる偏差値アップ対策
・親ができるサポートのヒント
についてお伝えします。高校受験を控えたお子さんを持つ保護者の方はぜひ、ご参考にしてください。
偏差値が下がった時に考えられる主な5つの原因
まずはお子さんの偏差値が下がった原因を探ってみましょう。偏差値が下がった主な原因として、次の5つが考えられます。
原因1|勉強内容が難しくなった
学年が中1、中2、中3と上がるにつれ、やはり勉強内容はだんだんと難しくなります。一例を上げると、
数学:関数、証明
英語:長文読解
国語:古文
などのように、応用的な要素や難解な問題が増え、得点を取りづらい単元に入ることが多いです。こうした単元は得意不得意の差も出やすく、中3になって「偏差値が下がった」という現象は意外と起こりやすいことでもあります。
原因2|模試や問題との相性が悪かった
高校受験に向けた模試にもいくつか種類があり、同じ難易度の模試であっても、主催元が前回と違えば問題の傾向も異なります。
苦手な形式や出題パターンが重なった場合、点数が取れず、一時的に「偏差値が下がった」となるケースもあります。あらかじめ模試ごとの特徴を知っておくと、結果を見る時の参考になります。
原因3|周りが受験勉強に本腰を入れ出した
高校受験が近づくにつれ、だんだんと受験勉強に本腰を入れ始めるお子さんが増えてきます。たとえお子さんがこれまでと勉強量やペースを落とすことなく取り組んでいても、周りの勉強量が増えたりペースが上がると全体の平均点が上がることで、結果的にお子さんの偏差値が下がることもあります。
原因4|勉強時間が減った
シンプルに、お子さんの勉強時間が減った可能性も考えられます。中3は高校受験を控えた学年でもありますが、学校生活や学校行事では中心となって引っ張る学年です。
もし部活動をしていれば、最後の大会に向けて部活に重きを置いてしまいがちです。部活引退後であれば気が緩んだり、燃え尽き症候群のようにやる気が出なくなってしまうケースもあります。
また、学年が上がり友達とのオンラインゲームやSNSに割く時間が増えると、勉強時間が減りがちです。一度毎日どれくらい勉強しているかを紙に書き出すなどして、見直してみると良いと思います。
原因5|勉強のやり方が合っていない
「勉強時間は増えているのに偏差値が下がった」という場合は、勉強方法がお子さんに合っていない可能性もあります。
せっかく長い時間勉強ができているのであれば、よりお子さんに合った勉強法や効率の良い方法に変えることで、成績の伸びを期待できます。
「何を(内容)、どれだけ(量・時間)、どのようにやったか(方法)」を見直してみると良いのではないでしょうか。
「自分に合った勉強法を探すのは大変」という方は、家庭教師を試してみてはいかがでしょうか?
家庭教師のガンバではまずは無料体験を行っております。(しつこい勧誘はありませんのでご安心ください)
今からできる偏差値アップの4つの対策
偏差値が下がってもあきらめず、
・今すぐに取りかかれること
・やるべきこと
を明確にすれば、高校受験までに伸びしろは十分にあります。以下に、効果が期待できる、偏差値アップのための対策を4つご紹介します。
対策1|苦手科目の重点対策に絞る
高校受験のコアシーズンは、一般的に私立で1月~2月、公立は2月~3月です。中3になった時点でも1年を切っているので、比較的短期間で偏差値を上げて行くことになります。
得意な教科の点数を伸ばすのも大事ですが、短期間で偏差値を上げるには、現時点で点数が取れていない「苦手科目」を対策する方が効果的です。
たとえば数学が苦手なら、まずは「1次関数」や「証明問題」など、高校受験の頻出分野に絞って対策すると良いと思います。
現時点で基礎問題が解けていないのであれば、基礎問題ができるようになるだけでも得点はずいぶん安定します。得意科目や苦手科目については次の記事もご参考にしてください。
得意科目と苦手科目の違いはなぜ生まれるのか?原因と克服法を徹底解説
対策2|模試の解き直しを徹底する
模試は、結果から偏差値や合否判定をみるだけではとても「もったいない」です。模試は偏差値アップのためのヒントの宝庫です。なぜなら答案には、
・解けた(できる)問題
・間違えた(できない)問題
が明確に表れているからです。模試の解き直しと復習をすることで、高い学習効果が期待できます。
①間違えた問題の原因は何か(調べる)
②同じ問題が解けるか(解法を知って解きなおし)
③似た問題も解けるか(類似問題を解く)
このプロセスを徹底することで、高校受験までに着実に実力がついていくはずです。
対策3|毎日〇〇分の学習習慣をつける
学習習慣の定着は、多くのお子さんにとって課題でもあります。特に高校受験を控えている場合、毎日少しでも学習する習慣をつけることが大切です。
『〇〇分』は、お子さんに合わせて15分だったり、30分だったりと、続けやすい時間から取り組み、徐々に増やしていくことが効果的だと思います。
毎日の学習習慣が定着すれば自然と力が蓄積されていきます。たとえ短時間でも、毎日続けることで記憶の定着が加速します。
また、「続けられた」という『小さな成功体験』を積み重ねることで、その後の学習にも良い影響を及ぼします。『小さな成功体験』については次の項目でもう少し詳しくお伝えします。
対策4|”やればできる”という『小さな成功体験』を経験する
高校受験を控えていて気持ちは焦るものの、偏差値が下がったことでお子さんは「どうせやってもできない」と感じてしまいがちです。だからこそ、『小さな成功体験』を経験することがとても大切です。具体的には、
・解けない問題が解けた
・間違えた漢字を覚えた
・小テストで5点アップした
などのように、達成しやすい課題をクリアすることで”やればできる”という自信につながり、偏差値アップへのキッカケやエネルギーとなります。
親ができるサポートのヒント
もし、偏差値が下がって落胆しているお子さんを目の前にしたら、親としては「何とかしてあげたい」と強く感じるのではないでしょうか。ここからは、保護者の方が親としてできるサポートのヒントをいくつかお伝えしたいと思います。
ヒント1|お子さんを責めずに落ち着いて話を聞く
偏差値が下がった結果を見てしまうと、つい「ちゃんと勉強してるの?」と言いたくなってしまうこともあるかも知れません。特に高校受験が近づいているとなると、不安も大きくなり、なおさらではないでしょうか。
ただ、ここは、お子さんの気持ちを守るためにも否定せず、まずは見守ったり、結果を一緒に受け止める姿勢が大切だと思います。
【声掛けの例】
◆気持ちに寄り添いたい場合
「今回の結果はそうだったんだね」
「悔しかったね」
◆お子さんが頑張っていたのに偏差値が下がった場合
「がんばってたの、ちゃんと知ってるよ。」
◆結果を受けて自信をなくしている場合
「模試は今の自分を知るためのものだから、いいんだよ。」
◆「もう無理!」と投げやりになっている場合
「諦めるのはまだ早いよ。つまづきは成功のもとだよ。」
お子さんが話をしたがらない場合は、そっと見守り、いつでも話を聞ける雰囲気を作っておくのもよいと思います。落ち込んでいるときに無理に励まそうとすると、逆効果になることもあります。
・そっと見守る
・好きな食べ物を用意してあげる
・一緒にテレビや動画を見る
などの何気ない行動や一緒にいる時間によって、「自分のことを気にかけてくれてる」と感じ、お子さんの心は癒されるのではないでしょうか。
お子さんが少し落ち着いたタイミングで、「次はどうするか、一緒に考えてみようか。」などのように、次の行動へつながるような声掛けを試みるのもよいと思います。
家庭教師のガンバでは、児童心理学の先生と共同制作をした『〜子どものやる気を引き出す〜 魔法の言葉がけ』を、ご希望の方には無料でプレゼントさせていただいています。
ヒント2|模試の結果を一緒に分析する
「対策2」の項目でもお伝えしたように、模試は偏差値アップのためのヒントの宝庫です。高校受験へ向けて模試を次に最大限に生かすには、お子さんと一緒に分析をするのもおすすめです。
くり返しになりますが、模試結果は点数や偏差値だけでなく「どの問題を間違えやすいのか」「どの単元が弱いか」が分かる貴重な資料です。
お子さんだけではミスの傾向や間違えやすい問題、苦手な単元や教科を分析するのは難しいかもしれません。一緒に分析することで、結果を冷静に見ることもできます。
ヒント3|志望校の見直しは焦らない
偏差値が下がったからといって、志望校の見直しを焦らないようにしましょう。とはいえ、志望校との距離感を確認しておくことは大切です。志望校に対しては次の視点から見ることがポイントです。
◆志望校との偏差値の差は指標としてみる
志望校に対して「偏差値があと〇足りない」となった場合、
・どうすれば届くか
・どこを伸ばせばいいか
に意識を向けるのことが大切です。
◆偏差値だけで判断しない
高校受験の合否は、偏差値だけではなく、次の要素も大事になります。
・内申点
・面接・小論文の有無
・学校ごとの特色選抜 など
ですので、「偏差値があと〇足りないから無理」と決めつける必要はありません。
◆3段階の志望校設定
一つの高校だけを目指すのではなく、現段階で、「チャレンジ校」「実力相応校」「安全校」の3段階で志望校を設定しておくと安心です。
・チャレンジ校(偏差値的にやや上)
・実力相応校(今の偏差値で現実的)
・安全校(確実に合格できそう)
志望校をバランスよく考えておくことで、心の余裕も生まれます。
◆最終的な決定はまだ先でも大丈夫
先にもお伝えしましたが、高校受験のコアシーズンは一般的に私立で1月~2月、公立は2月~3月です。1年を切っているとはいえ、まだまだ「成績を伸ばせる時期」です。
特に高校受験では、取り組み次第では最後の追い込みで飛躍的に伸びるケースも多々あります。模試の結果を受けてすぐに決めず、じっくり力をつけていきましょう。
塾・個別指導・家庭教師の活用
独学や家で対応しきれない場合は、塾・個別指導・家庭教師といったプロの力を借りるのも手です。忙しい昨今、保護者の方がじっくり問題を解いたり分析する時間はなかなかとりづらいというご家庭も多いのではないでしょうか。
また、勉強の大筋は変わっていないとはいえ、解き方は保護者世代と変わっているケースもあります。高校受験に関する情報等も変わっているケースもあります。ですので、現役のプロに頼むのもいいと思います。高校受験対策をやってきたノウハウもしっかり持っています。
すでに塾に通っている場合は塾の担任とこまめに連絡を取ったり、塾だけでは難しい場合は、苦手科目に対して個別指導や家庭教師の併用も有効です。
お子さん一人ひとりに合わせた個別の勉強法やサポートは家庭教師が最適解!完全個別指導で、学習計画から進捗管理、教科指導やメンタルサポートをおこないます。
まとめ
今回は、高校受験を控えた中3で偏差値が下がってしまったお子さんや保護者の方へ向けて、
・偏差値が下がったときに考えられる原因
・今からできる偏差値アップ対策
・親ができるサポートのヒント
についてお伝えしました。まずは原因を探り、対策を講じていくことがおすすめです。その時に、保護者の方のサポートがお子さんの大きな支えになります。
特に高校受験は、人生で初めての大きなプレッシャーとなるお子さんも多いです。お子さんに寄り添い見守りながら、先の行動へ導いていけるとよいのではないでしょうか。
「偏差値が下がった」からといって諦めたり焦ったりせず、志望校合格への道を着実に進んでいきましょう!
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。
また、受験対策をはじめとした、お子さんと保護者の方に役立つ様々な情報を発信しています。ご興味のある方はぜひ、ご参考にしてください。
家庭教師のガンバ 編集チーム ありま
こんにちは。家庭教師のガンバ編集チームです。日々の勉強やテスト、受験、不登校などのお悩みに役立つ情報を発信しています。