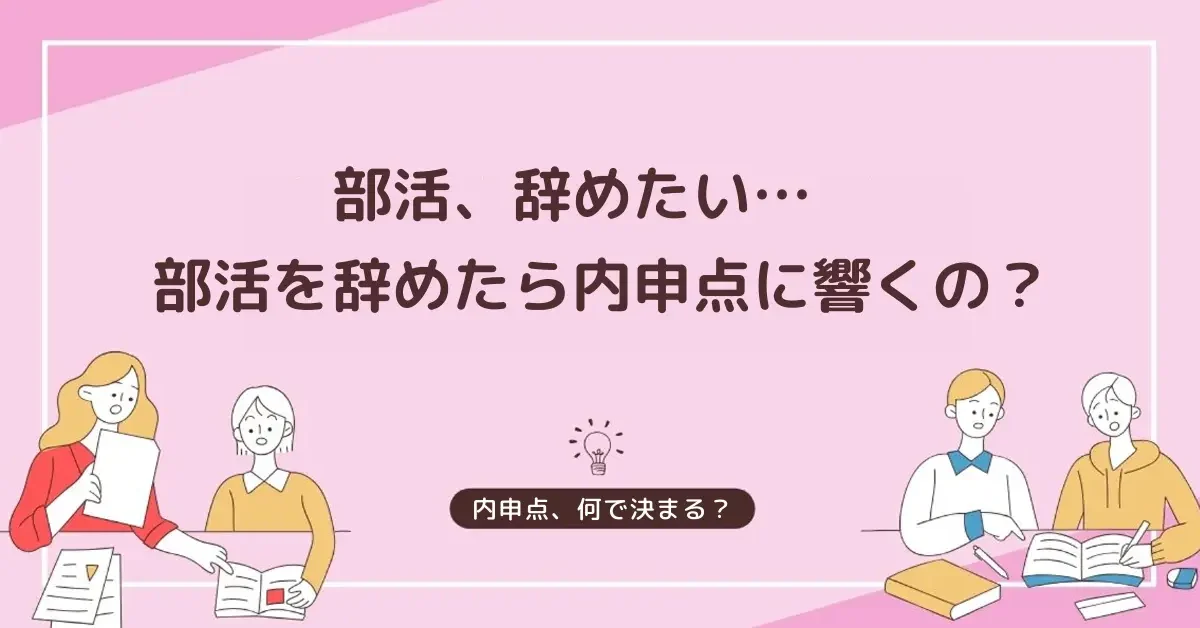中学生になると、多くのお子さんが何らかの部活動に所属します。仲間と目標に向かって努力したり、先輩後輩との関わりを学んだりする貴重な体験ができる一方で、「思っていたのと違う」「勉強と部活の両立がきつい」「人間関係がつらい」など、様々な理由で「部活を辞めたい」と感じるお子さんも少なくありません。
ただ、「部活を辞めたら内申点に影響するの?」と心配される方も多いと思います。高校入試では、内申点が大きく影響するため、心配になるのも無理はありません。
今回は、実際に部活動の有無が内申点にどう関係するのか、辞めたことで不利になる可能性はあるのかについて、中学校での評価の仕組みをもとに整理します。また、辞めるかどうかを親子で冷静に判断するために考えておきたい視点や、辞めた場合のフォロー方法などについてもご紹介します。
内申点とは何で決まるのか?
内申点は、各教科ごとの「観点別評価」をもとに算出されます。評価項目は主に「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「技能」「知識・理解」で、提出物や授業態度、テストの点数などが総合的に判断されます。内申点は高校入試において重要な選抜資料のひとつであり、特に公立高校では学力検査と同等、またはそれ以上に重視されるケースもあります。
部活動は内申点にどこまで影響する?
内申点は基本的に教科の評価で決まるため、部活動の有無が直接的に点数に影響することはほとんどありません。ただし、通知表の「特別活動の記録」に部活動の活動状況が記載されることがあり、これが高校に提出される調査書に反映される場合があります。
「特別活動の記録」は、授業以外の活動(部活動、委員会、生徒会、学校行事など)への参加状況をまとめた欄です。内申点とは別に扱われますが、調査書の一部として高校側に提出されるため、全く無関係ではありません。ただし、内容はあくまで「事実の記録」であり、良い・悪いの評価が加えられるわけではありません。
辞めた理由やその後の過ごし方が重要になります。熱心に取り組んでいた実績は加点材料になることもありますが、辞めたからといって即マイナス評価になることはありません。
部活を辞めることのメリットとデメリット
もちろん一番のメリットは、悩みの種であった部活動と距離を置くことが出来る点にあります。また時間と体力に余裕ができ、勉強や趣味に集中できるメリットがあります。特に受験を控えている場合は、自分のペースで学習できる環境が整いやすくなります。
一方で、チーム活動を通して得られる経験や人間関係、責任感などの成長機会を失うというデメリットも存在します。また、これまでのチームメイトと気まずくなってしまったり、孤独感を感じてしまったりすることもあるかもしれません。どちらが今の自分にとって必要かを見極め、冷静に判断することが大切です。
担任や顧問の先生に相談すべきタイミングと方法
辞めたい気持ちが明確になったら、早めに担任や顧問の先生に相談しましょう。無断で辞めたり曖昧なまま活動を休むのは、誤解を招いたりトラブルの元になります。正直に気持ちや理由を伝えることが大切です。「勉強に集中したい」「体調がつらい」など、具体的に話すことで先生も理解しやすくなります。相談は、お子さんだけでなく保護者が同席して行うと、より円滑に進むと思います。
部活以外で評価されるには?
部活動を辞めたとしても、内申点や高校の調査書で評価される機会がなくなるわけではありません。実際、学校生活における評価は「特別活動の記録」などで、部活動だけでなく、委員会活動やボランティア、生徒会活動、学校行事への参加など、多様な面から見られています。これらはすべて「学校生活への主体的な参加」として認められ、評価対象となるのです。
例えば、学級委員や生徒会役員としての活動は、責任感やリーダーシップ、協調性を示す良い機会となります。こうした役割を果たすことで、周囲との関わり方や問題解決能力を養うことができ、先生方の評価にもつながります。また、清掃活動や委員会活動など、学校の運営や環境整備に携わる委員会も重要です。これらの活動は、積極的に取り組む姿勢が評価されやすく、内申書にも反映されます。
さらに、校外でのボランティア活動も学校評価の対象になる場合があります。地域の清掃活動や福祉施設での支援など、社会に貢献する経験は、学習以外の視点で子どもの成長を示す材料となります。学校によっては、こうした外部活動の報告を積極的に受け入れ、調査書に記載しているケースも増えています。
部活動を辞める決断をした後は、こうした代替の活動に目を向けることも大切です。また、多様な経験を積むことで、受験時の面接や志望理由書でも説得力が増します。
もちろん、無理に何かに参加することが目的ではありません。あくまでも「自分らしく学校生活に関わること」が重要です。お子さんと話し合いながら、負担にならない範囲で挑戦できる活動を探してみましょう。部活を辞めたとしても、学校生活への積極的な参加があれば、内申点や高校入試の評価において十分にプラスになります。
辞めた後の過ごし方
部活動を辞めた後は、急に自由な時間が増えるため、生活リズムが乱れやすくなることがよくあります。これまで部活の練習や試合で忙しかった日々から一転、時間に余裕ができると、ついダラダラと過ごしてしまい、生活が不規則になったり、集中力が落ちたりすることがあります。特に受験生の場合は、この時期の生活習慣が学習の質に大きく影響するため、辞めた後の過ごし方を工夫することが非常に重要です。
まずは、毎日のスケジュールを見直し、家庭学習の時間をしっかり確保することが基本です。勉強だけでなく、趣味やリラックスの時間もバランスよく取り入れることで、気持ちの切り替えがしやすくなり、長時間の学習にも耐えられる体力と集中力が保てます。例えば、朝は決まった時間に起きて勉強を始め、夕方には軽い運動や散歩をする、といったメリハリのある生活リズムを意識するとよいでしょう。
また、部活動を辞めたことで運動不足になりがちなので、軽いストレッチやウォーキング、ヨガなどを日課に取り入れることもおすすめです。運動は身体の健康を維持するだけでなく、ストレス解消や気分転換にも効果的で、精神面の安定にもつながります。自宅でできる簡単な運動でも十分ですし、短時間でも続けることが大切です。
さらに、自分自身でスケジュールを管理する経験は、自己管理能力の向上にもつながります。部活のスケジュールがあった頃は、ある程度強制的に時間を使っていましたが、辞めた後は自分で計画を立てて実行しなければなりません。これは大人になってからも役立つ大切な力なので、親や先生のサポートを受けつつ、計画を立てる習慣を身につけていきましょう。
最後に、辞めた後の過ごし方は「自分に合ったペース」を見つけることがポイントです。親子で話し合いながら、健康的で充実した毎日を送れるよう工夫していくことが大切です。
親としてできること
お子さんが「部活を辞めたい」と話してきたとき、親としてまず心がけていただきたいのは、その気持ちを否定せずにしっかりと受け止めることだと思います。親としては「最後までやり抜きなさい」と励ましたくなるかもしれませんが、お子さんはその言葉をプレッシャーや否定と感じてしまうこともあるのではないでしょうか。その場合、本音を話さなくなり、気持ちを押し殺してしまうかもしれません。だからこそ、まずは「どうして辞めたいのか」「何がつらいのか」をじっくり聞くことが大切だと思います。
部活を辞めたいと思う背景には、体力的な疲労や精神的なストレス、勉強との両立が難しいと感じていることなど、さまざまな理由が考えられます。例えば、部活の練習時間が長すぎて勉強時間が足りない、部活の人間関係がつらい、体調が優れないなど、一つの原因だけでなく複数の要因が重なっていることも多いでしょう。親がその理由を理解しようと努めることで、お子さんは安心して話しやすくなり、心の負担も軽くなるはずです。
また、「辞めることは甘えではない」ということを伝えることも大切ではないでしょうか。根性論や我慢を美徳とする風潮はありますが、無理をして心身の健康を損なってしまっては本末転倒です。お子さんの心身の健康や将来のために、自分の判断で環境を変えることは決して悪いことではありません。
親がその選択を認め、尊重する姿勢を示すことで、自信を持って前向きに次のステップを考えられるようになります。親としては無理強いせず、お子さんのペースに合わせながらサポートし、励ますことが大切だと思います。
最後に、親子のコミュニケーションを大切にし、日頃から何でも話せる関係を築いておくことが、お子さんが困ったときに相談しやすくなるポイントです。部活を辞めるかどうかの決断は簡単ではありませんが、親の理解と支えがあれば、お子さんだけで考えるより良い選択ができるはずです。
まとめ
部活動を辞めること自体が、即座に内申点に悪影響を及ぼす訳ではありません。内申点は基本的に教科ごとの学習態度や提出物、テスト結果などをもとにした「学習の記録」によって決まります。ただし、部活動での態度や頑張りは「特別活動の記録」として記載される可能性があるため、全く無関係とは言い切れません。
大切なのは、辞めた後も前向きに学校生活を送ることです。たとえばボランティア活動、生徒会、委員会など、他の場での活動をしっかりと行えば十分に評価されます。また、部活を辞めた理由が明確で、勉強や健康などを優先した結果であるなら、それも一つの判断として尊重されるべきです。
無理して続けて心身の健康を崩すより、自分に合った選択をすることが将来にもつながります。親子でしっかり話し合い、納得できる決断ができればいいのだと思います。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。