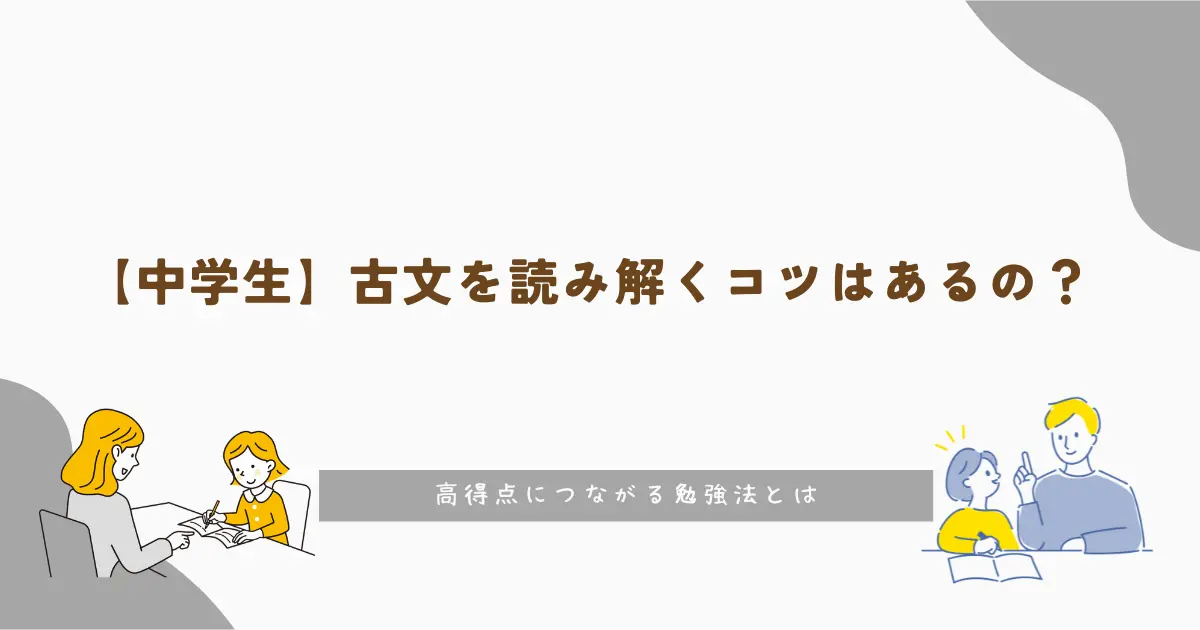中学校の国語に初めて古文が登場すると、「えっ…これ本当に日本語?」と驚く人も多いかも知れません。見慣れない言葉や言い回しに戸惑って、なんとなく読み飛ばしてしまったり、覚えられずに苦手意識が強くなってしまったり…。そんな声をよく耳にします。
でも実は古文って、ちょっとしたコツをつかめば得点源に変わる科目です。特に現代文が苦手な場合でも、古文でしっかり点を取れば、国語全体の点数アップにもつながります。そこで今回は、中学生の皆さんが古文を味方につけられるように、
・古文が苦手になってしまう人の特徴
・初めて読む古文をスムーズに理解するポイント
・苦手を克服してテストで高得点を取る勉強法
をやさしく解説していきます。「今までの勉強で何が足りなかったのか」を知って、ちょっとずつ古文への苦手意識を減らしていきましょう。読み終える頃には、古文がぐっと身近に感じられるはずです。
そもそも古文の勉強って本当に必要なの?
古文を勉強していると、ふと「なんでこんな古い言葉を覚えないといけないの?」って思うこと、ありませんか?
たしかに文部科学省は「我が国の言語文化を享受し、継承・発展させるため」と説明していますが、中学生のみなさんからすると、それだけでは少しピンとこないかもしれませんよね。
そこでまずは、「今のうちに古文を勉強しておくとどんなメリットがあるのか」を、わかりやすくお話しします。(参照:中学校学習指導要領解説 国語編 p.5 | 文部科学省)
高校入試で意外と得点源になる!
実は古文って、高校入試ではけっこうな頻出分野なんです。しかも現代文の読解がちょっと苦手な人でも、古文でしっかり点を取れるケースも多いんです。
なぜかというと、中学で習う古文の範囲はとても限られていて、単語も文法も“最低限”しか出てきません。授業の目的も「古典独特の表現や文体に慣れること」に重点が置かれているので、慣れてしまえばぐんと読みやすくなります。
さらに入試問題の古文には、たいてい現代語訳や注釈がしっかり付いています。ちょっとした読み方のコツをつかめば、ストーリーも理解しやすく、安定した得点につなげやすいんです。
高校から本格的に始まる古文学習の“下地”になる
古文の基礎を今のうちに学んでおくことは、高校に入ってからのスタートをスムーズにするためにも、とても大切です。
高校の古文は、中学とは比べものにならないくらい本格的。文法や単語は一気に増え、正確な訳も求められます。最初は大変に感じるかもしれませんが、中学のうちに基礎を身につけておけば、授業内容がぐっと理解しやすくなるんです。
逆に、高校に入ってから古文に苦手意識が残っていると、一気に“古文嫌い”になってしまう危険も…。そうならないためにも、中学生の今こそ、古文の土台をしっかり作っておきましょう。
中学校で古文が苦手になってしまう人の特徴
「どうしてこんなに点数が取れないんだろう…」
「覚えたはずなのに、テストになると全然出てこない…」
そんなふうに感じている人は、もしかすると古文が苦手になる“ある共通パターン”にはまっているのかもしれません。まずは自分の勉強法をちょっと振り返ってみましょう。
現代文と同じ感覚で読もうとしている
古文は同じ日本語…そう思って現代文と同じ感覚で読んでしまうと、ほぼ間違いなくつまずきます。私たちが普段読む現代文は、言葉も文法も今の感覚に合っていて、多少主語や接続詞が省かれていても文脈で自然に意味をつかめます。
でも古文になると、単語や表現がガラッと変わるため、次のようなことを意識しないと話が頭に入ってきません。
・主語(動作をしている人)は誰?相手は誰?
・物語はどう展開している?
・当時の時代背景はどうなっている?
こうしたポイントを意識して読む練習を重ねることで、だんだん古文のリズムやクセに慣れていけます。
単語だけ覚えて満足してしまう
単語を覚えることは大事ですが、「単語の暗記=古文が読める」ではありません。古文には、助詞や助動詞、独特な敬語表現など、意味をつかみにくくする要素がたくさんあります。単語を知っていても、文章として読んで練習しなければ、頭の中で単語だけが浮いてしまい、内容がつながらないのです。
単語を覚えたら、それを文章の中でどう生かすか、演習を通して身につけていきましょう。
初めての文章を音読しない
古文の勉強は、英語の勉強とちょっと似ています。英語の文章を読むとき、黙読だけより声に出したほうが覚えやすいですよね。古文も同じで、音読することでインプットとアウトプットを同時に行え、記憶に残りやすくなります。
特に初めて読む文章は、声に出して読むことで言葉のリズムや文章の流れを体で感じられます。逆に音読をしないと、難しい文章にぶつかったときに対応しにくくなってしまいます。
中学生が古文を読めるようになる3つのポイント
じゃあ、中学生が古文をスラスラ読めるようになるには、どうしたらいいのでしょうか?
中学の範囲では、細かい訳を自力で完璧にできるようになる必要はありません。ゴールは「古文に慣れて、初めての文章でも注釈や現代語訳をヒントに読み解ける状態」にすることです。
そのために押さえてほしいのが、この3つのポイントです。
・単語と文法の暗記
・音読
・多読
一つひとつ解説しますね。
①中学で習う単語と文法は最低限!全部覚えよう
中学校で扱う古文単語や文法は、本当に“最低限”の基礎知識です。だからこそ、定期テストでも問われますし、高校入試でも「知っていて当たり前」という前提で出題されます。ここはしっかり暗記しましょう。
単語は「現代にない語」と「意味が違う語」を重点的に
中学古文の単語数はおよそ100語。その中でも特に覚えたいのは、現代では使わない言葉と、意味が大きく変わっている言葉です。
<現代にない語>
・つれづれなり(退屈だ)
・いみじ(とても〜)
・おはす(いらっしゃる)
<意味が異なる語>
・あはれなり(しみじみ心にしみる)
・ながむ(物思いにふける)
・かなし(かわいい)
こういう語は、現代語の感覚では推測できません。覚えておかないと物語全体がつかみにくくなります。
文法は助動詞もチェック!
中学では文法の中でも「係り結びの法則」を習いますが、それだけでは足りません。実は、一部の助動詞を知っているかどうかが文章理解を大きく左右します。
特に注意したいのは「ぬ」という助動詞。現代語の「打ち消し」とは使い方が違い、基本は「完了(〜した)」で訳します。
例:来ぬ → 来た
こうした現代語と感覚が違う助動詞は、見つけたら必ず確認する習慣をつけましょう。
②音読で古文特有のリズムに慣れる
古文の勉強は、まず音読から始めるのがおすすめです。特に中1・中2のうちは、音読しないと単語の区切りやリズムがつかめませんし、記憶にも残りにくいと思います。
音読は、歴史的仮名遣いや古文特有の言い回しにも自然と慣れさせてくれます。助動詞や敬語の形を見ても「そういうものだな」と受け止められるようになるんです。
新しい文章に出会ったら、まずは「声に出して読んでみる」。これを習慣にしてみましょう。
③数をこなして“読み慣れ”を作る
中学古文のゴールは「一字一句訳せること」ではなく、「長い文章や初めての作品でも抵抗なく読めること」です。そのためには、出来るだけ、学校で扱う文章以外の文章にもチャレンジしましょう。
問題集を活用して、さまざまな古文に触れてみましょう。物語、説話、紀行文、軍記物語、随筆…ジャンルによって登場人物や会話の多さ、和歌の有無などが違います。いろいろな種類を経験しておくと、本番で「あ、このタイプの文章、読んだことある!」という安心感が持てます。
古文の苦手を克服し高得点に導く勉強法〜復習編
古文を得意にするポイントがわかったら、次は「どうやって実践するか」を考えましょう。ここで大切なのは、授業のあとにしっかり復習することです。毎日の少しずつの積み重ねで、苦手意識はどんどん薄れ、自然と高得点を狙えるようになります。
現代語訳と対比させながら音読する
復習の基本は、音読です。授業中に先生が読んだときのリズムや単語の区切りを覚えておき、家でゆっくり一語ずつ確かめながら声に出して読んでみましょう。
さらに、現代語訳のノートを横に置き、古文と対比させながら音読すると効果的です。単語の意味や現代語との違いを意識でき、古文特有のリズムや感覚が体に染みついてきます。
単語はイメージと文脈の中で覚える
単語を覚えるときは、ただ訳語を丸暗記するのではなく、文章の中でイメージを膨らませるのがポイントです。
たとえば『枕草子』で「あはれなり」を覚えるとき、「しみじみと趣深い」と訳だけを覚えるのではなく、山に沈む夕日を見上げ、飛びゆく鳥に感動している自分を想像してみましょう。文章の情景と結びつけることで感情が共鳴し、単語の意味がぐっと定着しやすくなります。
自分なりに訳を作って正解と比べる
音読や単語の確認ができたら、次は自分なりに訳を作ってみましょう。正確さは気にせず、習った知識を使って文章を自分の言葉に置き換えることが大切です。
・主語や助詞を補ってみる
・会話には「」をつけてみる
こうした作業を通して、古文の表現や文体を体で覚えていきます。その後、正解と比べて違いを確認すれば、自然と文章の読み方や古文の感覚が身についていきます。
古文の苦手を克服し高得点に導く勉強法〜受験勉強編
中学範囲の古文では、細かい訳や文法よりも「読み慣れ」がポイントです。特に高校入試で初めての文章に出会ったときに臨機応変に対応できる力をつけるには、問題集を使った演習が欠かせません。
その際、音読や単語確認とあわせて、次の2つのポイントを意識するとさらに効果的です。
文章を読むときは常に主語(動作主)を意識する
初めて読む文章では、ストーリーを正しく理解するために「主語は誰か」を意識することが大切です。古文では、主語が省かれていることが多く、気づかないうちに視点が変わっていたり、誰が誰に何をしているのかを取り違えることもあります。
・前後の流れ
・敬語の有無
・注釈の内容
こうした要素を確認しながら、文章を読む習慣をつけましょう。特に難しい文章ほど、主語を押さえることが理解のカギになります。
文脈がつかめなくなったポイントを把握する
問題集を解いていて「ここがわからなかった」という経験は誰にでもあります。でも、現代語訳を見て終わりにするのではなく、大切なのは「どこで、なぜ意味が取れなかったのか」を明確にすることです。
文脈を追いながら、わからなくなった箇所をチェックしてみましょう。原因を見つけると、次のような課題が浮かび上がります。
・単語力が足りなかった
・主語を取り違えていた
・注釈をよく読んでいなかった
こうした課題を復習や次の演習に活かすことで、苦手を少しずつ克服できます。
さいごに | 中学の古文は慣れが全て!得意分野に変えられる
古文の勉強は、単語、文法、現代語訳など覚えることが多く、大変に感じるかもしれません。でも中学生にとって大切なのは、文章の数をこなし、古文の表現や文体に慣れることです。
初めての文章でも抵抗なく読めるようになれば、高得点を取れる可能性はぐっと高まります。今は細かい訳にこだわらず、文章全体のストーリーをつかむことを意識しましょう。
中学のうちに得意分野にしておけば、高校で古文の学習が本格化しても、楽しく効率的に取り組めます。国語全体の得点源としても、大きな武器になるはずです。
まずは授業で進めた範囲の音読から、少しずつ始めてみましょう。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。
また、受験対策をはじめとした、お子さんと保護者の方に役立つ様々な情報を発信しています。ご興味のある方はぜひ、ご参考にしてください。