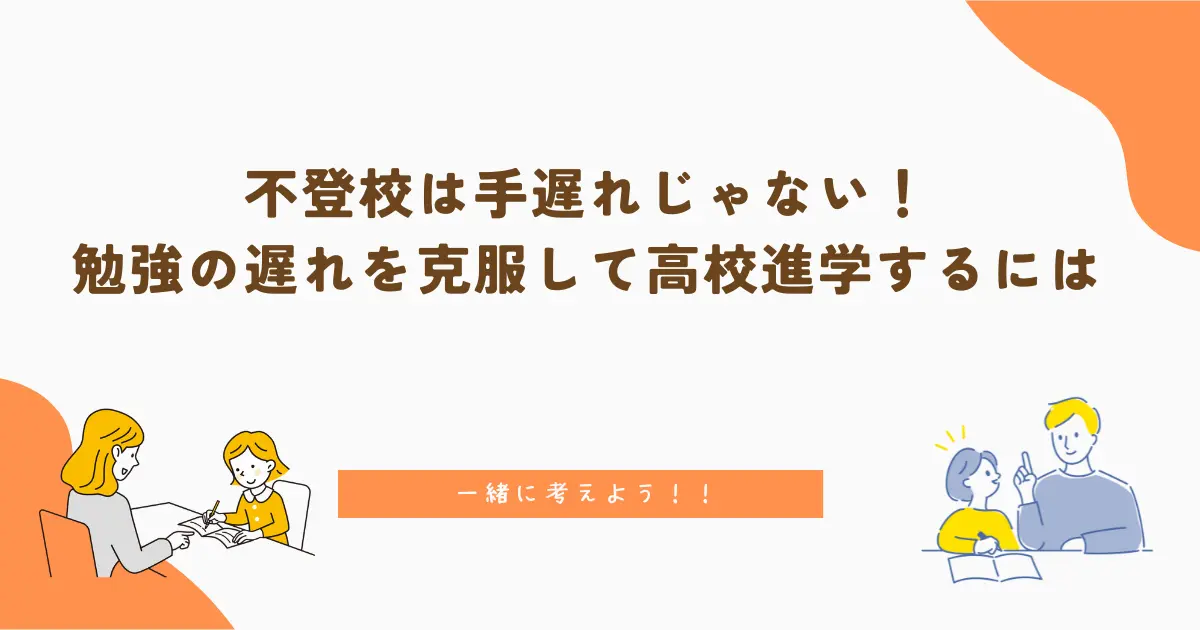中学校に通えていないとき、「勉強の遅れ」が気になる方も多いのではないでしょうか。「このまま置いていかれちゃうのかな…」と不安になってしまうかも知れません。
でも安心してください。不登校だからといって、すぐに学力が落ちてしまうわけではないんです。勉強できる環境を整えて、少しずつ学習習慣を身につければ、学校の内容に追いつくことは可能です。定期テスト対策も、高校入試にだって対応できます。
ただし、大切なのは「早めに取りかかること」。「ちょっとマズイかも…」と感じたときこそがスタートの合図です。勉強しない時間が長くなるほど、一人で追いつくのが大変になってしまいます。
とはいえ、いざ勉強を始めようとしても「何から手をつければいいの?」と悩んでしまいますよね。そこで今回は、不登校から学力を取り戻すために必要なことを、
・今すぐできる準備
・勉強に追いつくためのポイント
・学習をサポートしてくれる外部機関
にわけてご紹介します。「これならできそう!」と思えるヒントが見つかれば嬉しく思います。また、お子さんを支える保護者の方に向けても、効果的なサポートの方法を解説しています。「親はどう関わればいいの?」と迷っている方も、ぜひ参考にしてみてください。
不登校でも手遅れにならない!勉強の遅れは取り戻せる
不登校の期間が長くなると、勉強が追いつきにくくなるのは確かです。授業で先生から直接説明を受けられないと、疑問がどんどん積み重なってしまうからです。
ただし、それで「もう無理…」というわけではありません。塾や家庭教師、フリースクールなどで先生からわかりやすく教われば、疑問を一つずつ解消していけます。時間は少しかかるかもしれませんが、学校の授業に追いつくことは十分可能なんです。
大切なのは、なるべく早めに勉強を始めることです。勉強しない時間が長くなると、解けない問題が積み重なり、自分だけでは解決できなくなってしまいます。
日頃から少しずつ教科書を進めたり、塾や家庭教師に質問できる環境をつくったりすると安心です。
不登校からでも高校受験・高校進学はできる
「勉強を頑張っても、不登校だと高校に進学できないんじゃないの?」そう思ってしまうのも無理はありません。たしかに公立高校の多くは、調査書(内申点や欠席日数)を重視します。その点では、不登校は不利になることもあるのです。
でも、実は私立高校や通信制高校なら、不登校だからといって不利にならないケースがたくさんあるんです。
調査書を重視しない私立高校もある
私立高校の中には、調査書をあまり重視しない学校が少なくありません。なかには「調査書を全く使わない」入試を行う学校もあるんです。
特に首都圏の私立高校では、このような事例が多く見られます。たとえば東京都の私立高校は、調査書の影響を受けない「オープン入試」が基本。だから不登校でも不利にならず、実力で挑戦できるんです。
学力試験がない通信制高校という選択
「入試に学力試験があるのは不安…」という人には、通信制高校という道もあります。通信制高校は調査書を気にする必要がないだけでなく、学力試験がない学校もほとんど。
授業もレポート提出やオンライン学習が中心なので、不登校を経験したお子さんでも無理なく続けられる仕組みになっています。
不登校から勉強の遅れを取り戻すための準備
「高校に行けるかもしれないなら、ちょっと頑張ってみようかな」そう思えた人もいるかもしれません。でも、いきなり勉強を始める前に、実は準備しておくといいことがあるんです。土台を整えるだけで、勉強に向かいやすくなります。
生活リズムを整えて勉強時間を確保する
まずは生活リズムを見直してみましょう。寝る時間や起きる時間がバラバラだったり、好きなタイミングで食事をしていると、頭も体も「勉強モード」に切り替わりにくいんです。
私たちの体には「セロトニン」という物質があって、これが不足すると集中力や意欲が落ちてしまいます。セロトニンは、早寝早起き・規則正しい食事・朝の光を浴びることで増えやすいといわれているんです。生活のリズムを整えることが、勉強に集中する第一歩なんですね。
気力を支える体力を取り戻す
学校に行かないと歩く機会が減って、体力が少しずつ落ちてしまいます。体力が落ちると、気力もわきにくくなって「何をするにもだるい…」という状態になりがちです。
ですが、軽い運動や散歩、ストレッチなどを続けるだけで、体力も少しずつ戻ってきます。すると不思議と気力もついてきて、「やってみよう!」という気持ちになれるんです。
小さな短期目標を立てる
勉強を始めるには、はっきりした目標があることが大切です。もちろん「高校進学」といった大きな目標も大事ですが、それだけだと遠すぎてイメージしづらいですよね。そこでおすすめなのが、「近い未来の小さな目標」をつくること。たとえば…
「1週間で英語の単語を10個覚える」
「教科書の3ページを理解する」
といった、小さなゴールでOKです。実現できる目標なら、達成感も得られて「次もやろう!」と前に進めます。
不登校から勉強に追いつくための4つのポイント
準備が整ったら、いよいよ勉強をスタート!ここで大事なのは「少しずつでも毎日続けること」です。そのために意識してほしいポイントを4つご紹介します。
①1日10分から始めて習慣づける
「勉強って何時間も机に向かわなきゃいけない」と思っていませんか?でも、最初から長時間やろうとすると続かないんです。
まずは1日10分、机に座って教科書を開くだけで十分。慣れてきたら20分、30分と少しずつ伸ばしていきましょう。無理せず続ければ、自然と勉強する習慣がついてきます。
②得意な科目から始めて自信をつける
最初から苦手科目に挑戦すると、つまずいてやる気がなくなってしまうことも。まずは「やりやすい科目」や「得意な単元」から始めてみましょう。「できた!」という成功体験を積み重ねることで、自信がつき、少しずつ苦手な分野にもチャレンジできるようになります。
③基礎をしっかり固める
「学校に追いつかなきゃ!」と思うと、つい応用問題にも手を出したくなるかも知れません。でも実は、追いつくために一番大事なのは基礎なんです。特に数学や英語は基礎ができていないと、先に進んでも理解できなくなってしまいます。逆に、基礎をきちんと固めておけば、その後の内容はスムーズに頭に入ってきます。
応用問題は、基礎ができてからが無理なく確実です。
④わからないことは早めに解決する
勉強をしていると「ここがよくわからない…」というところが必ず出てきます。特に数学や理科は、ただ答えを見ただけでは理解できないことも多いですよね。
わからないことをそのままにすると、後でますますつまずく原因になります。だからこそ、疑問はできるだけ早めに解決しましょう。
家庭教師や個別指導塾の先生など、外部のサポートを利用するのもおすすめです。一人で抱え込まず、誰かに聞ける環境をつくると安心です。
不登校生の勉強をサポートする外部機関
「ひとりで勉強を進めるのは大変だな…」と感じるときは、外部のサポートを取り入れるのもおすすめです。お子さんの性格やペースに合わせられる、いろいろな学びの場があります。
学校への復帰を目指しやすい教育支援センター
教育支援センターは、自治体が設置している不登校の小中学生を支援する施設です。心理士さんや特別支援の専門家がいて、学習面や心のケアを受けられます。学校と連携してプリントに取り組んだり、オンラインで授業に参加したりすることも可能です。取り組み内容によっては、学校で「出席扱い」になることもあります。
基本的には学校復帰をサポートする施設なので、「また学校に行きたいな」という気持ちがあるお子さんにぴったり。授業に触れる感覚を少しずつ取り戻していけます。
学習支援に強いフリースクール
フリースクールにはいろいろなタイプがありますが、学習支援に力を入れているところを選ぶと、学校と同じようなカリキュラムで質の高い授業を受けられます。集団が苦手なお子さんなら、オンライン型のスクールが安心です。
また、フリースクールを選ぶ際は「出席扱い制度」に対応しているかもチェックしましょう。この制度があれば、在籍校の出席日数にカウントされるので通いやすいです。
学力を底上げする家庭教師
「自宅で安心して勉強したい」というお子さんには家庭教師が向いていると思います。マンツーマンだからこそ、お子さんに合わせた学習計画が可能です。学校の進度に追いつくサポートはもちろん、抜けてしまった基礎の復習にも対応できます。
特に長期欠席で「わからないところ」が増えてしまった場合、家庭教師は強い味方。基礎から丁寧に取り組むことで、学力をグンと底上げできます。対面が不安なお子さんには、オンライン家庭教師もあります。
「勉強を習いに行く」感覚を取り戻せる学習塾
他の生徒がいる環境が苦にならないお子さんなら、塾に通うのもよい方法です。決まった時間に通うことで「勉強を習いに行く」リズムができ、生活リズムの改善にもつながります。
高校進学や学校復帰を見据えている場合、塾に通うことが一種の練習になることも。勉強の遅れを取り戻したいなら、個別指導タイプがおすすめです。
不登校で勉強が手遅れにならないよう親にできる支援
ここからは、不登校のお子さんに保護者の方ができる勉強面でのサポートをご紹介します。
登校や勉強を強制せず、頑張りを認める
「勉強を頑張るなら学校に行かないと意味がないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。でも、不登校のお子さんにとって、登校はとても大きなハードルです。勉強への一歩も同じで、無理に背中を押されると余計に遠ざかってしまうことも多いです。
だからこそ、「やってみよう」と思えたその気持ちを認めてあげてください。お母さんやお父さんが見守ってくれているとわかるだけで、お子さんは安心して一歩を踏み出せます。
生活リズムが整うように協力する
勉強を続けるためには、規則正しい生活が大切です。夜更かしや不規則な食事が習慣になると、集中力もやる気も出づらくなってしまいます。たとえば、
・早寝早起きを一緒に意識する
・食事の時間を整える
・スマホやゲームにルールを決める
・外で体を動かす時間をとる
などが効果的です。特に寝る前のスマホは睡眠の質を下げると言われているので注意が必要です。
必要な支援を選ぶために情報を集める
「今どうしたいのか」「将来どんな進路を選びたいのか」を理解しても、親が情報を持っていないと適切なサポートができません。インターネットでの情報収集はもちろん、教育支援センターなどの無料相談機関を利用するのもおすすめです。
勉強では外部機関の協力を得る
不登校期間が長いと、勉強の「わからない」が積み重なってしまいます。保護者の方がすべてを教えるのは難しいので、家庭教師や塾といった専門家に頼るのが安心です。
お子さんに合った方法で基礎から取り戻せれば、受験対策にもつながります。
まとめ | 不登校が長いお子さんほど早めの対応を!
不登校が続くと「もう取り戻せないのでは…」と不安になるかもしれません。でも、正しいサポートを取り入れれば大丈夫。教育支援センターや家庭教師、塾など、頼れる場所はたくさんあります。
今は多様な進路がある時代です。学校に行けていなくても、自分に合った道を見つけて進学することはできます。小さな一歩を踏み出せれば、必ず未来につながります。
家庭教師のガンバでは年間100人以上の不登校のお子さんの家庭教師をお任せいただいています。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。