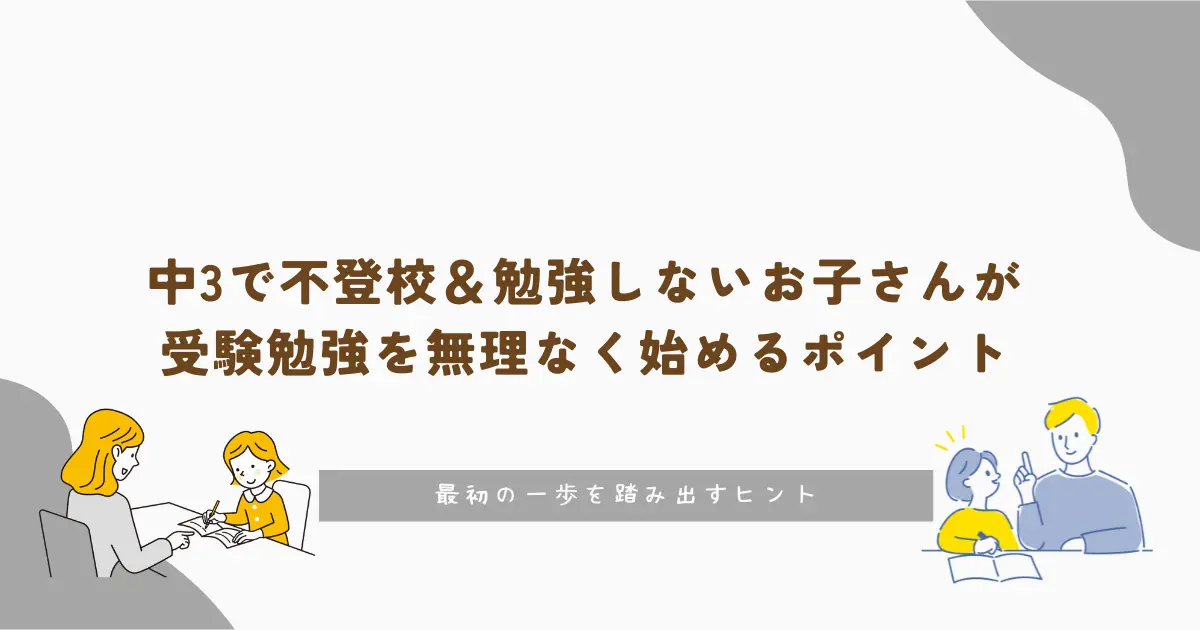不登校のお子さんは、どうしても学習のリズムが途切れやすいと思います。予定通りに進められなかったり、わからないことが積み重なって手が止まってしまったり…。その結果、「勉強しない」という状態になってしまうことも少なくありません。
そんな姿を見ていると、お子さん自身はもちろん、保護者の方も不安になってしまうのではないでしょうか。特に中3になると、
「今の学力で高校受験に間に合うの?」
「不登校でも高校に進学できるの?」
といった進路の悩みが増えてくると思います。でも、大丈夫です。実際に、中3から不登校だったけれど、小さな一歩から始めて自分に合った進路を見つけた生徒さんもたくさんいます。行動していくことで、不安は少しずつ軽くなっていくんです。
とはいえ、「じゃあ勉強は何から始めればいいの?」と迷ってしまう方も多いと思います。そこでこの記事では、
・不登校でも受験しやすい高校のタイプ
・無理なく始められる受験勉強の最初のステップ
をやさしく解説していきます。読み終わる頃に、「ちょっとやってみようかな」と思っていただけると嬉しいです。そして保護者の方に向けて、
・お子さんがつまずきやすいポイント
・無理のない支え方について
もご紹介します。ぜひご参考になさってください。
不登校で勉強しない中3生によくある悩み
まずは、不登校のお子さんによく見られる悩みについて整理してみます。原因や気持ちを理解し、共感してあげることが、サポートの第一歩になります。
不登校を続けていて高校進学できるか不安
中学校は、不登校でも卒業できます。ただ、その先の進路は自分で選ばなければなりません。多くのお子さんは、進学先の選択で立ち止まってしまいます。「学校に通えない自分を受け入れてくれる高校はあるのかな?」と不安に感じてしまうからです。
また、中3になると周りから「進路はどうするの?」と聞かれることも増えますよね。不登校によって選択肢が狭まることに本人も気づいていますから、「何とかしなくちゃ」と焦る一方で、その声をプレッシャーに感じてしまうのではないでしょうか。
学力がどんどん下がることへの焦り
不登校の状態だと、わからない問題をすぐに質問できず、解決が後回しになりがちです。「あとで調べよう」と思っても、気づけばどんどんたまってしまい、「もう勉強が全然わからない」という状態に…。
実は、お子さん自身が一番そのことに気づいています。中1・中2の頃は「そのうち頑張ればいいや」と思えても、中3になると「受験まで時間がない」と焦りが募りやすいのです。
周囲との比較による自信の喪失
不登校のお子さんは、「自分だけ学校に行けていない」と負い目を感じやすいです。さらに、受験モードに入った友達と比べることで、「自分は遅れている」と自信をなくしてしまうこともあります。
自信を失うと、行動すること自体がつらくなってしまいます。その結果、無気力に陥り、不登校から抜け出すきっかけさえ見つけにくくなることがあります。
不登校で勉強していないとどうなる?
では、実際に不登校で勉強をしないままでいると、どんな影響が出てくるのでしょうか。
【学力面】基礎力が低下し、高校受験への自信を失う
一番大きな影響はやはり学力です。学校に通わずにすべての教科を自力で学ぶのはとても難しく、どうしても「理解が不十分な部分」「まったくわからない部分」が出てきてしまいます。
そのままにすると基礎が身につかず、成績が下がって「自分は勉強が苦手だ」と思い込んでしまうことも…。特に中3の内容は一気に難しくなるので、誰かに丁寧に説明してもらうサポートが必要です。教育支援センターや家庭教師、個別指導塾などの力を借りるのも一つの方法です。
【内申面】評価がつかず、受験に不利になることも
不登校の場合、通知表に「斜線(評価不能)」や「1」が並んでしまうケースもあります。これは、出席や提出物が不足していると評価がつけられないためです。
通知表の成績は「調査書(内申書)」として高校に送られるので、どうしても受験に影響します。学力があっても、内申点が原因で合格できないこともあるのです。
【心理面】学校からさらに遠ざかる悪循環
不登校が長くなるほど、学校に戻るハードルも上がります。学力に不安があると「授業を受けてもついていけないのでは」と思い込み、余計にやる気を失ってしまうことも。
さらに「今さら自分の居場所なんてあるのかな」と考えてしまい、気持ちが後ろ向きになる悪循環に陥りやすいのです。
学校に戻る気持ちが少しでもあるなら、「まずは短時間だけ別室登校してみる」など、小さな行動から始めることが大切だと思います。
中3で不登校でも高校に進学できる?
「不登校だと内申点が心配…」と感じる方は多いと思います。たしかに入試では不利な点もありますが、だからといって高校進学ができないわけではありません。実は、高校には思っている以上にいろいろな選択肢があるんです。
【公立高校】内申点や出席日数が影響する場合あり
公立高校の入試では、基本的に「当日の学力試験」と「内申点」を合わせて評価されます。不登校の場合、内申点が低くなりがちなので不安に思うかもしれません。
でも、すべての学校が内申点を重視しているわけではありません。例えば、当日点と内申点の割合が「8:2」や「9:1」のように、当日の試験点を重視する高校もあるんです。この場合、不登校による影響は最小限に抑えられます。
ただし、高校によっては欠席日数を選考の材料にすることもあるため、注意が必要です。自治体や学校によって対応が異なるので、事前にきちんと確認しておきましょう。
【私立高校】当日試験重視や調査書不要の学校もある
私立高校は、学校ごとに入試の基準がかなり違います。調査書を「参考程度」にしか見ない学校や、まったく必要としない学校もあります。
調査書が不要な入試は「オープン入試」と呼ばれ、特に首都圏では一般的です。東京都の私立高校などでは、オープン入試で合否が決まるケースが多く、不登校でも十分にチャンスがあります。
【通信制・定時制】不登校でも受けやすいルート
「全日制」にこだわらなければ、通信制高校や定時制高校という道もあります。これらの高校では、調査書をあまり重視せず、入学試験を課さない学校も多いんです。
通信制高校は、自宅学習やレポート提出が中心で、自分のペースで学べるのが大きな魅力。定時制高校は、昼や夕方から授業があるスタイルで、働きながら通うこともできます。毎日朝から通う必要がないので、不登校経験があっても無理なく続けやすいと思います。
中3で不登校でも受験勉強を無理なく始める4つのポイント
<中3で不登校でも受験勉強を始めるポイント>
1、1日10だけ机に向かう
2、得意科目からスタート
3、通信教育や家庭教師を活用
4、生活リズムを整える
これらは不登校でも無理なく受験勉強を始めるポイントです。ポイントを抑え継続的に勉強することで、徐々に力がついてきます。高校受験にも対応できるようになります。
いきなり長時間ではなく「1日10分から」
「勉強=何時間も机に向かうもの」というイメージを持っていませんか?でも、最初から長時間やる必要はありません。むしろ「やっぱり無理だ…」と挫折してしまう原因になります。
まずは10分だけでもOKです。大切なのは「続けること」。少しずつ習慣にしていけば、自然と集中できる時間も伸びていきます。
苦手科目より「得意・やりやすい科目」から
勉強を始めても、続かなければ意味がありません。そこでおすすめなのは、得意な科目や「やりやすい」と感じる教科から始めること。
小さな「できた!」を積み重ねることで、少しずつ自信がついてきます。その成功体験がモチベーションにつながり、他の教科にもチャレンジしやすくなるんです。
通信教育や家庭教師を利用する
ひとりで勉強を進めるのが不安なときは、外部のサポートを取り入れてみましょう。最近の通信教育はタブレットやパソコンを使うものが多く、AIが自動で学習範囲を提案してくれるなど、とても進化しています。自分のペースで取り組めるので、不登校のお子さんにも合いやすい学習スタイルです。
また、家庭教師は「先生が来てくれる時間は頑張る!」という気持ちでメリハリをつけられるのがポイント。わからないところをその場で聞けるのはもちろん、必要に応じて中1・中2の内容までさかのぼって復習してもらえるのも心強いです。
生活リズムを整えるだけでも勉強しやすくなる
「どうしても勉強に気持ちが向かない…」というときは、まず生活リズムを整えることから始めてみましょう。
生活が不規則になると自律神経が乱れやすく、集中力の低下や体調不良につながります。これでは勉強どころではありませんよね。
朝はできるだけ同じ時間に起き、簡単でいいのでスケジュールを作ってみましょう。毎日のリズムが整うだけで、勉強に向かいやすくなります。
不登校のお子さんの高校受験に向けて、親にできるサポート
中3で不登校のお子さんを見て、「何とかしなきゃ…」と焦ってしまう保護者の方も多いと思います。ですが、無理に学校へ行かせたり、「勉強しなさい!」と強く言い過ぎてしまうのは逆効果になることも。大切なのは、お子さんが少しでも前に進めるよう、そっと背中を押してあげるサポートです。
無理に「勉強しなさい」と言わない
実は「勉強なんてどうでもいい」と思っている不登校のお子さんは少ないんです。心の中では「このままじゃまずいな」「どうにかしなきゃ」と焦っていることがほとんどだと思います。特に中3は受験が近い分、その気持ちが強くなります。
必要なのは“最初の一歩”を踏み出すきっかけです。ほんの小さなことからでも始められれば、再び勉強に取り組めるケースが多いんです。
だからこそ保護者の方が「勉強しなさい!」と繰り返してしまうと、かえって心を閉ざしてしまうことも…。そんなときは「少しやってみようか」と励ましたり、頑張れた瞬間をしっかり認めてあげたりすることが一番の力になります。
お子さんの気持ちを聞く時間を持つ
不登校のお子さんはたくさんの「もやもや」を抱えています。そんな気持ちを吐き出せるだけで、心がふっと軽くなることもあるんです。
そのためには、できるだけ親の意見を挟まずに“聞き役”に回ってあげることが大切です。安心して気持ちを話せるようになれば、「これからどうしたいか」「進路はどうするか」など、大事なことも自然と相談してくれるようになります。一緒に考えていける関係づくりを意識してみてください。
塾や家庭教師など、第三者の力を借りる
「勉強のサポートをしなきゃ」と思っても、保護者の方がお子さんに教えるのは何かと難しい面もあると思います。そんな時は塾や家庭教師など、経験豊富な第三者の力を借りるのも安心な方法です。
プロの先生なら「どこから復習するのが最適か」を見極めながら、抜けている部分を一つずつ埋めていくことができます。しかも塾や家庭教師センターには、さまざまなタイプのお子さんを支えてきた実績があるので、進路を考えるときにも色々と相談できるのではないでしょうか。
進路選びは“お子さんの目線”で一緒に考える
「不登校でも行ける高校ってあるのかな…?」と不安に思うのは、お子さんも同じです。だからこそ進路を一緒に考える時間を持つことが大切です。
「あなたのことを真剣に考えているよ」という姿勢や、「どんな道でもサポートするよ」という気持ちが伝わると、お子さんはとても安心します。その安心感が、勉強への前向きさにつながることもあります。
進路を決めるときは、親が先に答えを出すのではなく、「どんな環境なら無理なく通えて、学べるのか」というお子さんの目線を大切にしてください。
まとめ:不登校で勉強しない中3でも、少しずつ前に進める
不登校で勉強に手がつかない中3のお子さんは、焦らず少しずつ取り組むことが大切です。ポイントは次の通りです。
1、無理に詰め込まない
まずは短時間でも学習の習慣を作ることから始めましょう。
2、自分に合った学び方を見つける
家庭学習、通信教材、オンライン学習など、自分が続けやすい方法を選ぶことが重要です。
3、目標を小さく設定する
「今日の英単語10個」など、達成可能な目標を積み重ねることで自信がつきます。
4、周りのサポートを活用する
家族や先生、家庭教師など、信頼できる人に相談しながら進めると安心です。
少しずつでも学習の習慣をつけることで、高校受験に向けての準備は必ず整います。焦らず、自分のペースで一歩ずつ進めていきましょう。
家庭教師のガンバでは年間100人以上の不登校のお子さんの家庭教師をお任せいただいています。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。