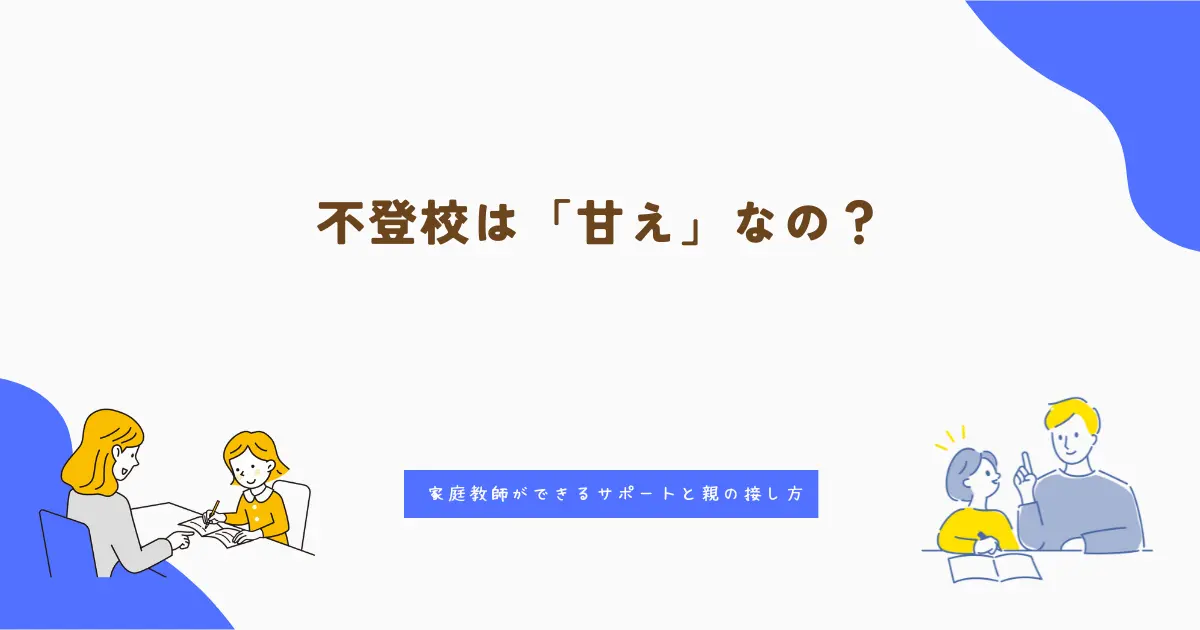「不登校って、甘えなのかな…」そんなふうに思い悩んでいる方も多いのではないでしょうか。お子さん自身は決して“甘えている”つもりなんてないのに、周りからそう言われてしまう—それはとてもつらいことです。
でも実際のところ、「甘え」が不登校の原因になることはほとんどありません。多くの場合、その背景には学校や家庭で感じた心理的・身体的なストレスがあります。
お子さんが立ち止まっている理由を理解し、そっと寄り添うことができれば、少しずつ前を向けるようになります。そしてその一歩を、私たち家庭教師も全力でサポートしていきます。
この記事では、不登校に悩む中学生と保護者の方に向けて、
・不登校の背景と理由
・「甘え」と誤解されやすい行動
・家庭教師ができるサポート
・親の接し方のポイント
をわかりやすくお伝えしていきます。今の状況を受け止めながら、お子さんらしい道を見つけるきっかけになれば嬉しいです。
不登校は甘えなの?悩めるお子さんの本当のところ
不登校が「甘え」と言われてしまうのは、周囲から見ると「学校に行かない理由がはっきりしない」ように見えることが多いからではないでしょうか。
ですが、実際にはその裏に“見えない理由”が隠れていることがほとんどです。文部科学省の調査によると、不登校の主な要因で最も多いのは「無気力・不安」で、全体の半数以上を占めています。
こうした「無気力な状態」は、外から見ると「やる気がない」「怠けている」と誤解されがちですが、そこには必ず“きっかけ”があります。
別の調査では、不登校になった最初のきっかけとして、「先生との関係」「友達との関係」「身体の不調」「勉強がわからない」などが挙げられています。
つまり、学校での人間関係や学習への不安、体調不良など、いくつもの小さなストレスが積み重なって、登校が難しくなってしまうのです。
こうして背景を見てみると、「不登校=甘え」と決めつけることが、どれだけお子さんを追い詰めてしまうかがわかります。
大切なのは「なぜ行けなくなったのか」を一緒に考えること。その理解こそが、次の一歩につながっていくのではないでしょうか。
(参照:令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について,p.83 | 文部科学省)
(参照:令和2年度不登校児童生徒の実態調査 結果の概要 | 文部科学省)
「甘え」と思う前に知ってほしい、不登校の背景と理由
不登校には、必ず何かしらの理由があります。一見「無気力に見える」お子さんでも、実はそうなってしまうきっかけがあったはず。ここでは、不登校につながりやすい要因をいくつか見ていきます。
学校での人間関係やいじめなどのストレス
中学校では友人関係が広がり、部活動では上下関係やライバル関係も生まれます。小学校の頃よりも、ずっと複雑な人間関係の中で過ごすことになります。
思春期という心が大きく揺れ動く時期に、そうした人間関係のプレッシャーを受けるのは大きなストレスです。ときには、友人とうまくいかず、いじめにつながってしまうこともあります。
大人から見ると「そんなことくらいで」と思えることも、本人にとっては深刻な悩みです。“些細なこと”の積み重ねが、学校に行けなくなるほどのストレスになることもあるのです。
勉強のつまずきや学習の遅れ
「勉強がわからない」「テストで点が取れない」—そんな経験を重ねるうちに、自信をなくしてしまうこともあります。最初は少しのつまずきでも、放っておくと「もう何もわからない」と感じることも。
テストの結果が悪かったり、友達との学力差を感じたりすると、「自分なんてダメだ」と思い込んでしまうこともあるかも知れません。
それが重なると、学校そのものがつらい場所に感じられ、登校への意欲を失ってしまうこともあります。
学校の環境や家庭の変化によるストレス
転校やクラス替え、担任の変更など、環境が変わることで心が疲れてしまうこともあります。新しい人間関係を築いたり、教室の雰囲気に慣れたりするのは、思っている以上にエネルギーが必要です。
そのストレスが重なると、学校に行くのが怖くなってしまうこともあります。また、家庭環境の変化もお子さんに影響を与えます。夫婦仲の不和や別居、家族の病気・死別、経済的な不安などは、心の負担になりやすいと思います。
学校が「安心できる場所」であれば救いになりますが、そうでない場合、家に閉じこもってしまうこともあります。
自律神経の乱れによる起立性調節障害
夜ふかしや生活リズムの乱れが続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなります。すると朝なかなか起きられなかったり、めまいやだるさが出たりする「起立性調節障害」という症状が現れることもあります。この症状があると、「学校に行きたくても体が動かない」状態になります。
気持ちの問題ではなく、身体の不調によるものですから、医療機関での診断や治療が必要です。「怠けている」と誤解されやすいですが、実際は身体が悲鳴を上げているサインなのです。
「不登校=甘え」と誤解されやすい行動の例
不登校のお子さんの行動を見て、「甘えているのでは?」と感じる方もいるかもしれません。ただ、表面上の行動だけで判断してしまうと、かえってお子さんを追い詰めてしまうこともあります。
ここでは、誤解されやすい行動の裏にある“本当の理由”を見てみます。
生活が不規則で朝起きられない
夜ふかしをして朝起きられないと、「だらしない」「甘えている」と思われがちです。でも、長期間続いている場合は注意が必要です。
先ほど触れたように、起立性調節障害や抑うつ状態が関係しているケースも少なくありません。「気持ちの問題」と片づけず、医師に相談したり、生活リズムを整えるサポートをしていくことが大切です。焦らず、少しずつ整えていきましょう。
勉強をせず、課題にも手をつけない
「何も勉強していない」「宿題もやらない」—そんな姿を見ると、つい「怠けているのでは」と感じてしまうこともあると思います。でも実際は、勉強に向かう気力がわかないほど疲れている場合も多いのです。
自己肯定感が下がり、「どうせやっても無理」と思っているお子さんにとって、勉強はつらいもの。だからこそ、「なぜやらないの?」と叱るより、「最近、どんな気持ちなの?」と声をかけてあげることが大切です。まずは心を立て直すところから、一歩ずつ始めましょう。
遊んでばかりいるように見える
家でゲームをしたり、動画を見て過ごしている姿に「危機感がない」と感じることもあるかもしれません。でも実は、それも心を守るための行動なのかもしれません。
つらい現実を直視するのがしんどいとき、人は自然と“逃げ場”を作ります。ゲームやスマホはその「避難場所」になっている場合もあります。遊ぶことで気持ちを落ち着かせたり、ストレスを発散させている可能性もあります。
頭ごなしに「遊んでばかりじゃダメ」と否定するよりも、「どんなときにゲームしたくなるの?」と穏やかに話を聞くことで、心の奥にある気持ちが見えてきます。
何をするにも無気力に見える
何をしても反応が薄かったり、声をかけても返事がない—そんなとき、「やる気がない」「甘えている」と感じてしまうのは自然なことだと思います。ただ実際には、心がエネルギー切れを起こしているだけかもしれません。
気持ちに寄り添いながら、焦らず見守ること。それが回復の第一歩になります。少しでも表情が和らいだり、自分から話しかけてくれる日が来たら、その小さな変化を一緒に喜ぶことが大切ではないでしょうか。
不登校のお子さんを支える家庭教師の活用法
「不登校のままで大丈夫かな?」「勉強が遅れてしまって心配」…
そんなとき、家庭教師が大きな力になれることがあります。ここでは、不登校のお子さんに家庭教師ができるサポートと、そのメリットをわかりやすくご紹介します。
少しずつ“勉強するリズム”を取り戻せる
不登校の期間が続くと、どうしても勉強の習慣がなくなってしまいますよね。でも、ペースを崩してしまっても大丈夫。家庭教師なら、お子さんの今の状態をしっかり見ながら、無理のないペースで学習を始めていけます。
たとえば「今日は10分だけ机に向かう」といった小さな一歩からでもOK。少しずつ自信を取り戻せるよう、先生がとなりで見守りながら寄り添い進めていきます。「わかる楽しさ」を少しずつ積み重ねることで、自然に学習習慣がついてくると思います。
安心して話せる“第三者”の存在になる
不登校になった理由や気持ちは、なかなか家族にも話しづらいものです。そんなときに支えになれるのが、家庭教師という第三者の存在。
年齢が近く、話しやすい家庭教師なら、勉強の合間にいろんな話をすることもできます。実はこの「話せる時間」がとても大切で、気持ちが少しずつ前向きになっていくきっかけにもなるんです。
心が落ち着けば、勉強への意欲も戻ってきます。家庭教師は“教える人”であると同時に、“寄り添う人”でもあると思います。
進路や受験の相談にも具体的に応えられる
学校に行けない間、「このままで高校受験は大丈夫かな…?」と不安に思う方も多いです。家庭教師なら、全日制だけでなく、定時制・通信制高校など幅広い進路の選択肢をふまえてアドバイスできます。
これまでたくさんの不登校のお子さんをサポートしてきた経験があるので、「今の状況からどんな学校を目指せるのか」「合格に向けて何をすればいいのか」など、具体的な道筋を一緒に考えられます。
勉強の積み重ねが“学校復帰”への橋渡しに
「また学校に行けるようになりたい」と思っているお子さんにとっても、家庭教師のサポートは大きな助けになります。
授業の遅れを感じるまま学校に戻るのは勇気がいりますが、家庭教師と一緒に「わからないところ」から一歩ずつ進めれば大丈夫。
少しずつ勉強の内容がわかるようになり、「できた!」という気持ちが増えることで、学校に対する不安が小さくなっていきます。
勉強を通して自信を取り戻し、再び前を向けるようになる—家庭教師はその橋渡しの役割を担います。
不登校のお子さんに親ができる関わり方
不登校の期間は、保護者の方にとってもお子さんにとっても不安が多いと思います。一番近くで支える存在だからこそ、無理をせず、気持ちに寄り添うことが大切ではないでしょうか。
ここでは、家庭で意識してほしいポイントをご紹介します。
無理に登校や勉強を促さず、“今”を受け止める
不登校には必ず“心のストレス”があります。焦って無理に登校や勉強を促すと、かえってお子さんの気持ちを追い詰めてしまうことも。
まずは現状をそのまま受け止め、「話したいときに話せる環境」をつくってあげましょう。「いつでも聞くよ」と伝えておくだけでも、安心感になります。
小さな会話を重ねていくうちに、お子さんの心は少しずつ開いていきます。
“甘え”と決めつけず、気持ちを理解しようとする
不登校の原因は人それぞれ。「甘えているだけ」と周囲に言われても、保護者の方までそう感じてしまうのは禁物です。親はお子さんにとって、最後の安心できる場所。どんなに心配でも、“理解しようとする姿勢”を見せることが大切だと思います。
「そばにいるよ」「大丈夫だよ」という一言が、想像以上に大きな支えになります。
家庭教師や専門機関に頼るのも大切な選択
不登校のサポートを、家族だけで抱え込むのはとても大変です。お子さんの心のケアには専門的な知識が必要な場合もありますし、勉強の面でもサポートが追いつかないこともあります。
そんなときは、家庭教師や教育支援センターなどの専門機関に相談してみましょう。支援センターには心理士や専門スタッフがいて、学校復帰に向けたアドバイスを受けられます。
勉強面は家庭教師に任せれば、わからないところまで戻って丁寧に教えてもらえるので安心です。ひとりで悩まず、周りと協力しながら進めていくことが大切だと思います。
不登校と家庭教師に関するよくある質問
最後に、不登校のお子さんの対応について、よく寄せられるご質問にお答えします。
Q.不登校は本当に「甘え」ではないの?
A.「甘え」ではありません。不登校の背景には、学校や家庭でのストレス、心の疲れなど、さまざまな要因が重なっています。「甘え」と決めつけてしまうと、お子さんが抱えている本当の苦しさに気づけなくなってしまうかもしれません。
Q.家庭教師をつけると不登校は改善しますか?
A.家庭教師が直接「不登校を治す」わけではありませんが、前に進むきっかけになることは多いです。勉強を通して少しずつ生活リズムが整ったり、「わかる」「できる」という自信を取り戻したりすることで、学校へ戻る気持ちが芽生えることも少なくありません。
Q.不登校のお子さんにとって、塾や通信教育との違いは?
A.家庭教師は、完全マンツーマンでお子さんの気持ちや体調に合わせた指導ができる点が大きな特徴です。外に出ることが難しくても、家で安心して勉強を始められますし、先生がペースを一緒に作ってくれるので「やる気の波」に左右されにくいんです。通信教育のように「自分で進める」スタイルが合わないお子さんでも、無理なく継続できます。
まとめ|不登校は「甘え」ではなく、サポートで前に進める
不登校は「甘え」ではありません。学校や家庭でのさまざまなストレスが積み重なり、心が限界を迎えた結果として「行けない」状態になっているのです。
大切なのは、「どうして行けないのか」を理解し、そこからどう支えていけるかを一緒に考えることではないでしょうか。
その中で、家庭教師は大きな味方になれます。お子さんの気持ちに寄り添いながら、安心できる時間をつくり、学び直しや進路のサポートをしていきます。少しずつでも「自分のペースで前に進める」と感じられたら、それが何よりの成長だと思います。
もちろん、教育支援センターやフリースクールなど、頼れる外部機関もたくさんあります。お父さん・お母さんが一人で抱え込む必要はありません。いろいろな支援を上手に活用することも大切なことではないでしょうか。
家庭教師のガンバでは年間100人以上の不登校のお子さんの家庭教師をお任せいただいています。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。