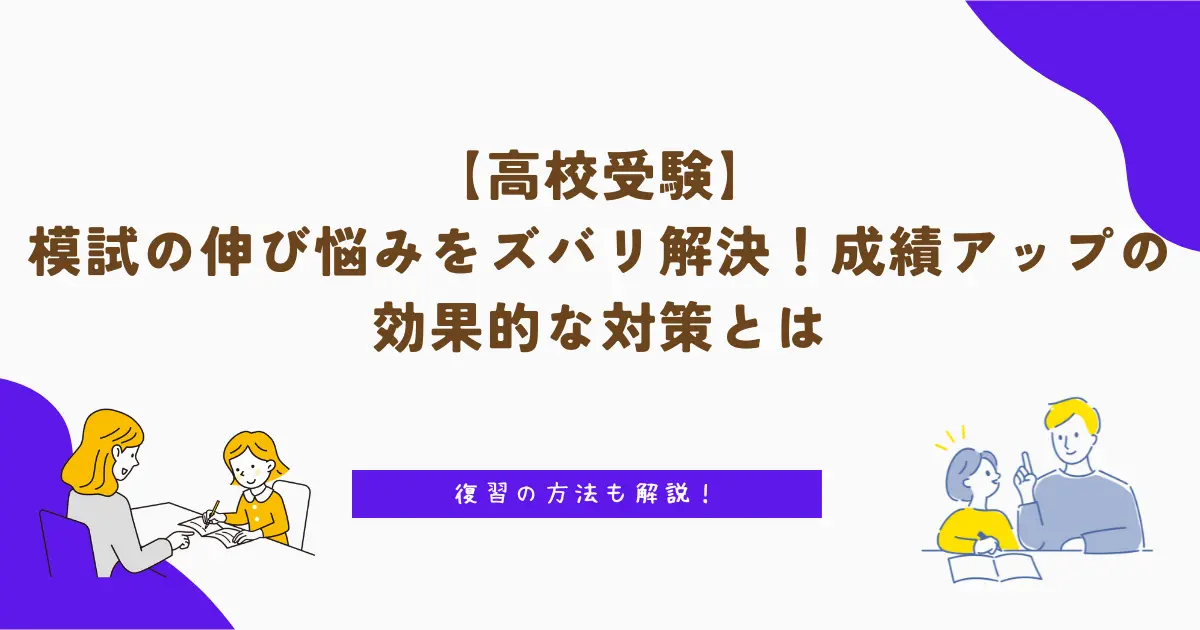「受験勉強を始めたのに、模試の成績がなかなか伸びない…」
皆さんはそんな悩みを抱えていませんか?実は模試の成績が伸びないお子さんには、多くの場合、共通した特徴があります。それは、学校の定期テストと同じ勉強法で模試にも取り組んでいるということです。模試ならではの特徴を知り、対策を練ることもとても大切なのです。
この記事では模試の成績に悩む高校受験生に向け、伸び悩みの原因と有効な対策を解説します。受験勉強の正しい取り組み方や、力を入れるべきポイントの参考にしてください。また保護者様には、お子さんの努力を支えるために取るべき行動をお伝えします。模試でお子さんが成績不振に陥った際の参考にしていただければと思います。
定期テストと何が違う?模試の特徴を知ろう
学校の定期テストでは良い点数を取れても、模試で伸び悩むお子さんは少なくありません。思うような成績が取れないのは、両者の性質が大きく異なるからです。模試の特徴に意識を向けることで、「なぜ伸び悩むのか」現状の問題点が見えてきます。
模試はこれまでに習った全範囲から出題される
模試は受験日以前に学習した全範囲から出題されます。過去に理解不十分でやり過ごした部分、演習が不足している部分を伸ばさない限り、高得点には結びつきません。
それに対し、定期テストのメインは直近に学習した範囲です。ピンポイントで勉強しておけば、得点を取りやすい傾向があります。
勉強に時間がかかるのは、当然模試です。学校の勉強とは別に、いかに受験勉強の時間を取るかが大切になってきます。
受験者数が定期テストとは大違い
模試の多くは都道府県単位で実施されます。同じ県内に住むあらゆる高校受験生が取り組みます。多くても200〜250人ほどの定期テストとは、受験者数が全く異なるのです。
ですので、学校で良い順位を取れても、都道府県レベルでトップ層に入れるとは限らないのです。ただ、もし順位が思ったより悪くても、気を落とさず現在の自分の位置を冷静に理解することが大切です。
入試に準じた出題形式で応用問題が多い
受験生の中には「中3になってから模試が難しくなった」と感じているお子さんもいるかもしれません。実際中3の夏以降の模試は、問題形式・難易度ともに入試に即したものになってきます。定期テストの感覚で臨んではギャップを感じるかも知れません。
夏は受験勉強を始めて日が浅いお子さんも多く、模試をすらすら解ける人の方が稀です。焦らず勉強を重ねていく中で、徐々に応用問題にも適応していきましょう。
模試は分析のツールとして見ることが大切
<模試から分析するべきこと>
・各科目の苦手分野と強化ポイント
・現状取れる点数と偏差値
・志望校合格までに必要な点数
・同じ高校を志望する生徒内での順位
模試の成績には現在の状態が現れます。だからこそ、現状を分析し勉強法を見定めるツールとして利用価値があります。「良い」「悪い」と一喜一憂するのではなく、模試を受けるメリットをしっかり意識しましょう。
項目の中で最も大切なのが、各科目の苦手分野と強化ポイントの把握です。分析で得られた内容こそが、受験勉強で取り組むべきポイントです。特に基礎からすっぽり抜けている部分は、重点的に学習しなければなりません。
模試を受けるたびに分析をくり返し、少しずつ苦手を減らしましょう。入試本番までに全ての苦手をなくすのが目標です。
勉強をしても成績が下がる?模試で伸び悩む原因
勉強をしているにも関わらず模試の成績が下がると、自己不信に陥るお子さんもいるかもしれません。ただ、伸び悩みの原因は「努力不足」でも「実力不足」でもないことが多くあります。自分を責めるのではなく、成績を低下させる要因がないか確認しましょう。
受験勉強を始めて日が浅い
勉強した内容は一朝一夕では身につきません。一般的に学習した内容は復習しなければ、24時間以内にほとんど忘れてしまうと言われています。なので復習をくり返しながら、徐々に定着を図る必要があります。受験勉強を始めて日が浅いうちは、結果が伴わなくても仕方がありません。
成績アップまでにかかる時間は、復習する量などにより異なります。復習範囲が広い人は、定着にも時間がかかります。たとえば数学で一次方程式が定着しただけでは、模試で通用する力にはなりません。連立方程式、二次方程式と段階を辿る必要があります。結果を急がず、確実に努力を続けましょう。
中1・中2範囲の内容が定着していない
「今学校で習っている範囲」「予習範囲」だけを勉強しても、模試の成績は上がりません。模試は復習範囲がメインです。中1・中2部分が定着していないと、苦戦を強いられてしまいます。
「学校の勉強で手いっぱい」というお子さんは、夏休みを有効に使うことをおすすめします。復習するべき範囲を書き出し、スケジュールを立てた上で実行すると効率的です。2学期以降は生活を見直し、復習範囲の勉強にあてる時間を確保しましょう。
基礎が抜けたまま勉強を進めている
受験に向けて気合いを入れるあまり、早い時期から過去問や高レベルの問題集に取り組むお子さんもいます。ただ、基礎が十分に定着していない状態で取り組んでも、理解するのは難しくなります。
基礎が定着しているかどうかの一つの目安は、例えば、数学や理科なら「なぜその解き方になるのか」を他人に説明できるかどうか、だと思います。こういった原理から理解していれば、応用もききます。
初めは基礎徹底で構いません。演習を重ねた後、できる感覚を確かめながら応用問題を解くのが効果的です。
相対的に見て勉強時間が足りていない
成績が下がるお子さんは、受験勉強の時間が足りない可能性もあります。特にこれまでほとんど勉強をしてこなかったお子さんは、短時間の勉強でも達成感を感じがちです。「勉強しているつもり」でも、勉強不足になっているのかもしれません。一度自分の勉強時間を再確認してください。
勉強法が自分に合わない
勉強法が自分に合わないお子さんも成績が伸び悩みます。よくあるのが「塾に通っているのに成績が伸びない」ケースです。
例えば、中学1年で勉強につまづき、苦手を抱えている場合、塾で集団授業を受けても成果に結びつけるのは難しいはずです。必要なのは「学び直し」にも関わらず、授業では中学3年の予習範囲が進むからです。苦手に目を向けない限り、成績は上がりません。
本来必要としている学習内容と、実際に行われている指導にズレがある場合、早急に状態を修正する必要があります。先生と生徒、保護者の三者間で認識をすり合わせ、調整をお願いしましょう。
自分で勉強を進めている場合も同様です。親や先生など周りの意見も聞きながら、現在の勉強方法が合っているか、確認する必要があります。
勉強を成績アップに繋げる!伸び悩み対策4STEP
伸び悩みの原因が分かったら、対策を考えます。「塾に行く」「家庭教師をつける」といった判断は、必要な対策を講じてからでも遅くありません。自己分析が進めば、塾や家庭教師に求めるべき内容も的確に判断できるのではないでしょうか。
①現状把握のために模試を受験する
まずは現状の成績を分析するために模試を受験します。学校の実力テストは「偏差値が出ない」「都道府県内での相対的な立ち位置が分からない」などの弱点があります。居住地で実施される模試を受けるのが適切です。近隣の塾やWeb(指定会場)で申し込めます。
②苦手分野・強化ポイントを正確に把握
<数学の分析例>
- 基礎から復習が必要な分野・・・一次関数(式の求め方、グラフの読み取り方、交点の出し方)
- 基礎は定着しているが応用がきかない分野・・・連立方程式(文章題の立式)
模試の成績が出たら、科目ごとに「苦手分野」「強化ポイント」を分析します。自分の苦手がはっきり認識できれば、何をどう勉強するべきか見えてきます。苦手に一つひとつ取り組みながら、入試までに不得意分野をなくしましょう。
③他人の手も借りて「自分に合った勉強法」を理解する
勉強するべき内容が分かったら、自分に合った勉強法を見つけ出します。参考になるのは「思考の癖」や「認知特性」などですが、中学生が自分自身をしっかりと分析するのは、あまり現実的とは言えません。親や学校の先生、塾の先生など信頼できる大人に意見をもらうのが適切ではないでしょうか。
④教科書レベルから苦手分野の復習を始める
勉強法も理解したら、教科書の復習から取り掛かりましょう。難しいことを行うのではなく、基礎徹底を心がけます。他人に説明できるレベルまで演習を進め、徐々に応用を取り入れるよう工夫します。
また、もし塾や家庭教師に頼るなら、「自分に合った勉強法」で苦手に寄り添ってくれる先生を見つけましょう。要望や方向性をできるだけ詳しく伝えること、可能であれば体験授業を受けることをおすすめします。
受験生必見!科目別伸び悩み対策
ここからは講師の立場で、科目ごとの伸び悩みに対するアドバイスを行います。強化するべき内容が分かっても、勉強の進め方が分からなければ取り組みようがありません。科目ごとに重視するポイントを認識しましょう。
【英語】文法や語彙だけでなく早期の長文対策を
受験英語では、長文対策が重要です。公立私立を問わず、英語の中心に据えられるのは長文です。難関私立高校や東京都の進学指導重点校では、一見、大学入試と思ってしまうほどの長文を出題する学校もあります。語彙力はもちろん、スピードや正確性が大きなテーマです。
公立中学校では初見の長文をすばやく読む訓練はあまり行わないと思います。ですので、教科書以外で長文に触れる機会が少ないと、模試で面食らうことが多くなってしまうでしょう。できるだけ早くから長文問題に取り組み、目を慣らす必要があります。
【数学】分からなくなった部分に戻り基礎を徹底する
数学は積み重ねの学問です。分からない問題を解くには、何が分かっていないかを特定する必要があります。学習内容をさかのぼり、復習の起点とする部分を探し出しましょう。
たとえば二次方程式が解けない場合、因数分解や平方根が定着していない可能性があります。さらに因数分解や平方根の円滑な計算には、基礎計算を正確に行う力が必要です。中1範囲から復習した方が良い場合もあります。
極端に時間をさかのぼるのは、「面倒」「無駄」と感じるかもしれません。ただ、数学は前の内容とのつながりが強いので、本質的な理解なしには解けないことを認識しましょう。
【国語】解くことより文章への抵抗をなくす努力を
国語が苦手なお子さんは「何となく文章は読める。けど、内容がなかなか頭に入らない」状態に陥っている可能性があります。問題にあたる前に、長い文章を頭に入れる工夫をしなければなりません。
一般的に、国語の力は文章の要約に取り組むことで伸びると言われます。ただ、文字の羅列を追っているだけの状態では、論理的にまとめようがありません。読み慣れることにフォーカスするのが重要です。
おすすめは、好きな本を好きなように読むことです。読む習慣をつけ、文章への抵抗をなくしましょう。題材は小説でも児童書でも、Web記事でも構いません。慣れてくれば、少しずつ文字の羅列を意味として捉えられるようになります。
【理科】苦手分野の基礎演習で集中的に復習する
本来、理科は実験で現象を体感するのが一番記憶に残るのではないでしょうか。ただ、中学で扱う分野は想像に頼らざるを得ない部分も多く、全てを体感できるわけではありません。復習では少しでも記憶に定着させられるよう、仕組みや理屈を意識することが大切です。
生物や地学では図や表を使い、自分なりに理屈付けると効果的です。化学・物理は「なぜそうなるのか」を、先生に簡単な言葉で説明してもらうと納得しやすいでしょう。一度納得したものは、記憶に留まりやすく、応用もききます。基礎問題から順に演習し、問題に慣れていきましょう。
【社会】闇雲な暗記より定着する知識をつくる努力が大切
社会は「覚えればできる」とも言われます。ただ実際は、地理・歴史・公民すべてに興味を持ち、積極的に暗記できる人は稀です。興味がないものを無理やり頭に詰め込むだけでは、入試まで記憶を保持できません。
長続きする記憶を作るには「ストーリー」「原因と結果」「自分との結びつき」などを意識すると効果的です。たとえば歴史の場合、年号と出来事だけを覚えるのではなく、「時代背景」「その出来事が起こる原因」「結果とその後の変化」「現代社会への影響」などを一緒に覚えると良いでしょう。頭の中にストーリーが出来上がり、断片的な項目が繋がって感じられます。
自分なりに流れを整理しながらノートをつくると、ストーリーを形成しやすくなります。
模試の成績が伸び悩むお子さんに保護者の方がするべきこと
最後に受験生の保護者様に向け、お子さんが成績の伸び悩みを抱えたときの対処法をお伝えします。少しでもご参考にしていただければ嬉しいです。
怒るのではなく原因を一緒に分析する
模試の成績が悪いと、つい「本当に勉強しているの?」と疑いたくなります。ただ、明らかに勉強していない場合以外は、怒ったり強くあたるのは得策とは言えません。お子さんは努力しているのに成績が伸びないことに、悩み傷ついているかもしれません。そんな場合は、保護者の方の言葉が、余計に傷口を広げる可能性もあります。
お子さんに必要なのは、勉強しているのに成績が上がらない原因の究明と、解決に向けたアクションです。お子さん一人でどうにもならないなら、一緒に考えてあげてください。親だからこそ分かる特性、考え方の癖などが、解決の糸口になるかもしれません。
お子さんが決めたことを完遂できるよう励まし見守る
お子さんが勉強の方針を決めて取り組んでいるなら、決めたことを完遂できるよう、励まし見守ってください。万一、結果が出なかったら、次の模試までに軌道修正を行うはずです。
ただ、お子さんが投げやりになったとき、自分を見失ったときなどは積極的に相談に乗ってあげることも大切だと思います。
小さな成功体験でもねぎらう
勉強した範囲の成績が伸びたり、基礎問題のミスが減っているなどの進歩があれば、積極的にねぎらうことも忘れないでください。お子さんは「自分の勉強は正しいのかな?」「成績は本当に伸びるかな?」と不安を感じている時もあると思います。
ちょっとしたことでも、お子さんの努力を認めることで、自分の勉強方法に自信を持ち、迷わず進めるようになります。保護者の方の言葉が、勉強を続ける原動力になるのではないでしょうか。
まとめ〜焦らず地道に受験勉強を進めよう
<模試で結果が出ないときに考えられる原因>
・受験勉強を始めて日が浅い
・中1・中2範囲の内容が定着していない
・基礎が抜けたまま勉強を進めている
・相対的に見て勉強時間が足りていない
・勉強法が自分に合わない
上記のいずれかにあてはまるお子さんは、模試で思うように成績が伸びないと思います。「努力が足りない」「実力がない」と自分を責めるのではなく、以下の4STEPで勉強方法を見直しましょう。
<受験勉強の4STEP>
①結果を分析するために模試を受ける
②苦手分野を正確に把握し、強化ポイントを見定める
③親や先生の意見を聞きながら、自分に合った勉強法を見つける
④教科書レベルから苦手分野の復習を始め、徐々にステップアップする
成果はすぐには現れないかもしれません。ただ、地道に努力を続けることで、基礎がしっかりと構築されます。次第に応用問題にも対応できる力がつくでしょう。長い道のりだからこそ、焦らず前を向き続けることが大切です。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。