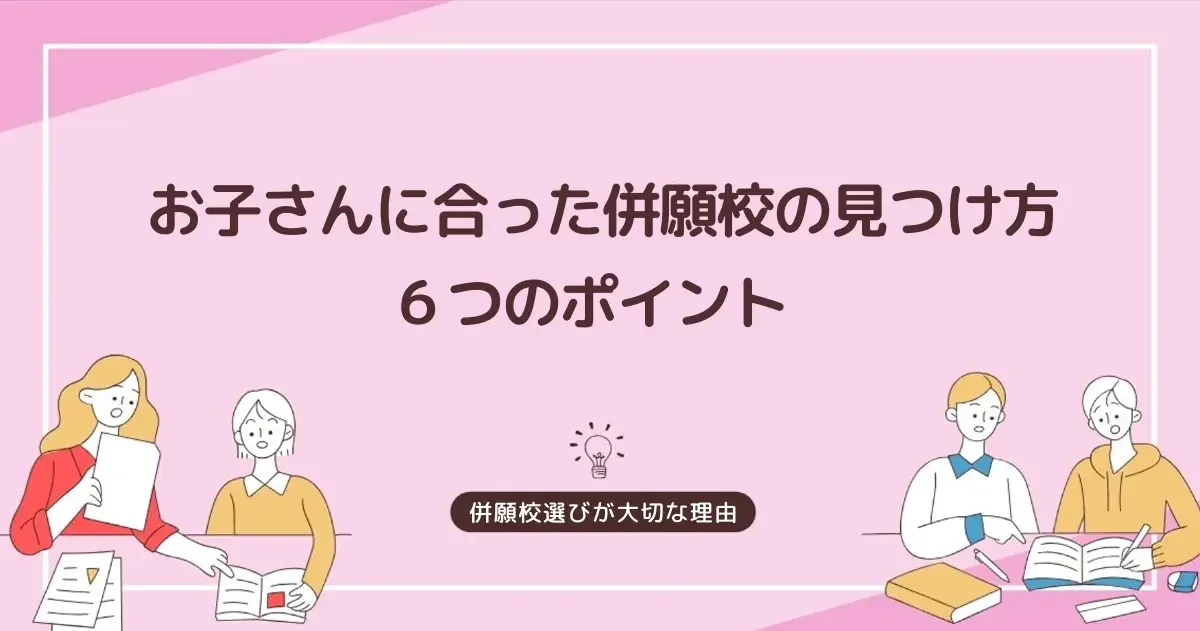なぜ併願校選びが大切なのか?…
受験の時期が近づいてくると、どうしても「第一志望の学校に合格すること」に気持ちが集中しがちです。もちろん、行きたい学校に合格するために気持ちを集中させたり、努力することはとても大切です。でも、受験には“絶対”がありません。思うような結果に結びつかない場合もあります。
そんなときに支えになるのが、併願校の存在です。併願校は、第一志望とは別に受験する学校のことです。「すべり止め」と呼ばれることも多いですが、実際にはただの保険ではありません。
「もし第一志望校以外なら、どの学校に通いたいか?」
この問いにしっかり向き合って併願校を選ぶことで、受験本番への不安が減り、お子さんも落ち着いて試験にのぞむことができます。
この記事では、お子さんにとって後悔のない併願校選びをするために、6つの大切なポイントをご紹介します。今からできる準備として、お子さんと保護者の方のお役に立てれば嬉しく思います。
①情報は早めに集めよう|秋からでは遅いかも?
併願校選びは、できるだけ早い段階からスタートするのがおすすめです。多くのご家庭では「秋になってから説明会に行こう」「進路面談が始まってから考えよう」と思いがちですが、実際には中学3年生の春や夏から動き出しておくと安心です。
なぜなら、併願校の中には説明会やオープンキャンパスが夏休み前後に集中している学校が多いからです。見学のタイミングを逃すと、「パンフレットやネットだけの情報で選ばなければならない」という状況になってしまうことも。情報を集める方法には以下のようなものがあります。
■学校説明会に参加する:学校の方針や学習スタイルがよくわかります。
■オープンキャンパスで実際の雰囲気を見る:校舎の設備や先生、生徒の様子が体感できます。
■先輩や保護者に話を聞く:もし身近に在校生や卒業生がいる場合は、直接聞いてみるとリアルな声が聞けるため、とても参考になります。
■インターネットやSNSで調べる:最近は動画で学校紹介をしているところも多く、イメージしやすいと思います。
このように、自分の目や耳で確かめることが併願校選びではとても大切です。
②志望校とのレベルのバランスを考えて選ぼう
受験校の組み合わせにはバランスが必要です。すべてが高いレベルの学校だと、リスクが高くなりすぎてしまいます。逆に、全部が簡単すぎると、お子さんの力を十分に活かすことができません。よくある受験パターンは以下のようなバランスです。
■合格するのが少し難しいが、頑張れば届く学校
■今の学力で合格の可能性が高い学校
■安心して合格できる学校
併願校は、安全策として選ぶ意味もありますが、「この学校なら入れそうだから」だけで決めるのはもったいないです。「実際に通うことになるかもしれない学校」として、しっかり選ぶことが必要です。
学校によっては、偏差値の数字だけではわからない魅力がたくさんあります。「ここなら、第一志望でなくても納得できる」と思える学校を併願校にできたら、受験後の気持ちの整理もしやすくなります。
③お子さんが「行ってもいいな」と思える学校を選ぼう
どれだけ成績的に合格しやすくても、お子さんが「ここには行きたくないな」と感じている学校を併願校にしてしまうと、もし、実際に進学することになったときに後悔する可能性もあります。
併願校を選ぶときには、通いやすさだけでなく、「この学校に通ってもいい」と思えるかどうかを重視しましょう。たとえば以下のようなことが判断のポイントになります。
■通学時間と交通の便利さ
■部活動の内容や実績
■進学実績や就職サポート
■先生の雰囲気やサポート体制
■学校のイベントや校則のゆるさ・厳しさ
■学費や制服、施設の印象
また、お子さんの性格や価値観に合っているかも大切です。たとえば、個別対応が丁寧な学校を好む子もいれば、大人数でにぎやかに過ごす学校が合っている子もいます。
「行ける学校」ではなく、「行きたいと思える学校」を併願校にする意識が大切です。
④併願校の試験も、しっかり対策しよう
併願校は「すべり止め」だからといって油断してしまうと、試験で思うように力を発揮できないこともあります。特に、第一志望と試験内容が違う場合には注意が必要です。たとえば以下のような違いがあります。
■記述式と選択式の比率が違う
■面接や作文の有無
■リスニングがあるか・ないか
■英語の難しさの違い
■内申点と当日点の配点バランス
こうした違いに気づかずに本番を迎えると、「え?こんな問題出るの?」と焦ってしまい、思わぬ失点につながってしまうことも…。
併願校が決まったら、最低でも過去問には取り組んでおきましょう。過去問は、当然ですが、1年分より2年分、2年分より3年分…と、多く取り組む方がいいです。慣れておくことで、本番で落ち着いて問題に臨むことができます。
⑤受験スケジュールを確認しよう|日程の重なりに注意!
意外と忘れがちなのが、受験日程の調整です。特に私立高校を複数受ける場合、受験日が同じ日だったり、遠い場所で連続した日程になっていたりすると、体力的にも精神的にも大きな負担になります。
■A高校:2月10日
■B高校:2月11日(場所が遠くて朝早く出なければ間に合わない)
■C高校:2月12日(3日連続の試験で体力的につらい)
もちろん、A高・B高・C高の全てが「受験したい高校」なら別ですが、こういったスケジュールになると、体調を崩したり、実力が発揮できなかったりすることもあるかも知れません。対策としては、以下のような工夫が有効です。
■受験カレンダーを作成して、日程の重なりや移動時間を確認する
■余裕を持って受験できる日程の学校を選ぶ
■「試験を受けるかどうかは後で決める」学校も、候補に入れておく
受験スケジュールをうまく組めば、心と体に余裕をもって受験に臨めます。
⑥検定や大会実績が評価される学校もある
最近では、英検、漢検などの検定資格が入試で評価される学校が増えています。また、スポーツや音楽などの分野で優れた実績を持つお子さんにも、特別な枠や優遇制度がある場合があります。たとえば…
■英検準2級以上で加点がある
■全国大会や県大会での入賞が評価対象になる
これらの情報は、学校説明会や公式HPで公開されていることが多いです。思わぬところで自分の強みが活かせるかもしれないので、しっかり確認しておく必要があります。
まとめ|併願校も大切な「選択肢のひとつ」
ここまで、併願校を選ぶときのポイントを6つに分けてご紹介してきました。
①情報は早めに集める
②志望校とのバランスを考える
③通いたいと思える学校を選ぶ
④試験対策も忘れずに
⑤日程の重なりに注意する
⑥検定や実績が活かせる学校もある
併願校は、万が一のためだけに選ぶ学校ではありません。むしろ、「ここでなら3年間しっかり過ごせそう」と思える学校を見つけることが、お子さんにとっても、保護者の方にとっても安心感につながります。
受験は不安も多いと思いますが、「どの学校に通っても、がんばれば道は開ける」という前向きな気持ちで、進路を考えていけるといいのではないでしょうか。
参考文献:高校受験は「内申点アップ」が9割(桂野智也著/青春出版社)
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。志望校選びのアドバイスもできますので、お気軽にお問い合わせください。
また、受験対策をはじめとした、お子さんと保護者の方に役立つ様々な情報を発信しています。ご興味のある方はぜひ、ご参考にしてください。