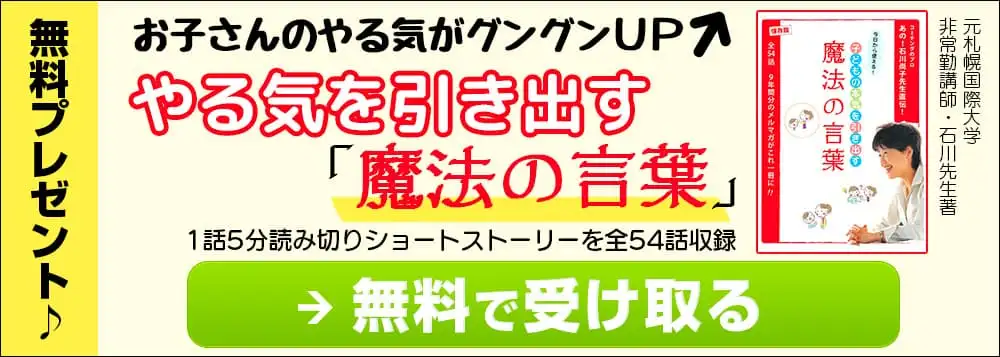「うちの子、高い塾代を払って通わせているのに、一向に成績が上がらない…」
「むしろ、塾の宿題に追われて、学校の提出物まで疎かになっている気がする…」
そんな子を持つ親御さんのための記事です!!
はじめまして。私は「家庭教師のガンバ」の体験スタッフTです。日々、勉強が苦手だったり、これから頑張りたいと思っていたりするお子さんと保護者の皆様のご自宅に伺い、一人ひとりに合った勉強のやり方から一緒に見つけていくお手伝いをしています。
やる気が出ない・集中できない・・・それでも合格できる高校受験対策とは?>>
私たちが訪問するご家庭で、今まさに上で挙げたような悩みを抱えているケースが非常に増えています。「塾に行かせさえすれば安心」――そう思っていたのに、模試の結果は横ばいか、むしろ下がっている。中学3年生が近づくにつれ、親御さんの焦りはピークに達します。
なぜ、こんなことが起きてしまうのでしょうか?
それは、お子さんのやる気がないからでも、塾の先生の教え方が悪いからでもありません。 ただ純粋に、お子さんの現在の学力や性格と、塾という学習環境の「ミスマッチ」が起きている可能性が非常に高いのです。
この記事では、35年間も「勉強が苦手」な生徒さんたちと、とことん向き合ってきた家庭教師会社の視点から、なぜ塾に行っても成績が上がらないのか、その根本的な理由を5つに分解し、今すぐご家庭で実践できる具体的な受験対策術を徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、「うちの子は、なぜ伸び悩んでいたのか」という原因が明確になり、「今、何をすべきか」という具体的な行動プランが見えているはずです。
なぜ? 塾に通っているのに成績が上がらない「5つの根本理由」
塾は、受験対策の王道のように思えます。しかし、特に「勉強が苦手」と感じているお子さんにとって、塾のシステムが逆効果になってしまうことが少なくありません。
理由1:授業のペースについていけず「お客様状態」になっている
多くの進学塾は、学校の授業を先取りする形で、決められたカリキュラムに沿ってハイスピードで進んでいきます。これは、難関校を目指す生徒にとっては効率的ですが、勉強が苦手な子にとっては大きな負担です。
- 「さっきのところ、よくわからなかったな…」
- 「この公式、いつ使うんだろう…」
そう思っても、授業はどんどん先に進んでしまいます。集団授業の中で「すみません、わかりません」と手を挙げるのは、大人でも勇気がいることです。ましてや思春期の中学生なら、なおさらでしょう。
結果、お子さんはただ座って黒板を写しているだけの「お客様状態」になってしまいます。週に数時間、わからない授業を受け続けることは、むしろ「勉強はやっぱりつまらない」「自分には無理だ」という苦手意識を強めてしまう危険すらあるのです。
理由2:質問ができず「わからない」が雪だるま式に蓄積している
理由1とも関連しますが、「質問ができない」環境は致命的です。勉強が苦手な子は、そもそも「自分が何がわからないのかすら、わからない」という状態に陥っていることが多々あります。
- 授業後、先生のところに質問に行こうにも、他の生徒が列を作っていて気後れする。
- なんとなく質問しづらい雰囲気で、結局そのまま帰宅してしまう。
- 質問しようにも、どこから手をつけていいか言葉にできない。
一つひとつの「わからない」は小さくても、それが蓄積すれば、あっという間に巨大な雪だるまになります。数学で言えば、「正負の数」の理解が曖昧なまま「方程式」に進み、「方程式」がわからないまま「関数」に進む…という状態です。土台がグラグラなまま家を建てるようなもので、どれだけ塾で新しい知識を上塗りしても、テストで点数が取れるようにはなりません。
理由3:演習(アウトプット)不足で「わかったつもり」になっている
塾の授業は、プロの講師による非常にわかりやすい解説が魅力です。お子さんも授業中は「なるほど!」「わかった!」とスッキリした顔をしているかもしれません。
しかし、これが最大の落とし穴です。「わかる(インプット)」と「できる(アウトプット)」の間には、天と地ほどの差があります。
授業を聞いて「わかったつもり」になっただけで、いざ一人で問題集を開いてみると、手が止まってしまう。これは、演習量が絶対的に不足している証拠です。塾の宿題は出されるかもしれませんが、それが「解説を丸写しするだけ」の作業になっていませんか?
勉強が苦手な子ほど、この「わかったつもり」のワナに陥りやすく、自分では勉強している「つもり」なのに、一向に点数に結びつかないという悪循環に陥ります。
理由4:本当のつまずき(小学校の範囲など)が放置されている
これは、私たちが体験授業で最も重視するポイントです。 例えば、中学2年生で数学の「連立方程式の文章題」が苦手だとします。塾では当然、連立方程式の解き方を教えます。しかし、その子の本当のつまずきが、中学1年生の「文字式のルール」や、もっと言えば小学校5年生の「割合(%)」「速さ・時間・道のり」にあったとしたらどうでしょう?
どれだけ連立方程式のテクニックを学んでも、土台となる知識が抜けていては、応用問題は解けません。
集団塾は、カリキュラム上、そこまでさかのぼって指導することは困難です。
結果として、根本的な弱点が放置されたままになり、お子さんは「自分は数学のセンスがないんだ」と諦めてしまうのです。
理由5:家庭学習の「やり方」を教えてもらっていない
塾は、基本的に「授業をする場所」です。もちろん自習室を提供したり、宿題を出したりはしますが、「家で一人でいる時間に、どうやって勉強を進めるか」という、最も重要な部分までは指導してくれないケースがほとんどです。
- テスト前に、どこから復習を始めればいいかわからない。
- ノートの取り方がわからず、後で見返しても何が重要かわからない。
- 英単語や漢字の、効率的な暗記法を知らない。
- そもそも、勉強の計画の立て方がわからない。
勉強が苦手な子は、この「勉強のやり方」そのものを知りません。塾に通うことで、勉強している「時間」は増えても、勉強の「質」が改善されていないため、成績が上がらないのです。
塾で伸びない…勉強が苦手な中学生のための「逆転」受験対策術
では、塾に行っても成績が上がらない場合、どうすればいいのでしょうか。「うちの子には無理だ」と諦めるのは、まだ早すぎます。今すぐご家庭でできる、具体的な対策術をご紹介します。
対策1:【最重要】「さかのぼり学習」で本当の弱点を見つける
成績が上がらない最大の原因は、前述の通り「根本的なつまずき」が放置されていることです。これを解決する唯一の方法が「さかのぼり学習」です。
これは、勇気がいる作業です。「中学3年生にもなって、小学校のドリルをやるなんて…」と抵抗を感じるお子さんや親御さんもいらっしゃいます。しかし、私たちが断言します。これが合格への最短ルートです。
<さかのぼり学習の進め方>
- 弱点の特定:直近のテストや模試の答案を広げ、間違えた問題を見てみます。
- 単元の特定:例えば「1次関数」で間違えたとします。
- さかのぼり:
- 1次関数(中2)がわからない ↓
- もしかして「比例・反比例」(中1)が怪しい? ↓
- さらに「方程式」(中1)の移項ができていない? ↓
- 「正負の数」の計算(中1)が曖昧? ↓
- いや、そもそも「分数・小数」の計算(小5)でつまずいている!
このように、お子さんが「ここなら完璧にわかる!」と自信を持って言える単元まで、徹底的にさかのぼります。そして、そこをスタート地点にするのです。
市販されている「総復習ドリル」などを使い、簡単な問題を解いて「できた!」という成功体験を積ませることが重要です。急がば回れ。土台を固めれば、その上に積み上げる知識は、驚くほど安定します。
対策2:勉強時間を「量」から「質」へ転換する
「1日3時間勉強しなさい!」 そう言われて、ダラダラと3時間机に向かうのと、集中して1時間問題演習をするのでは、後者の方が圧倒的に成果が出ます。
<勉強の「質」を高める具体例>
- 「解き直し」こそが勉強の核: 勉強が苦手な子は、問題集を解いて丸付けをし、「あー、間違えた」で終わってしまいます。一番成績が伸びるのは、この「間違えた後」です。 なぜ間違えたのか?(計算ミス?公式忘れ?勘違い?)を分析し、解説を読み、何も見ないで、もう一度自力で解き直す。この「解き直し」の時間を、新しく問題を解く時間よりも大切にしてください。「間違いノート」を作るのも非常に効果的です。
- 「インプット3割、アウトプット7割」を意識する: 授業を聞いたり、教科書を読んだりする「インプット」の時間は、勉強全体の3割で十分です。残りの7割は、実際に問題を解く「アウトプット」に使いましょう。知識は、使って初めて定着します。
対策3:勉強の「やり方」そのものを具体的に教える
勉強が苦手な子は、具体的な「作業」に落とし込んであげないと動けません。「英語を勉強しなさい」ではなく、「今日は、この単語帳のP.10〜11の20個を、15分で覚えて、その後テストしよう」と具体的に指示します。
私たち「家庭教師のガンバ」が体験授業で必ずお伝えしている「やり方」の一部をご紹介します。
<すぐに使える「勉強のやり方」>
- 英単語の暗記法: 「書いて覚える」のは効率が悪いことが多いです。おすすめは「音読」です。単語を見て、発音し、日本語訳を言う。これを10個の単語で1セットとし、スピーディーに5周繰り返します。目(視覚)、口(運動)、耳(聴覚)をすべて使うため、記憶に定着しやすくなります。
- 数学の「解き直し」ノート: ノートの左ページに、間違えた問題のコピーを貼る。右ページに、①なぜ間違えたかの分析、②正しい解き方のポイント、③(可能なら)類題、を書きます。テスト前にこのノートを見返すだけで、自分だけの最強の参考書になります。
対策4:親子で「学習計画」を立て、進捗を「見える化」する
「いつまでに、何を、どれだけやるか」が曖昧だと、勉強は後回しになります。 しかし、お子さん一人で計画を立てるのは困難です。ここはぜひ、親御さんがサポートしてあげてください。
<実行可能な計画の立て方>
- ゴールから逆算する:次の定期テスト、次の模試、そして入試本番というゴールを設定します。
- やるべきことを書き出す:さかのぼり学習で見つかった弱点、学校のワーク、塾の宿題などをすべてリストアップします。
- 週単位→日単位に落とし込む: 「今週は、数学のワークをP.50まで終わらせる」と決めたら、 「じゃあ、月曜にP.46-47、水曜にP.48-49、金曜にP.50をやろう。火曜と木曜は英語の単語にしよう」 というように、**「今日やること」**を明確にします。
大切なのは、最初から詰め込みすぎないことです。まずは「これなら絶対にできる」という量から始めましょう。そして、カレンダーやホワイトボードに書き出し、終わったら花マルをつけるなど、「進んでいる」ことを親子で「見える化」すると、モチベーション維持に繋がります。
塾が合わないなら…「家庭教師」という選択肢
ここまでご家庭でできる対策術をお伝えしましたが、 「親が言うと、どうしても感情的になって喧嘩になってしまう」 「さかのぼり学習が必要なのはわかったが、どこから手をつけていいか親では判断できない」 という壁にぶつかることも多いかと思います。
もし、今通っている塾がお子さんに合っていないと明確に感じられるなら、勇気を持って学習環境を変えることも、立派な受験対策術の一つです。
そして、その有力な選択肢が、私たち「家庭教師」です。
集団塾が「多くの生徒を平均的に引き上げる」のが得意なのに対し、家庭教師は「勉強が苦手な一人の生徒を、その子のペースで徹底的に引き上げる」プロフェッショナルです。
家庭教師が「塾で伸びない子」に最適な理由
- 完全1対1で「わからない」をその場で解決: お子さんの隣に座り、手元を見ながら指導します。わからない表情を見逃さず、「ん?今、手が止まったね。どこで悩んでる?」と即座に声をかけられます。「質問できない」という悩みは、家庭教師なら100%解消されます。
- その子だけの「さかのぼり学習」プランを組める: 私たちは、お子さんの学力を正確に診断し、たとえ小学校の範囲であっても、必要な場所まで迷わずさかのぼります。そして、お子さん専用のカリキュラムを組み、合格までの最短ルートを設計します。
- 勉強の「やり方」から徹底的に指導: 私たちは、教科の内容を教えるだけではありません。ノートの取り方、暗記の仕方、計画の立て方、時間の使い方といった「勉強のやり方」そのものを、お子さんが一人でできるようになるまで、根気強く指導します。
- 精神的な「伴走者」になれる: 親でも学校の先生でもない、「ナナメの関係」の大人だからこそ、お子さんも本音を話しやすいことがあります。「最近、部活で疲れてて…」「友達とケンカして…」そんな雑談の中から信頼関係を築き、勉強面だけでなく精神面でもお子さんを支える「一番の味方」になります。
まとめ:お子さんに合った場所で、自信を取り戻そう
「塾に行っているのに成績が上がらない」 この事実は、お子さんからの「今のやり方、合ってないかも!」というSOSのサインです。 決して、お子さんの能力を否定するものではありません。
重要なのは、そのサインを見逃さず、できるだけ早く対策を打つことです。
今回ご紹介した対策術は以下の通りです。
- 原因を知る:(ペースが合わない、質問できない、わかったつもり、弱点放置、やり方を知らない)
- 「さかのぼり学習」を敢行する
- 勉強の「質」を高める(特に「解き直し」)
- 「勉強のやり方」を具体的に教える
- 親子で計画を「見える化」する
- 合わない環境(塾)に見切りをつけ、家庭教師など他の選択肢を検討する
私たち「家庭教師のガンバ」では、まさに今、こうした悩みを抱えているご家庭のために「無料の体験授業」を行っています。 そこでは、強引な勧誘は一切ありません。まずはお子さんの学習状況や親御さんの悩みをじっくりお伺いし、家庭教師の視点から「なぜ成績が上がらないのか」「今、何をすべきか」を具体的にアドバイスさせていただきます。
この記事を読んだだけでは、まだ不安かもしれません。ぜひ一度、私たちの目で、お子さんの可能性を診断させてください。 受験は団体戦です。親子だけで抱え込まず、私たちのような家庭教師を「チームの一員」として頼っていただけたら幸いです。
お子さんに合った学習環境さえ見つかれば、子どもは驚くほどのスピードで変わり始めます。 最高の春を迎えるために、今、この瞬間から第一歩を踏み出しましょう。
家庭教師のガンバ T