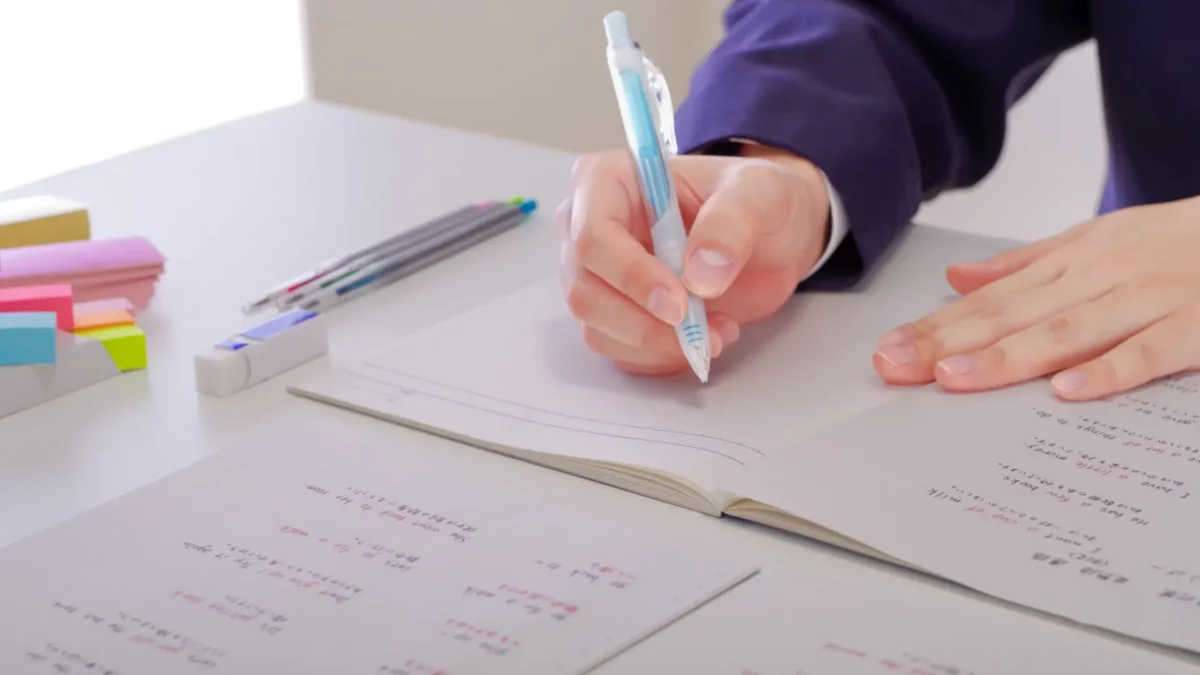模試の結果が返ってくると、つい真っ先に「偏差値」「判定」「順位」に目がいってしまいますよね。
「偏差値が下がってる…」
「志望校の判定がEになってしまった…」
「この成績で本当に高校受験、大丈夫なの?」
お子さん以上に、保護者の方がドキッとしてしまうことも多いと思います。
でも、模試の本当の価値は「良い判定を取ること」ではなく、「結果をどう分析して、次にどうつなげるか」にあります。
模試はあくまで“途中経過のチェック”であって、“合否の判決”ではありません。
この記事では、
模試の結果の見方(どこをどう見ればいいのか)
「偏差値」「判定」「正答率」などの意味
苦手分野の見つけ方と伸ばし方
模試後1週間でやっておきたい復習のポイント
保護者ができる声かけ・サポートのコツ
を、できるだけわかりやすく解説していきます。
「模試の成績表を見るたびに落ち込んでしまう…」
そんなご家庭にこそ読んでいただきたい、“親子で前向きになれる模試の結果の見方”です。
塾に行っても成績が上がらない…勉強が苦手な中学生のための受験対策術>>
1.模試の結果は「合否」ではなく「健康診断の結果」
まず最初にお伝えしたいのは、
模試=合格・不合格の判定ではない
模試=学力の健康診断
という考え方です。
健康診断の結果を見たとき、
「血圧が少し高めだから、食生活を見直そう」
「コレステロールが基準より上だから、運動を増やそう」
と“改善に活かす”イメージで見ると思いますよね。
模試の結果も同じで、
「この教科の点数が低いから、ここの単元を復習しよう」
「ケアレスミスが多かったから、見直しの仕方を変えてみよう」
といった形で、「次の学習計画にどう反映するか」が何より大切です。
偏差値や判定だけを見て落ち込んで終わってしまうと、模試の意味が半分しか活かせません。
逆に言えば、模試の成績表をうまく読めるようになると、それだけで受験勉強の質がグッと上がります。
2.偏差値より大事?「教科別の得点バランス」をチェック
模試の結果の見方として、保護者の方にまず意識してほしいのが、
「総合偏差値」よりも「教科別のバランス」
です。
●こんなパターン、心当たりありませんか?
合計点はそこまで悪くないのに、英語と数学だけ極端に低い
理科・社会で点数を稼いで、主要教科の弱点をカバーしている
どの教科も横並びで“平均〜少し下”くらい
一見同じような総合点・偏差値でも、教科バランスによって志望校との相性や、今後の伸び方が大きく変わります。
●志望校の配点と照らし合わせてみよう
高校受験では、学校ごとに
「英語・数学の配点が高い学校」
「5教科均等の学校」
「国語・英語重視の学校」
など、配点バランスが違います。
たとえば、
志望校が「英数重視型」で、英語・数学の点数が明らかに低い
→ 早めのテコ入れが必要なサイン5教科が大きな差なく“中くらい”にそろっている
→ 苦手教科を底上げすると、短期間でも合計点を伸ばしやすい
など、「どの教科にどれだけ時間をかけるべきか」のヒントが見えてきます。
●親子で一緒に“作戦会議”を
成績表を前にして、お子さんと一緒に次のような会話をしてみてください。
「この教科は前回より頑張れたね」
「この教科は志望校の配点が高いから、ここを少し上げるとすごく有利になりそうだね」
「どの教科を優先的に伸ばしたい?」
ポイントは、
「この教科がダメ」ではなく
「この教科をどう補強していこうか?」
という“改善の視点”で話すことです。
これだけで、模試の結果が「ダメ出し」ではなく、「作戦会議の材料」に変わります。
3.A〜E判定はどこまで信じていい?
「判定の落とし穴」と正しい受け止め方
模試の結果の見方で、保護者の方が一番気にされるのが「志望校判定(A〜E)」ではないでしょうか。
A判定 → 「もう大丈夫かな?」と安心
E判定 → 「もう無理なんじゃ…」と大きな不安
どうしても、心が揺れ動いてしまいますよね。
●判定は“今の位置”を示す「写真」
判定は、「今この模試の段階で、同じ模試を受けている受験生の中での位置」を示したものです。
受けている生徒層(トップ層が多い/中間層が多いなど)
その模試の難易度
実施時期(受験直前なのか、まだ中2〜中3の早い時期なのか)
によって、同じ点数・同じ偏差値でも判定の出方は変わります。
ですから、
「E判定だから絶望的」
「A判定だからもう安心」
と、判定だけで一喜一憂しすぎないことがとても大切です。
●判定を見るときの3つのポイント
模試の種類・受験者層を確認する
全国模試なのか、地域限定なのか、塾内模試なのかで、判定の“重さ”は変わります。時期を考える
中3の夏前と、冬の直前模試では意味合いが違います。早い時期のC〜D判定なら「ここからどれだけ伸ばせるか」が勝負です。志望校のレベルとの“距離”を把握する
判定だけでなく、「合格圏まであと何点くらいなのか」「どの教科を何点上げる必要があるのか」を一緒に確認しましょう。
保護者のスタンスとしては、
「この判定はダメだ」ではなく、
「この判定から、次にどんな一歩が必要か考えよう」
という方向に会話を持っていってあげると、お子さんの心が折れにくくなります。
4.正答率・全国平均で見る「今の立ち位置」
最近の模試の成績表には、
問題ごとの正答率
単元ごとの全国平均点
同じ志望校を受ける受験生の平均
など、細かいデータが載っていることも多くなっています。
これをうまく使うと、**お子さんが「全国の中でどのあたりにいるのか」**を、感覚ではなく“数字で”把握しやすくなります。
●「全国との差=伸びしろ」と考える
たとえば、ある単元で
全国平均が60%
お子さんが40%
だったとします。
このとき、
「全国より20%低い=20ポイント伸びる余地がある」
というポジティブな見方もできます。
逆に、
全国平均70%
お子さん68%
であれば、「ここは大きな弱点ではないから、他の単元を優先したほうが効率的かも?」という判断もできます。
●親子で使える声かけ例
成績表を見ながら、こんなふうに話してみてください。
「この単元は、全国平均よりちょっと低いね。あと何点くらい取れたら届きそうかな?」
「ここは全国平均より上だね。得意なところがはっきりしてきたね」
「この単元を得意にできたら、志望校にかなり近づけそうだね」
「できていないところ探し」ではなく、
「どこに伸びしろがあるか」
「どこを強みにしていけそうか」
という視点で話すだけで、お子さんの受け止め方は大きく変わります。
5.苦手分野こそ“最も点数が上がる場所”
模試の結果を見ると、どうしても目についてしまうのが「苦手教科」「苦手単元」ですよね。
「国語の長文が全然できていない…」
「数学の文章題になるとガクッと点数が落ちる…」
「英語のリスニングでほとんど点が取れていない…」
保護者としても心配になりますが、ここでの考え方がとても大事です。
●「苦手=ダメなところ」ではなく「一番伸びるところ」
苦手な教科・単元は、見方を変えると
「点数を一番伸ばせるチャンスがある場所」
です。
たとえば、今60点の教科を70点に上げるのと、20点の教科を40点に上げるのでは、後者のほうが合計点の伸び幅は大きくなります。
●分析のステップ
成績表の「分野別・単元別」の欄を見る
全国平均との差が大きい単元に印をつける
その中から、「志望校でもよく出る単元」「配点が高い分野」を優先候補にする
お子さんと一緒に、「なぜ点が取れなかったのか」を話し合う
例:
基礎知識がうろ覚えだった
そもそも習っていない(学校の進度の問題)
見直しの時間がなくて焦ってミスした
「この単元が●点上がると、この教科全体でどれくらい上がりそうか」をざっくりでいいので計算してみる
こうすることで、お子さん自身も
「苦手だから怖い」ではなく
「ここを上げれば一気に点数が変わる」
という感覚を持ちやすくなります。
6.ミスの原因を「知識」「時間」「ケアレス」に分ける
模試の復習で大事なのが、「なぜ間違えたのか」を具体的にすること。
そのとき役に立つのが、ミスを次の3つに分類する方法です。
知識不足のミス
公式を知らなかった、単語がわからなかった、解き方自体がわからなかった、など。時間配分のミス
前半の難しい問題に時間をかけすぎて、後半の簡単な問題に手が回らなかった、など。ケアレスミス
問題の読み間違い、計算の写し間違い、符号の見落とし、マークのずれ、など。
●親子での会話例
「この問題は、どうして間違えちゃったと思う?」
「これは時間が足りなかった?それともやり方がわからなかった?」
「こういうケアレスミスを減らすには、どんな工夫ができそうかな?」
ポイントは、ミスを責めないこと。
「なんでこんなの間違えたの?」ではなく
「どうしてこうなったのか、一緒に原因を探してみよう」
というスタンスで話してあげると、お子さんは自分の弱点を“冷静な目”で見られるようになっていきます。
ミスの原因がわかれば、
知識不足 → 教科書・問題集で基礎の復習
時間ミス → 解く順番や時間配分の練習
ケアレス → 見直しの方法を工夫する
と、対策がとても具体的になります。
7.模試の結果を見せてもらうときの「NGワード」と「OKワード」
模試の成績表をお子さんが持ち帰ったとき、保護者の一言は本当に大きな影響があります。
●できれば避けたい言葉(NGワード)
「なんでこんな点数なの?」
「こんなんじゃ志望校なんて無理でしょ」
「前回より下がってるじゃない!」
気持ちは痛いほどわかるのですが、こうした言葉は
「もう見せたくない」
「どうせ怒られるだけだし…」
と、お子さんの心を閉ざしてしまう原因になります。
●最初にかけたい言葉(OKワード)
「お疲れさま、まずは最後までよく頑張ったね」
「受けるだけでも緊張したよね」
「結果見てどう思った?」
結果より先に「頑張ったこと」や「感想」を聞くことが、とても大事です。
そのあとで、
「この教科は前より上がってるね」
「ここはちょっと苦戦したんだね。どのあたりが難しかった?」
など、**“対話を引き出す言葉”**を意識してみてください。
成績表を見る時間を、
「ダメ出しの時間」ではなく
「一緒に現状を確認する時間」
に変えていくことが、模試の結果の見方でいちばん大事なポイントかもしれません。
8.家庭でできる「結果を責めないコミュニケーション」
模試の結果が悪いと、保護者の方も不安になりますよね。
だからこそ、つい感情的な言葉が出てしまうこともあると思います。
でも、受験期のお子さんは、
「このままじゃまずい」
「自分でもなんとかしなきゃ」
と、心の中ではだれよりも不安を抱えています。
そこにさらに、
「だから言ったでしょ」
「ちゃんとやってないからこうなるのよ」
と責める言葉が重なると、お子さんは
「どうせ自分はダメだ」と自己肯定感を失い、
「じゃあもういいや」と勉強からさらに遠ざかってしまうこともあります。
●模試の結果を“失敗”ではなく“情報”として扱う
家庭で意識していただきたいのは、
「模試=失敗か成功かを判断するテスト」ではなく
「模試=自分の今の状態を知るための情報」
という受け止め方です。
結果が悪かったときこそ、
「何がうまくいかなかったのか」
「次に変えられそうなところはどこか」
を一緒に整理できると、その模試が“成長のきっかけ”に変わります。
また、結果が良かったときも
「どうして今回はうまくいったと思う?」
「次も同じようにできるようにするには、何を続けたい?」
と振り返ることで、成功パターンを再現できる力がついてきます。
9.模試後1週間が勝負!「復習ゴールデンタイム」の使い方
模試の結果の見方と同じくらい大切なのが、
「模試を受けてから1週間の過ごし方」
です。
テストの内容を覚えているのは、だいたい1週間くらいまで。
この“ゴールデンタイム”にどれだけ復習できるかで、模試の価値が大きく変わります。
●1週間でやりたいこと
問題用紙を見ながら解き直し
特に間違えた問題・迷った問題を中心にやり直す。ミスの原因を書き出す
知識不足なのか、時間なのか、ケアレスなのかをノートにメモ。「次に同じ問題が出たらどう解くか」を決める
解き方・手順をはっきりさせておく。苦手単元の基本に戻って確認する
教科書や参考書で、「本当にわかっていなかったところ」をチェック。
●保護者にできるサポート
「復習しなさい!」と急かすのではなく、
「どのあたりが一番難しかった?」
「どこから復習すると良さそう?」
と、振り返りのきっかけになる質問を投げてみる。もしお子さんが話したがるタイプなら、
「この問題どうやって解こうとしたの?」と聞いて、
解き方を説明してもらうだけでも理解が深まります。間違えた問題だけを集めた“まちがいノート”を作るのもおすすめです。
「なぜ間違えたか」「次はどうするか」を一言でも書いておくと、“次につながる復習”になります。
10.模試の推移グラフで「がんばりの軌跡」を見える化
成績表に載っている“推移グラフ”も、模試の結果の見方としてぜひ活用したいポイントです。
●短期の上下より「長期の流れ」を見る
模試の偏差値や点数は、どうしても上下します。
たまたま難しい回だった
体調が悪かった
たまたま得意な分野が多く出た
など、1回だけの結果には“運”の要素も混ざっています。
大事なのは、
「ここ数ヶ月〜半年で、全体としてどう変化しているか」
「下がっても、そのあと戻せているか」
という“長期的な流れ”です。
●“右肩上がり”じゃなくてもOK
受験勉強は、必ずしもきれいな右肩上がりにはなりません。
一時的に成績が落ちる
新しい単元に入って点数が下がる
ことは、むしろ自然なことです。
保護者の方には、
「前より少し上がってるね」
「最近はこのラインで安定してきたね」
と、“プラスの変化”を見つけて言葉にしてあげてほしいと思います。
もし目標偏差値が決まっているなら、グラフに線を引いて
「ここまであと少しだね」
と“到達までの距離”を一緒に確認するのも、モチベーション維持につながります。
11.模試の結果から「次の行動計画」を一緒に決めよう
模試の結果の見方を理解したら、最後に必ずやってほしいのが、
「じゃあ、次の模試までに何をする?」
という“行動計画づくり”です。
●保護者が「決める」のではなく「引き出す」
ここで重要なのは、
親が一方的に計画を押しつけるのではなく
お子さん自身に考えてもらうこと
です。
たとえば、こんな質問を投げかけてみてください。
「どの教科から手をつけると良さそう?」
「今回の模試でいちばん気になったところはどこ?」
「次の模試までに“これだけはやる”って決めるとしたら何にする?」
お子さんが自分の言葉で
「じゃあ、数学の計算だけは毎日10分やる」
「英単語を1日20個だけやってみる」
などと言えたら、その時点で大きな一歩です。
●“完璧な計画”より“続けられる計画”
最初から完璧な勉強計画を立てる必要はありません。
むしろ、
頑張ればギリギリ続けられそう
ちょっと肩の力を抜いてもできそう
くらいの“ゆるめの計画”の方が、結果的に長続きします。
保護者の方は、
「できなかった日」を責めるのではなく
「できた日」を一緒に喜ぶ
というスタンスで見守ってあげてください。
12.家庭教師の活用もひとつの選択肢
「模試の結果の見方は何となくわかったけれど、
実際にどう勉強を進めたらいいか不安…」
そんなときは、家庭教師や個別指導の力を借りるのもひとつの方法です。
家庭教師なら、
模試の成績表を一緒に見ながら、弱点を分析
志望校の配点や出題傾向をふまえた対策
「どこから戻ればいいか」がわからない教科のやり直し
お子さんの性格・ペースに合わせた学習計画づくり
などを、マンツーマンでサポートできます。
特に、
「親が言うとどうしてもケンカになってしまう」
「何をどれくらいやればいいか、本人も保護者もわからない」
というご家庭にとっては、第三者の存在がクッションになってくれることも多いです。
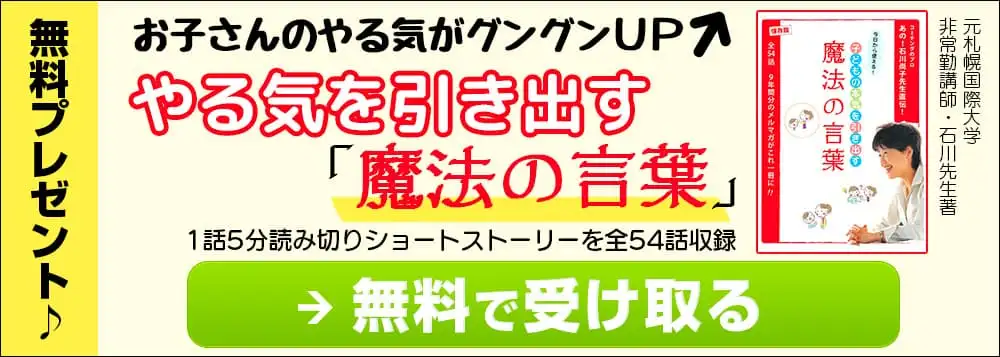
まとめ|模試の結果を「成長の材料」に変えよう
最後に、この記事でお伝えしてきた「模試の結果の見方・親ができること」をまとめます。
模試は「合否の判決」ではなく、「学力の健康診断」
偏差値や判定だけでなく、「教科別バランス」「正答率」「ミスの原因」を見る
苦手分野は「一番伸びしろが大きい場所」
ミスは「知識」「時間」「ケアレス」に分けて分析
成績表を見るときは、結果より先に「努力」を認める言葉を
模試後1週間は“復習ゴールデンタイム”
推移グラフで「長期の成長」を一緒に確認
最後は必ず「次の一歩」を親子で決める
必要に応じて、家庭教師や個別指導など第三者の力も活用する
模試の結果の見方を変えるだけで、お子さんの受験勉強はもっと前向きなものに変わります。
数字の上下だけにとらわれるのではなく、
「どこができるようになったか」
「どこをどう変えれば、次につながるか」
という視点で、親子で一緒に模試と向き合ってみてください。
その積み重ねが、きっと本番の入試での自信につながっていきます。
家庭教師のガンバ 今村