はじめに
こんにちは家庭教師のガンバのTです。私は医学部に通う現役大学生で、大学1年生のときからガンバで家庭教師をやっています。現在は体験のスタッフというお仕事で、これから家庭教師を始めたいと思っているご家庭を訪問し、体験授業をしています。体験授業を通じてさまざまな生徒とお話をしてきた経験や私自身の中学受験の経験に基づいて記事を書いていきます。
中学受験において、算数と国語は合否を大きく左右する最重要科目です。しかし、塾に通っていても「思うように成績が伸びない」「苦手意識が強い」と悩むご家庭も多いのではないでしょうか。
この記事では、中学受験を目指す受験生に向けて、算数・国語それぞれの効果的な勉強法や、成績アップにつながる具体的なアプローチを詳しくご紹介します。さらに、科目ごとの勉強を効果的に進めるための「学習計画の立て方」も解説。この記事を読むことで、学習の質と効率が格段が上がってくれたら嬉しいです。
1. 中学受験の算数|得点源に変えるための4ステップ勉強法
■ 算数の特徴:思考力・論理力を問う「積み上げ型」科目
算数は、単なる計算力ではなく、論理的な思考力や図形把握力、試行錯誤する力が求められます。また、苦手単元があるとその後の学習に大きな影響を与えるため、積み重ねが特に重要な科目です。
■ ステップ①:計算力を徹底的に鍛える
計算問題は、毎日のウォーミングアップとして取り組むべき基本。「早く・正確に」計算できる力は、すべての問題の土台となります。具体的には以下を意識しましょう。
- 毎日10~15分程度、計算練習をルーティン化
- 苦手な四則演算、分数や小数の計算などを重点的に
- 間違えた箇所はすぐに解き直し、「なぜミスしたのか」を分析
非常に重要なのですが、みんな軽視をしていますが計算ミスで失っている点数はかなり大きいのです。計算ミスを減らすだけでも、模試の得点は安定し始めます。
■ ステップ②:単元ごとの「理解」を深める
「速さ」「割合」「比」「場合の数」など、頻出単元をしっかり理解することが得点アップへの近道です。塾のテキストや問題集を使い、以下のようなサイクルで学習を進めましょう。
- 例題の理解 → 類題演習 → 練習問題で定着
- 解き方を「自分の言葉」でノートにまとめる
- 分からない部分は放置せず、必ず質問・復習する
難しい単元は、図や表を活用して可視化することで理解が深まります。
■ ステップ③:応用問題は「パターンの蓄積」が鍵
応用問題で差がつくのが中学受験。難しい問題に対しても、「どこかで見たことがある」と思えるようにするには、多くのパターンを経験することが不可欠です。
- 解き方の「型」を覚える(線分図・面積図・比の使い方など)
- 間違えた問題は、問題文・図・解き方をセットでノートに記録
- 自分の弱点が出やすい単元を重点的に反復練習
「なぜその式になるのか?」を毎回考える癖をつけることで、本質的な理解に結びつきます。
■ ステップ④:志望校に合わせた過去問演習
志望校の出題傾向を把握するためには、過去問演習が最も効果的です。6年生夏以降は本格的に取り組み、以下のように活用しましょう。
- 最初は時間無制限でじっくり解き、解法を確認
- 慣れてきたら制限時間内で解いて、時間配分の練習
- 1回で解けなかった問題は、数日後に再チャレンジ
単に解いて終わりではなく、「なぜ間違えたのか」「他の方法で解けないか」を振り返ることで、解く力の底上げが可能になります。
2. 中学受験の国語|波の出やすい科目を安定させる勉強法
■ 国語の特徴:感覚に頼らない「読解の技術」が求められる
国語は一見センスが必要な科目に思われがちですが、実は論理的な読み方と記述の型を身につけることで、誰でも得点を安定させられる科目です。
「本文から根拠を探し、論理的に答える」能力を鍛えるためには、以下のような学習が効果的です。
■ ステップ①:語彙力を日々積み重ねる
語彙力が不足していると、本文の意味を正確に理解できず、選択肢も誤る傾向があります。以下を習慣化しましょう。
- 漢字ドリルや語句問題集で、週に20語程度を目標に習得
- 四字熟語・ことわざカードなどでゲーム感覚で覚える
- 苦手な語句は、例文を自作して意味とセットで記憶する
語彙力=読解力の土台です。語句を制する者が国語を制します。
■ ステップ②:読解問題は「根拠を拾う」訓練が命
読解問題は、「なんとなく」ではなく本文から答えの根拠を見つける習慣が重要です。
- 指示語(それ・この・あの)や接続語に注目する
- 登場人物の気持ちや状況の変化を整理しながら読む
- 解答前に「本文中のどこに根拠があるか」を必ず確認
選択肢問題では、消去法や言い換えの視点も有効です。毎回の演習で解答へのプロセスを意識しましょう。
■ ステップ③:記述対策は「型」を覚えて訓練
中学受験では、50~100字程度の記述問題が出題される学校も多くあります。これもセンスではなく、以下のような「基本の型」を覚えることから始まります。
- 「登場人物の気持ち+その理由」の2点構成
- 「筆者の主張+具体例」の構成で論説文に対応
- 模範解答を写す練習 → 自分の言葉で書く訓練へ発展
制限時間内に書く力を養うため、書いたあとは必ず読み返す習慣も身につけましょう。
■ ステップ④:音読と要約で文章理解を深める
音読は、集中力・読解力・語彙力のすべてに効果的です。さらに、要約練習を取り入れることで文章構造の理解が深まります。
- 1日1本、物語文または論説文を声に出して読む
- 「この段落で何が言いたいか?」を自分の言葉でまとめる
- 要約は書かずに口頭で行うだけでも効果大
国語の力は一朝一夕には身につきません。地道な積み重ねこそが安定した得点力に結びつきます。
3. 算数・国語の成績を伸ばす「学習計画」の立て方
どんなに良い教材や塾に通っていても、日々の学習がバラバラで計画性がなければ、成績の伸びは限定的です。効果的な学習計画の立て方は、受験勉強を成功させる大きな鍵になります。
■ ポイント①:1週間単位でバランスよく計画する
中学受験生にとって、塾の宿題・学校の勉強・家庭学習のバランスをとるのは簡単ではありません。1日単位ではなく「1週間単位」で勉強スケジュールを組むことで無理なく学習が続けられます。
例)
- 月〜金は塾の復習+基本問題
- 土日は苦手分野の克服や応用問題・過去問演習
- 国語と算数を“セット”で毎日バランスよく配置
「火曜と金曜は国語多め」「日曜は算数の図形特訓」など、曜日ごとのテーマを決めるのも効果的です。
■ ポイント②:可視化することで「勉強の見通し」が立つ
学習計画は、頭の中だけでなく紙やスケジュール表で可視化することで、学習の見通しが立ち、モチベーションの維持にもつながります。
- 週間カレンダーや付箋を使って予定を見える化
- 勉強した内容を色分けして記録する(算数=青、国語=赤など)
- 達成したらチェックをつけることで達成感UP
計画通りにいかない日があっても問題ありません。「できなかったら翌日に回す」柔軟性を持ちつつ、続けることが大事です。
■ ポイント③:振り返りタイムで“学びを定着”させる
学習計画は立てて終わりではなく、週末に5分〜10分程度の振り返りタイムを設けることが効果的です。
- どの科目に時間をかけすぎたか?
- どこが理解できていないまま進んでいないか?
- 解き直しが必要な問題はどれか?
この振り返りを繰り返すことで、「勉強の質そのもの」を改善する視点が育ちます。
4. 志望校対策はいつから?科目別の「過去問」の取り入れ方
多くの受験生が最後に意識するのが過去問演習ですが、これを「直前期の総仕上げ」だけにせず、段階的に取り入れることで“戦略的な勉強”が可能になります。
■ 算数の過去問は「出題パターン分析」に使う
算数の過去問は、単に得点を見るだけでなく、「どの単元が出やすいか」を知るための分析ツールとして活用しましょう。
- 毎年のように出る単元(割合・場合の数・図形の応用など)を特定
- 出題形式(誘導付き・単問・記述)の傾向をチェック
- 解けなかった問題を「単元別に分類」して対策リスト化
頻出分野がわかれば、優先的に時間を割くべき単元が見えてきます。
■ 国語の過去問は「文章傾向」と「設問形式」に注目
国語の過去問では、出題される文章のタイプや設問形式が学校ごとに特徴的です。
- 物語文/論説文どちらが多いか
- 記述問題がどれくらいの割合を占めるか
- 選択肢問題の難易度やひっかけの傾向は?
過去問は最初から高得点を狙うのではなく、「志望校がどんな力を見ているか」を知ることが第一歩です。演習→分析→弱点対策という流れで活用することが重要です。
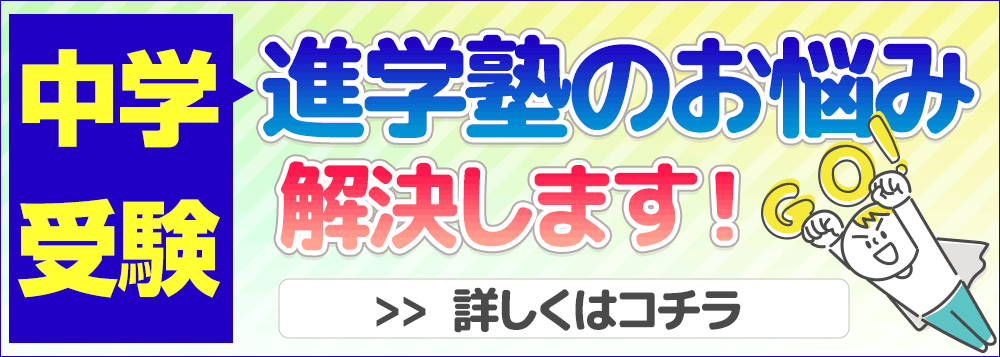
まとめ|中学受験の算数・国語を攻略するために、今すぐ始めるべきこと
中学受験の合否を左右する算数と国語の攻略には、ただ闇雲に問題を解くだけでは不十分です。「理解→反復→分析→改善」のサイクルを日々意識し、効率的に取り組むことが、成績アップの鍵になります。
本記事で紹介したように、
- 算数は「基礎力の徹底」「単元別理解」「応用問題対策」「過去問演習」の4ステップで段階的に力をつける
- 国語は「語彙・漢字」「読解技術の習得」「記述対策」「音読の習慣化」で安定した得点力を育てる
- 学習計画を立て、1週間単位で「継続できる仕組み」をつくることが、長期的な成果につながる
- 志望校の過去問を早い段階で分析し、科目ごとの出題傾向に沿った対策を行う
といった一連の流れを、戦略的に実践することが重要です。
中学受験は長期戦ですが、毎日の積み重ねが確実に力となります。「自分に合ったやり方」を見つけ、迷わず継続することが最大の合格対策です。
本記事を参考に、ぜひ今日から自分だけの勉強法と計画を見直してみてください。確かな土台があれば、志望校合格は決して夢ではありません。
家庭教師のガンバ T

