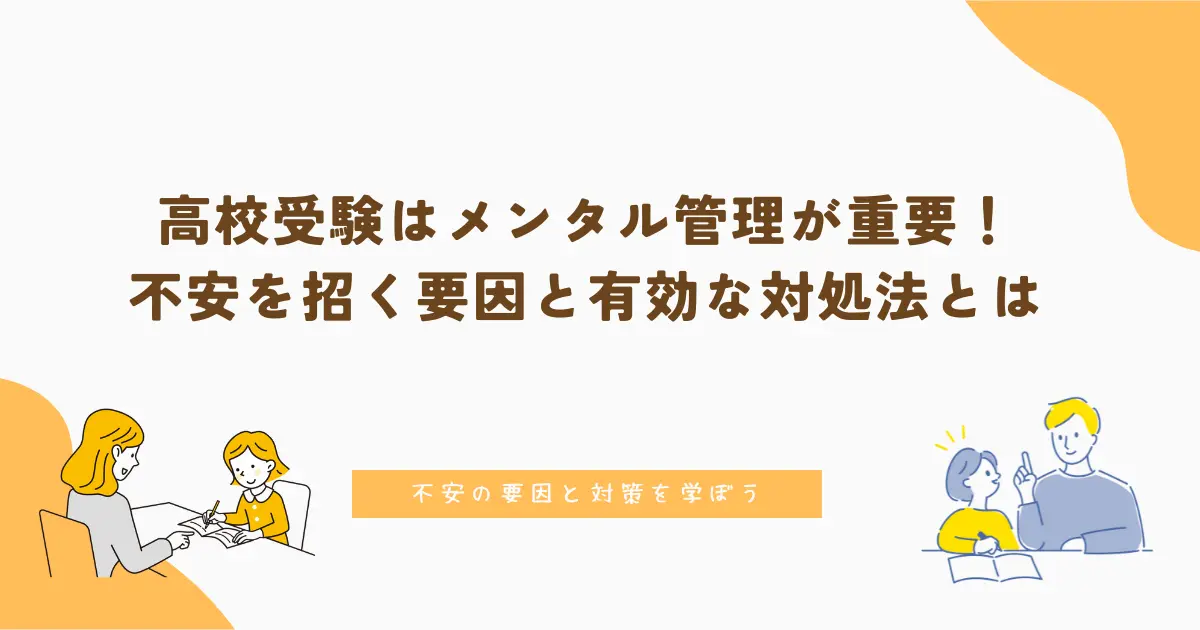高校受験は長期戦です。メンタル管理をしっかりと行い、万全の状態で臨まなければなりません。この記事では受験生と保護者様に向け、適切にメンタルを管理する方法を説明します。不調を招く要因や、生活習慣の中でメンタルを鍛えるコツなどをお伝えできれば嬉しいです。
高校受験に向け勉強を効果的に進めるには、メンタル管理が欠かせません。メンタルが不調だと、勉強が思うようにはかどらないだけでなく、やる気や熱意まで失ってしまうかも知れません。受験に初めて臨むお子さんも多いため、不安や焦りを感じるのは仕方がないことです。メンタルの悪化に適切に対処できるよう、不安を引き起こす要因と対策を学んでおきましょう。
高校受験生のメンタルが不安定になるよくある要因
「受験勉強を進めるほどメンタルが悪化する」
「受験が近づくほどに不安が大きくなる」
そんなお子さんは、メンタルが不安定になる要因を知る必要があります。中学生は多感な時期で、ただでさえ悩みや不安を抱えがちです。受験本番までメンタルを健康に保つのは容易ではありません。「頑張ればもやもやが解決する」と考え、闇雲に勉強をしても余計に悩みが深まる恐れもあります。まずは自分の状況を客観的に判断することが大切です。
勉強をしているのに成績が上がらない
勉強をしているのに成績が伸び悩むと焦りや不安が生じます。「先生の指導が悪い」と環境に要因を求めたり、「自分は無力だ」と思い込んだりと、後ろ向きな感情に飲み込まれがちです。周囲からは「努力不足だ」と判断され、責め立てられることもあるかも知れません。混乱した状態のまま、有効な対策も立てられずに受験勉強を続けることになってしまいます。
受験勉強の進め方が分からない
勉強の必要性は理解していても、何をどう始めるべきか分からないお子さんもいます。このタイプのお子さんは、評判の良い塾に通ったり、参考書を買い揃えても、思うように力がつかないことが多いと思います。試行錯誤するうちに時間が経ち、焦りばかりが募ります。成績が一向に伸びず、悩みが深まってしまいます。
理想と現実がかけ離れている
大きな理想を掲げている場合、それが原動力となり大きな成果を上げることもあります。ですが、逆に現実とのギャップに悩むこともあります。たとえば「将来は医者を目指したい」と考えているにもかかわらず、数学や理科の成績が悪ければ、どんどん自信を失くしてしまうかも知れません。「何としてでも夢を叶えたい」と思えば思うほど、焦りと不安に襲われます。先生や親から過度の期待をかけられ、プレッシャーがさらにメンタルを悪化させるケースもあります。
受験での失敗が怖い
受験での失敗を恐れ、日ごとに不安を募らせるお子さんもいます。自分の努力を否定される恐怖、合格へのプレッシャーは、勉強を進めるほどに増えるかもしれません。不安を覚えるのは自然なことではありますが、受験への恐怖が先に立ちすぎると、円滑に勉強を進められません。気持ちで負けてしまいます。
周りと比較し弱気になる
友だちと自分を比較し、弱気になるお子さんもいるかも知れません。特に肩を並べていた友だちがどんどん成績を伸ばし始めると、「自分だけがうまくいかない」と思い込み、メンタルが悪化する場合もあります。そして、勉強へのやる気を喪失する恐れもあります。
親も不安で口を出しすぎてしまう
必要以上に親が干渉することも、お子さんのメンタルに悪い影響を与えてしまうことがあります。中学生の心は思っている以上に繊細で複雑です。受験や勉強だけでなく、友人関係や部活動、自分の将来などさまざまな悩みを抱えています。アドバイスには相当に慎重にならないと、的を外す恐れもあります。単なる叱責と捉えられれば、お子さんは反発してしまうかも知れません。
高校受験に向けてメンタル管理を行う重要性
高校受験生に日々のメンタル管理が欠かせないのは、心を健康に保つためだけではありません。日々の勉強を円滑に進めるためにも、受験当日に平常心で試験に臨むためにも、強いメンタルが大切です。
メンタルが崩壊すると受験に間に合わない恐れがある
一般的に高校受験に向けた勉強が本格化するのは、部活動がひと段落つく中3の夏頃からというお子さんが多いと思います。受験生は、半年の勉強期間を「長い」と感じるかもしれません。でも、実際は半年という期間はあっという間です。
基礎を定着させ、応用力をつけ、受験に対応できる状態まで持っていくには、相応の時間が必要です。特に基礎学習に不安があるお子さんは、受験までのスケジューリングを綿密に行わなければ間に合わなくなってしまいます。
メンタルが崩れると、勉強に前向きに取り組めない期間が生じます。少しの遅れが合否を大きく左右することもあり得るので、強いメンタルを持ち、目の前の現実を一つひとつ乗り越えていく必要があります。
日頃のメンタル管理が試験当日にも活きる
日常的にメンタル管理ができているお子さんは、試験当日にも強さを発揮します。不安や焦りを乗り越え、平常心で試験に臨めるでしょう。本番は誰しも緊張します。普段の7〜8割の点数しか取れないお子さんも少なくありません。平常心で試験を受けられるメンタルがあれば、大きなアドバンテージになります。
高校受験生が上手にメンタル管理する方法
メンタルを不安定にさせる要因を把握したら、必要な対策を講じます。メンタル管理には絶対的な手法があるわけではありません。学校や塾に一般的な回答を求めるより、「今の状況ならどのような対策が必要か」を見出す姿勢が大切だと思います。学校や塾、家庭教師に対応をお願いするのはその後が理想です。本章を参考に、状況に合った対策を考えてみてください。
自分の学力を正しく把握することから始める
「勉強をしても成績が上がらない」「何から勉強するべきか分からない」というお子さんは、自分の学力を正しく把握するよう努めます。認識がずれてしまっていると、強化するべき内容を誤ったり、基礎が定着しないまま応用を進めたりと、成果に結びつきません。目の前のハードルをクリアできない状態が続きます。
学力を正確にはかるには、模試の活用がおすすめです。模試を受けることで、「学力の現在地」を把握できます。やるべきことが明確になり、もやもやした気持ちを払拭できるのではないでしょうか。
先生から自分にあった勉強のやり方を学ぶ
思うように成績が伸びないお子さんは、勉強のやり方が合っていない可能性があります。合わない勉強を続けても、効率や効果が上がりづらく、焦りが増えてしまいます。
たとえば視覚で物事を認識する傾向が強いお子さんには、文字ベースの論理的な勉強方法より、図表を多用した勉強方法の方が効果的である場合が多いです。闇雲に勉強を進めるより、自分に合った方法を見つけることが大切ではないでしょうか。
学校や塾の先生、家庭教師など、身近で相談できる人がいれば「どんな勉強法がいいのか?」のアドバイスをもらうのもひとつです。
短期目標を立て成功体験を重ねる
大きな理想を掲げ、現実とのギャップに悩んでいるお子さんは、短期目標の設定をおすすめします。将来の夢を長期目標とするなら、高校入試を中期目標、苦手分野の克服を短期目標に掲げるという感じです。実現可能な短期目標は、勉強のモチベーションに繋がります。一つひとつをクリアすることで、小さな成功体験を重ねることもでき、自信につながります。
短期目標のポイントは2つ。「頑張れば実現できること」「具体的であること」です。特に具体的であることは重要です。何をどう頑張るべきか分かれば、勉強に迷いが生じません。成功体験を重ねながら、一つひとつ夢に近づく自信を得られるはずです。
もやもやの原因を書き出し客観視する
自分に合った勉強法で努力しても不安が残る人は、不安の原因を紙に書き出してみましょう。書くことで自分の中に溜め込んだ気持ちが整理されます。
書き出す内容は、以下のとおりです。
①起こった出来事(例:成績が伸びない、友人においていかれそう)
②どのような感情を持ったか(例:悔しい、悲しい、どうすれば良いか分からない)
③出来事を体験した後の行動(例:やる気がなくなり、勉強をやめた)
④本当はどうしたいか(例:受験を早く終わらせたい)
現実をありのままに書き出し客観視するのは「セルフモニタリング」と呼ばれ、認知行動療法などの心理療法でも用いられている手法です。多くのお子さんは、書くことで落ち着きを取り戻せます。
自分を客観視できるようになったら、変えられない現実には無理に歯向かおうとせず、変えられる物事に意識を集中すると効果的です。できる行動を続けることで、心が晴れていきます。
「受験は通過点」と認識する
受験での失敗を過度に恐れるお子さんは、高校受験を絶対視しすぎているかもしれません。高校受験の先には進学や就職があり、その先に目指す未来があります。「高校受験に失敗したら終わり」ではないのです。
もちろん、志望校に強いこだわりを持つことは悪いことではありません。でも、それで心が苦しくなるのなら、「受験は通過点」という意識を強く持つ方が賢明です。
自分は自分と割り切って考える
他人と比較し憂鬱になるお子さんは「自分は自分」と割り切って考えましょう。当然、お子さん一人ひとりの段階や状況が違うため、成績が伸びる速度にも違いが生じます。少しずつでも勉強が進んでいれば、他人と比較することはあまり得策ではないと思います。
周囲の大人が一人ひとりが自分らしく頑張れるよう、背中を押してあげられれば、お子さんにとって心強いのではないでしょうか。
親は「見守る」と「ねぎらう」が基本
親が成績や勉強方法に口出ししすぎないことも重要ではないでしょうか。親の側が焦ってしまうと、お子さんの不安は増すばかりです。お子さんと先生を信頼し、見守りに徹することも大切だと思います。ただし、「見守っている」事実が伝わるよう、適度な距離感を保つことも忘れないようにしてください。親がお子さんに関心を持ち味方でいることが伝われば、お子さんは安心して自分の道を進めるはずです。
お子さんの成績が上がったり、学習意欲が向上するなどのプラスの変化を実感した際には、忘れずにねぎらってあげてください。お子さんはより強く成功を実感し自信を深めていけると思います。
高校受験生のメンタル管理におすすめの生活習慣
最後にメンタル管理に効果的な生活習慣をご紹介します。生活リズムのずれは、心身に重大な影響を及ぼすと言われます。生活習慣を乱してまで勉強を頑張ると、かえって逆効果になるのです。「早寝早起き」「朝食」「適度な運動」などの生活習慣が、メンタルヘルスと強く結びつくことを実感しましょう。
休日や長期休暇中も早寝早起きを心がける
メンタルヘルスには「セロトニン」という神経伝達物質が大きく影響します。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、心を安定させ、意欲や集中力の低下を防ぐ機能があります。「朝は明るく夜は暗く」という規則正しい刺激が、セロトニンの生成を促します。十分な睡眠をとり、朝の光を浴びて起きる生活が大切です。
受験生は夜遅くまで勉強を進めがちです。でも心の健康を考えるなら、規則正しい生活こそが重要ではないでしょうか。
朝食は脳の活性化に役立つ
朝食も軽視できません。メンタルヘルスに重要な役割を果たすセロトニンの分泌を促すだけでなく、学習効率を上げる効果も期待できます。
文部科学省が全国の中学3年生を対象に行った調査によると、朝食を食べている生徒ほど、国語・数学・英語の学力が高い傾向があります。特に国語は朝食を毎日食べている生徒と、そうでない生徒との間に大きな差が生じています。
学習には多くのエネルギーを使います。朝食で脳を活性化させることで、勉強にエネルギーを存分に使えるようになるのです。メンタルが不調なときほど、朝食で勉強に向かう姿勢をつくることが肝心ではないでしょうか。
(参照:2.質問紙調査の結果 | 文部科学省)
長期休み中も軽い運動を欠かさない
セロトニンの分泌には適度な運動も必須です。特にウォーキングやリズム運動は良い刺激になります。セロトニンの分泌は20〜30分程度でピークに達すると言われています。勉強の息抜きに体を動かす意識を持つと良いと思います。
長期休暇中は体をほとんど動かさず、勉強漬けになってしまいがちです。過度に運動する必要はないものの、必要最低限の運動を続けましょう。
(参照:vol.113「リズム運動」でメンタル強化を | OMRON)
リフレッシュタイムを設ける
勉強の合間にリフレッシュタイムを設けるのもおすすめです。一般的に集中力が持続できるのは90分程度と言われています。勉強の成果を実感するためにも、適度な休憩は欠かせません。
リフレッシュ中は音楽を聴いても、ゲームをしても良いと思いますが、時間を取られ過ぎたり、集中が切れて勉強に戻れないようでは本末転倒になってしまいます。「ストーリー性のあるゲームはやらない」「テレビは見ない」などのルールを設け、時間を区切ることが大切です。
まとめ〜メンタル管理で受験を乗り切ろう
<高校受験生が上手にメンタル管理する方法>
・模試を受け、自分の学力を正しく把握する
・自分に合った勉強法を学ぶ
・頑張れば実現できること、具体的な指針を得られることを短期目標に設定し、成功体験を重ねる
・もやもやの原因を書き出し客観視した上で、変えられる現実に注力する
・「受験は通過点」と認識し、失敗を過度に怖がらない
・「自分は自分で良い」と認識し、友達と比較しない
・親は「見守る」&「ねぎらう」が基本
これらを心がけることで、成績の伸び悩みを解消し、受験まで計画的に勉強を進められるようになることが期待できます。
高校受験で培ったメンタル管理の技術は、大学受験、社会人生活でも役立ちます。「将来の財産になる」と考え、しっかりと向き合うのも良いのではないでしょうか。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。
また、受験対策をはじめとした、お子さんと保護者の方に役立つ様々な情報を発信しています。ご興味のある方はぜひ、ご参考にしてください。
家庭教師のガンバ 編集チーム ありま
こんにちは。家庭教師のガンバ編集チームです。日々の勉強やテスト、受験、不登校などのお悩みに役立つ情報を発信しています。