こんにちは家庭教師のガンバのTです。私は医学部に通う現役大学生で、大学1年生のときからガンバで家庭教師をやっています。現在は体験のスタッフをやっていて、これから家庭教師を始めたいと思っているご家庭を訪問し、体験授業をしています。体験授業を通じてさまざまな生徒とお話をしてきた経験や私自身の中学受験の経験に基づいて記事を書いていきます。
中学受験に臨む保護者の皆様、そして受験生の皆さん。
いよいよ正念場、お子さんの「過去問」対策は進んでいらっしゃいますか?
「志望校の過去問、もう3年分解かせてみました」
「丸付けして、点数も出して、苦手な単元もなんとなく分かっています」
素晴らしいスタートです。
ですが、もしその演習が「解かせて、丸付けして、点数を見て一喜一憂して終わり」になっているとしたら…それは過去問の力を30%も引き出せていないかもしれません!
中学受験における過去問は、志望校合格への「最強の教材」であると同時に、学校からの「ラブレター」とも言えるメッセージです。
なんとなく解くだけでは、せっかくの宝の地図を眺めているだけになってしまいます。
この記事では、家庭教師のガンバが多くのご家庭と共に実践してきた「過去問を120%活用し尽くす」ための、効果的な解き方と、合格をグッと引き寄せる「復習法」を徹底的に解説します。
なぜ過去問は「最強の教材」なのか?
「過去問が大事なのはわかっている」という方も、まずはその理由を深掘りさせてください。この「なぜ」をご家庭で共有できているかで、活用の質が大きく変わります。
1. 志望校の「傾向」と「クセ」がわかる
中学受験の入試問題は、学校側が「こういう力を持ったお子さんに来てほしい」という明確なメッセージを込めて作っています。
- 「計算力より、思考のプロセスを言葉で説明できる子が欲しい」(=記述・作図問題が多い)
- 「幅広い知識を素早く正確に処理できる子が欲しい」(=問題数は多いが、一つひとつは基礎的)
- 「この分野(例:速さ、時事問題)だけは、毎年必ず出題しますよ」(=超頻出単元)
これらは、塾のテキストや模試だけでは見えてこない、その学校だけの「クセ」です。
過去問は、そのクセを知るための唯一の「公式ガイドブック」なのです。
2. お子さんの「現在地」と「課題」が明確になる
過去問を解くと、「合格者平均点」や「合格最低点」と自分の点数との差が、シビアな「点数」として現れます。
「合格最低点まで、あと40点も足りない…」
ショックを受けるかもしれません。しかし、それは「絶望」ではなく「希望」です。
なぜなら、「本番までに何をすれば、その40点を上乗せできるか」が具体的にわかるからです。
- 「大問1の計算ミスだけで12点も落としている」
- 「国語の長文読解に時間をかけすぎて、最後の知識問題が手付かずだ」
- 「理科は『てこ』の計算が全滅している」
このように、お子さんの課題が「分野」や「問題形式」で浮き彫りになります。これがわかれば、あとはその穴を埋めるだけ。やみくもに塾の宿題をこなす状態から、「弱点克服」という明確な目的を持った勉強にシフトできます。
3. 本番の「時間配分」をシミュレーションできる
中学受験は、小学生にとって非常にシビアな「時間との戦い」です。
「時間が足りなくて、解けるはずの問題を落とした」
これが受験で一番悔しい負け方です。
過去問演習は、本番と全く同じ制限時間で戦う「予行演習(リハーサル)」です。
- 大問1(計算や知識)には何分かけるか?
- 難問にぶつかった時、何分で見切りをつけて次に進むか?
- 見直しの時間は何分確保するか?
この「時間戦略」を体にしみこませる最高の練習が、過去問演習なのです。
【実践編】合格を掴む!過去問の「解き方」5ステップ
さあ、いよいよ過去問を解きます。
ただ解くのではありません。「本番力」を鍛えるため、ご家庭で以下の環境を整えてあげてください。
ステップ1:環境を「本番」にする(保護者の役割)
- 時間を計る:スマホのタイマーではなく、試験会場に持ち込める「腕時計」や「キッチンタイマー」を使います。
- 場所を整える:机の上には筆記用具、消しゴム、問題、解答用紙(できれば拡大コピー)、時計以外は何も置かない。
- 邪魔を入れない:ここが保護者の方の腕の見せ所です。「過去問を解いている50分間」は、他のご家族も静かにする、電話も取らないなど、本番さながらの緊張感を作ります。
ステップ2:時間を「厳守」する
「あと5分あれば解けたのに…」とお子さんが言っても、時間を延長してはいけません。
アラームが鳴ったら、たとえ解いている途中でも、絶対に鉛筆を置かせます。
「時間内に解き切るプレッシャー」の中で解くことこそが、最大の練習です。
ステップ3:「解ける問題」から手をつける
中学受験は満点を取る必要はありません。「合格最低点」を超えれば勝ちです。
難しい問題(いわゆる「捨て問」)に時間を使いすぎて、簡単な問題を落とすのが最悪のパターン。
問題全体をざっと見渡し、「これは確実に取れる」という問題から手をつける練習をしましょう。
ステップ4:迷った問題には「△」をつける
これが後で「120%活用」するための最重要テクニックです。
解いている最中に、
- 「自信はないけど、たぶん(ウ)かな…」
「この公式で合ってると思うけど、ちょっと不安…」
と感じた問題の番号に、大きく「△」マークをつけるよう、お子さんに徹底させてください。
ステップ5:最後まで諦めない
ステップ2(時間厳守)と矛盾するようですが、これは「精神論」です。
途中で「あ、これ絶対無理だ」と心が折れて、残りの時間を惰性で過ごすのが一番もったいない。
本番では、最後の1秒まで「1点でも多く取る!」という執着心が合否を分けます。そのメンタルトレーニングも過去問演習のうちです。
解きっぱなしはNG!「復習法」こそが合格の鍵
お疲れ様でした!お子さんは全力を出し切りました。
…でも、本当の勝負はここからです。過去問は「解いた時間」の3倍の時間を「復習」にかけるつもりでいてください。
合格するご家庭は、例外なくこの「復習」を徹底しています。
そして、ここが保護者の方の最大のサポートポイントです。
小学生が一人で完璧な分析と復習をするのは不可能です。ぜひ、親子で一緒に取り組んでください。
ステップ1:すぐに丸付け(採点)
記憶が新しいうちに、すぐに丸付けをします。
この時、ステップ4でつけた「△」マークが超重要です。
採点結果を、以下の3種類に分類しましょう。
1. ◎(完璧):自信を持って正解した問題
2. △(まぐれ):迷った(△をつけた)が、結果的に合っていた問題
3. ×(間違い):間違えた問題
ステップ2:徹底的な「解き直し」
次に、「△」と「×」がついた問題を、解説を一切見ずに、もう一度自力で解き直させます。
- なぜ間違えたのか?
- なぜ迷ったのか?
時間をかけて、じっくり考え抜く。ここで「うーん、やっぱりわからない!」とお子さんが頭を抱える経験が、脳に知識を定着させます。
ステップ3:3種類の「なぜ」で親子で分析する
自力で解き直してもわからなかった問題や、「△(まぐれ)」だった問題について、ようやく解説を読みます。
そして、お子さんと一緒に、「なぜ」間違えた(または迷った)のかを、徹底的に分析します。この『対話』こそが、過去問演習の心臓部です。
間違いの原因は、大きく分けて以下の3つです。
1. ケアレスミス(不注意)
2. 知識不足(わからなかった)
3. 時間不足(解き方が遅い・戦略ミス)
ステップ4:原因別の「対策」を立てる
分析して終わりではありません。次への「対策」を親子で決めます。
1. 「ケアレスミス」の撲滅法
「次から気をつける」という精神論だけでは、ケアレスミスはなくなりません。
- ミスの「見える化」:「+と−を書き間違えた」「問題文の『正しくないもの』を読み飛ばした」など、ミスの内容を具体的に書き出します。
- ミスの「パターン化」:保護者の方が、お子さんがどんなミスをしやすいか、パターンを一緒に見つけてあげましょう。(例:繰り上がりの計算、単位の書き忘れが多い、など)
- 対策:計算問題は必ず「見直し」の時間を取る、問題文の「~でないものを選べ」には必ず線を引く、など具体的な「行動ルール」を決めます。
2. 「知識不足」の克服法
これはシンプルです。「穴」を埋めましょう。
- 対策:間違えた単元のページに、塾のテキストや参考書で戻ります。
- 例:「不定詞の使い方がわからなかった」→ 塾のテキストの不定詞のページをもう一度読み、基本問題を解き直す。
- 重要:過去問で出た「関連知識」も一緒に復習すると効果倍増です。(例:不定詞と動名詞の違いも確認しておく)
3. 「時間不足」の解決法
これは「戦略」の問題です。
- 対策:なぜ時間が足りなかったのかを分析します。
- 例1:「大問1の計算に時間をかけすぎた」→ 毎朝、塾の計算ドリルを時間を計って解き、スピードを上げる。
- 例2:「難しい問題にこだわりすぎた」→ 次回から「1問3分悩んだら、印をつけて飛ばす」という『親子で決めたルール』を徹底しましょう。
過去問活用を120%にする「過去問ノート」
この徹底的な復習を「未来のお子さん」のために残すのが「過去問ノート」です。
このノート作りも、ぜひ保護者の方がサポートしてあげてください。お子さんが分析した内容を、親御さんが書き留めてあげる形でも構いません。
ノートに何をまとめるか?
ルーズリーフや専用のノートを用意し、年度ごと・教科ごとにまとめます。
1. 日付・教科・年度・点数(素点)・合格最低点・合格者平均点
2. 分類(◎・△・×)した結果の集計
3. 「×」と「△」の問題のコピーを貼り付け
4. 【最重要】間違えた「原因」の分析(例:ケアレスミス、知識不足など)
5. 【最重要】正しい解き方・考え方(解説の丸写しではなく、自分の言葉でまとめる)
6. 次回への「対策」(例:大問3を先に解く、てこの復習をする)
このノートが、入試直前期に「お子さんだけの最強の参考書」になります。
過去問は何周も解くべき?
よく「過去問は3周しろ」と言われますが、ガンバは「量より質」だと考えています。
- 1周目:時間を計って解き、徹底的に復習する(上記の流れ)
- 2周目:1周目で「×」「△」がついた問題だけを解き直す。ここで「◎」にできるか確認する。
- 3周目:(入試直前期に)もう一度、全問解き直す。時間配分の最終確認。
ただ3回解くのではなく、「できなかった問題を、できるようにする」ために周回することが大切です。
過去問が難しすぎて解けない…そんな時の対処法
小6の秋に初めて過去問を解いた時、点数があまりに低く、お子さんだけでなく、保護者の方まで心が折れてしまうことがあります。
でも、焦らないでください!それが普通です。
模試とは全く違う「クセ」のある問題に、最初は戸惑うものです。
大切なのは、その「現実」から目をそらさないこと。
基礎に戻る勇気を親子で持つ
「志望校のレベルに、今の基礎力が全く追いついていない」
それがわかっただけでも、大きな収穫です。
過去問演習を一旦ストップし、「塾のテキストの基本問題レベルに戻る」勇気を親子で持ってください。
一見遠回りに見えますが、過去問で浮き彫りになった「穴」だらけの単元をもう一度やり直すことこそが、合格への一番の近道です。
家庭教師のガンバがサポートできること
とはいえ、「うちの子の弱点がどこか、うまく分析できない」
「どうやって復習の計画を立てればいいかわからない」
「難しすぎて、親が叱ってしまい、親子関係が悪化しそう…」
…ご家庭だけで過去問と向き合うのは、本当に大変なことです。
私たち家庭教師のガンバは、勉強を教えるだけでなく、「勉強のやり方」を教え、親子間のコミュニケーションをサポートするプロです。
- 「お子さんのミスの傾向は、ここですね。だから、こういうルールで解いてみましょう」
- 「この問題が解けないのは、5年生のあの単元が抜けている証拠。そこだけ集中的に復習しましょう」
- 「点数が悪くても大丈夫です。お母さん。本番までに、あと〇点と〇点をここで取れるように作戦を立てましょう」
一人ひとりの「現在地」と「目標」に合わせて、過去問の分析と対策を一緒に考え、伴走します。
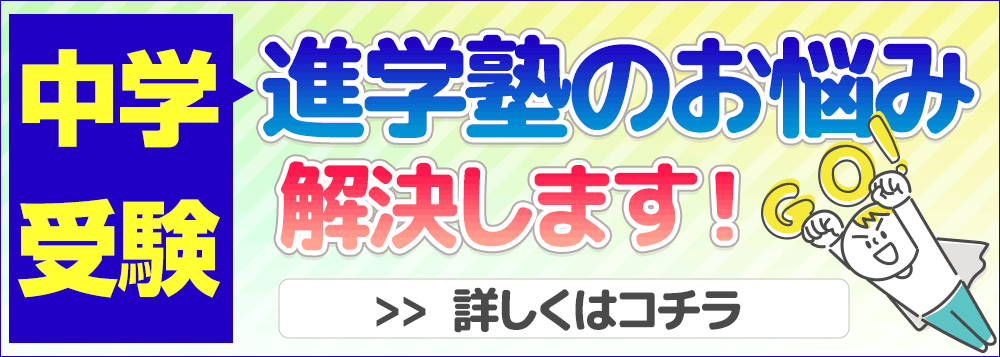
まとめ:過去問は「未来の合格」への羅針盤
過去問は、解いて点数を見て一喜一憂するためのものではありません。
それは、志望校が「こんな準備をしてきてね」と教えてくれる「ご家庭への羅針盤」です。
1. 本番の環境で解き(ステップ1~5)
2. 親子で徹底的に分析し(復習ステップ1~3)
3. 対策を立てて実行する(復習ステップ4)
このサイクルを回し続ければ、過去問は「解けなかった問題」から「確実に得点できる問題」へと変わっていきます。
もし、過去問の活用法に迷ったり、お子さんへの声掛けに悩んだりしたら、いつでも家庭教師のガンバに相談してください。
一人一人に沿った「合格プラン」を一緒に見つけましょう!
家庭教師のガンバ T

