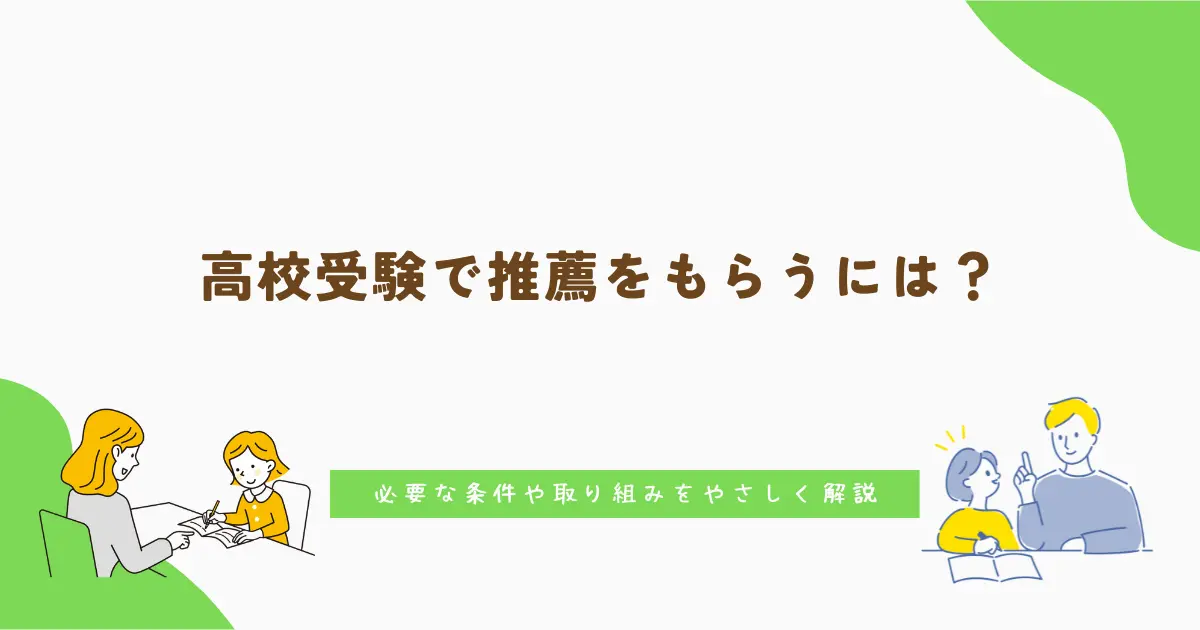「できれば推薦で高校に進学したいな」そう思っている中学生は少なくないと思います。
推薦入試は、それまでの学校生活や努力をしっかり評価してもらえる制度です。中には学力試験を受けずに合格できる場合もあり、大きな魅力がありますよね。
でも、実は誰でも推薦を受けられるわけではありません。学校生活の成績や部活動での実績など、各高校が定める基準を満たしている必要があります。ちょっと厳しい面もあるんです。
そこで今回は、中学生のみなさん、そして保護者の方に向けて、
・推薦をもらうための条件
・推薦を受けるために日ごろから意識したいこと
・推薦入試の流れ
を順番に解説していきます。「推薦をもらいやすい人ってどんなタイプ?」というヒントもお伝えしますので、今のうちからどんな行動をしておくといいかが見えてくると思います。
公立高校・私立高校それぞれの推薦制度についても触れていきますので、受験プランを立てる参考にしてください。
【公立高校】高校受験における推薦入試の種類
まずは、公立高校でよく行われている推薦入試のパターンを確認してみましょう。
面接や小論文で合否が決まる「一般推薦」
一般推薦は、調査書(内申書)・面接・小論文(作文) の3つを総合的に判断して合否が決まる方式です。それぞれの成績を点数化し、合計点で合否を判断します。
調査書(内申書)
調査書は、成績や部活動の記録、出欠の様子など、中学校生活の記録をまとめた大切な書類です。特に推薦では、内申点と出欠記録が重視されます。「普段からコツコツ頑張ってきた姿勢」が評価につながります。
面接
面接では、高校でどんな学校生活を送りたいか、中学校でどんな努力をしてきたかなどを聞かれます。先生方は「その子の人柄」や「学校に合うかどうか」を知りたいと考えているんです。
小論文(作文)
小論文では、物事を自分なりに考えて、筋道を立てて表現する力が問われます。テーマは学校によってさまざま。環境問題や教育についてだったり、理数系の課題だったりと幅広いです。日ごろから社会のニュースに目を向け、自分の意見をもつ習慣をつけておくと役立ちます。
部活などの実績を重視する「文化・スポーツ等特別推薦」
「文化・スポーツ等特別推薦」は、部活動や課外活動で優れた実績を残した生徒が対象です。ただし、すべての部活が対象になるわけではなく、その高校が力を入れている部活動に限られます。
試験では実技が行われることも多く、その分野での力を直接評価されます。進学後は、その部活動に所属することが条件になる場合が多いので、しっかり確認しておきましょう。
公立推薦入試の共通ポイント
公立高校の推薦入試を受けるには、中学校長の推薦書が必要です。さらに、合格したら必ずその高校に進学することになります。つまり、推薦を受けられるのは「第一志望の高校だけ」なんです。
試験は一般入試よりも1か月ほど早く行われますが、「とりあえず受けて安心しておきたい」という理由では利用できません。
また、公立の推薦は倍率が高いことが多く、必ずしも合格できるとは限りません。特に一般推薦は人気が集中するため、かなり狭き門になることもあります。
地域によっては、そもそも推薦制度がないところもあるので、早めに確認しておきましょう。
【私立高校】高校受験における推薦入試の種類
続いて、私立高校の推薦入試について見ていきましょう。
第一志望の学校だけに絞る「専願(単願)推薦」
専願推薦(単願推薦)は、その高校を第一志望と決めて「合格したら必ず入学します」と約束して受ける方式です。ほかの公立・私立は受験できなくなるので、覚悟を持って選ぶ必要があります。
その代わり、試験は調査書と面接が中心で、合格しやすい傾向があります。
また、学校によっては「部活動での実績がある生徒向けの特別推薦枠」を設けている場合もあります。高校側からスカウトを受けるケースもあり、その際は実技試験や面接を通して力が確認されます。
他校も受験できる「併願推薦」
併願推薦は、私立高校の推薦を受けながら、他の学校も受験できる方式です。合格しても必ず進学しなければならないわけではなく、最終的な進学先を選べます。多くの受験生が、
「私立の併願推薦で合格を確保 → 公立高校に挑戦」
という流れをとっています。合格校があると、精神的にも安心して本命に挑めますね。試験は調査書と面接が一般的で、公立の一般推薦に比べると受かりやすい傾向があります。
私立推薦入試の共通ポイント
私立の場合も、中学校長の推薦書が必要です。さらに高校との「入試相談」で合格可能性があらかじめ伝えられることも多く、高校が求める基準に達していないと推薦自体がもらえないケースもあります。ただし、一度推薦をもらえれば合格可能性は高くなります。
なお、推薦に必要な内申点は「専願」と「併願」で異なり、併願の方が高めに設定されるのが一般的です。
高校受験で推薦をもらうための条件
「推薦を受けたい!」と思ったら、まずはクリアしなければならない条件があります。どんなに学力が高くても、この条件を満たさなければ推薦はもらえません。
<一般推薦>
・高校が指定する以上の内申点(評定平均)
・欠席日数が基準以内であること
<特別推薦(部活動など)>
上の条件に加えて、部活動や課外活動での目立った実績
この3つが基本になります。
内申点(評定平均)
内申点は通知表の成績から算出されます。自治体によっては1〜3年すべてを対象にしたり、3年生だけを見る場合もあります。
成績は「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習する態度」の3つで評価されるので、テストの点数だけでなく、授業態度や提出物も大切なんです。
欠席日数
「3年間で10日以内」など、高校ごとに基準があります。インフルエンザなどの出席停止扱いや公欠は含まれませんが、普段から元気に登校できるかどうかが見られます。
部活動や課外活動での実績
特別推薦を狙う場合は、大会での成績や活躍が必要です。例として「県大会ベスト8」「地方大会出場」などが挙げられます。推薦枠がある部活動は高校によって違うので、希望校を早めに確認しておくと安心です。
高校受験で推薦をもらいやすい生徒の特徴とは?
条件をふまえると、次のようなタイプのお子さんが推薦をもらいやすいと言えます。
・定期テストで安定して良い成績をキープしている
・欠席がほとんどなく、生活リズムが安定している
・部活動で実績を残している、または中心となって頑張ってきた
ちなみに、部活動では必ずしもキャプテンやエースである必要はありません。チームの一員としてしっかり活動してきた実績も評価されるんです。
推薦をもらうために大切にしたい日々のポイント
推薦を得るためには、特別なことよりも「日々の学校生活を丁寧に積み重ねること」が一番の近道です。
授業を大切にして、復習を習慣にする
評定は定期テストだけでなく、授業態度やレポートも評価対象です。授業後に少し復習するだけで理解が深まり、「主体的に取り組む姿勢」として見てもらえます。 復習は基礎固めになるので、定期テストでの高得点にも繋がります。
提出物は期限を守る
提出物をきちんと出すことは、大きな評価ポイントです。特にレポートは「思考・判断・表現」の評価に直結するので、丁寧に取り組んでみましょう。
健康管理を意識する
欠席が多いと不利になるため、規則正しい生活を心がけることも大切です。部活引退後は運動不足になりやすいので、軽い運動やストレッチを習慣にすると体調を保ちやすいと思います。
推薦入試の流れを3つのステップで解説!
「推薦入試を受けたい!」と思ったら、最初にやることは学校にその気持ちをしっかり伝えることです。ここでは、推薦をお願いしてから実際にもらうまでの流れを、3つのステップでご紹介します。
①三者面談で推薦を希望する気持ちを伝える
まずは二学期の三者面談で、担任の先生に推薦を受けたいことを伝えましょう。そのために、夏休みまでに気になる高校をいくつか調べておくと安心です。推薦制度についても確認しておき、志望校を決めてから面談に臨むのがおすすめです。面談では、
・どの高校を、どんな形で受験したいのか
・一般入試を含めた全体の受験プラン
をはっきり伝えることが大切です。希望が受理されると、校長先生を交えた校内での協議に進みます。
②私立高校では「入試相談」があることも
私立高校では、中学と高校の先生の間で「入試相談」と呼ばれるやり取りが行われることがあります。これは、高校に受験予定者のリストを渡し、内申点や欠席日数などをもとに「合格の可能性」を見てもらう仕組みです。
ここでの判断が、推薦を出してもらえるかどうかに直結するため、とても大事なステップになります。
③担任の先生からの通知で推薦が決定
校内での話し合いが終わると、担任の先生から結果が伝えられます。推薦をもらえることになったら、いよいよ面接や小論文の練習に入ります。
推薦が難しいと判断された場合は、他の学校への変更や一般入試への切り替えを勧められることもあります。そのときは落ち込まず、親御さんや先生と一緒に改めて計画を立て直しましょう。
中学校から推薦をもらったら取り組むべきこと
無事に推薦が決まると「面接や小論文って、どう準備すればいいの?」と不安になりますよね。推薦入試は一般入試よりも早い時期に行われるので、効率よく対策していきましょう。
志望動機や高校でやりたいことをはっきりさせる
面接では必ずと言っていいほど聞かれるポイントがあります。
・志望動機(なぜその高校を選んだのか)
・高校で頑張りたいこと
・将来の進路や夢
・中学校生活で得られたこと
特に「志望動機」と「高校で頑張りたいこと」は欠かせません。まずは自分の気持ちを紙に書き出し、そこから整理していくと答えやすくなります。内容は学校や塾・家庭教師の先生に確認してもらうと安心です。
緊張しても話せるように練習する
入試本番では、誰でも緊張するものです。でも、緊張の中でも伝えたいことをしっかり話せるよう、練習を重ねましょう。
おすすめは、できるだけ多くの大人に面接の練習相手になってもらうこと。普段話したことのない大人(あまり関わりのない先生など)と練習すると、本番に近い緊張感が味わえます。
面接では答えを丸暗記する必要はありません。「話す方向性」だけを覚えて、自然に話せる状態を目指しましょう。
小論文は過去問を解いて添削してもらう
小論文は、過去問を研究するのが一番の対策です。公立高校なら教育委員会や学校のホームページで公開されていることもあります。
解いた後は必ず先生に見てもらいましょう。自分ではしっかり書けたつもりでも、他の人から見ると矛盾や不足があることが多いからです。客観的な意見をもらうことが、上達の近道です。
さいごに|推薦をうまく活用して受験を有利に
推薦入試には、
・一般入試より時期が早い
・面接や小論文だけで受けられることが多い
といったメリットがあります。例えば「私立の合格を早めに確保して、安心した状態で本命の公立に挑戦!」という作戦も立てられます。
ただし、内申点や欠席日数といった条件があるため、必ずしも誰もが挑戦できるわけではありません。もし条件が厳しいようであれば、推薦だけにこだわらず、一般入試に向けて準備するのも大切な選択です。
推薦は、あくまで「受験の選択肢のひとつ」。お子さんに合った方法を、先生やご家族と相談しながら選んでいきましょう。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。
また、受験対策をはじめとした、お子さんと保護者の方に役立つ様々な情報を発信しています。ご興味のある方はぜひ、ご参考にしてください。