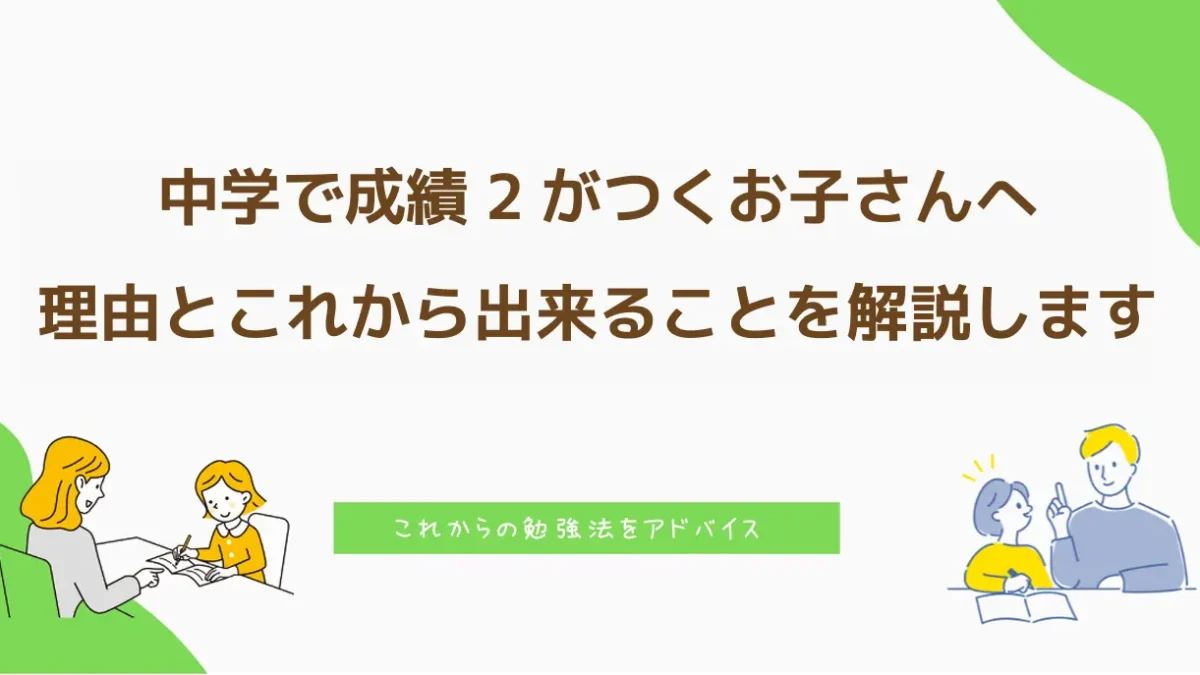「えっ、通知表に“2”がついてる…」
そんなふうに驚いたり、落ち込んだりしている中学生はいませんか?友だちが「オール3だった〜」と言っている中で、自分だけ2があると、すごく不安になりますよね。
「なんで2がついたんだろう……」「このままじゃ高校に行けないのかな」って、モヤモヤする気持ちも、とてもよくわかります。
でも、成績2がついたからといって「終わり」ではありません。今からだって、評価はしっかり変えられるし、自分のがんばりで未来を明るくすることができます。
この記事では、どうして「2」がついてしまうのか、その理由をやさしく説明します。これからどうすればいいかを、一緒に考えていきましょう!
成績2ってどうやって決まるの?まずは「しくみ」を知ろう
「先生ってどうやって成績つけてるの?」って疑問に思う人も多いと思います。実は通知表の成績は、テストの点数だけで決まっているわけではないのです。先生たちは、授業や提出物、発言の様子など、いろいろなところを見て評価しています。
文部科学省のルールでは、3つの観点から評価する決まりがあります。
成績を決める「3つの観点」とは
①知識・技能
授業で習ったことがしっかり身についているか、テストやプリント、小テストで確認されることが多いです。
②思考・判断・表現
応用問題を考える力、レポートや発表で自分の考えをまとめる力など、「どう考えたか」を見られます。
③主体的に学習に取り組む態度
授業中のようすや、宿題・提出物への取り組み、積極性などを判断されます。
たとえば、テストで80点が取れても、提出物をまったく出していなかったり、授業中にぼーっとしていたら、評価が下がってしまうこともあります。
成績2は「C」が多いとついてしまう
先生は上の3つの観点ごとに、A(よくできている)、B(ふつう)、C(もっとがんばろう)の3段階で評価しています。
<具体例>
・知識・技能:B(ふつう)
・思考・判断・表現:C(がんばろう)
・主体性:C(がんばろう)
この3つの合計を数値にして(A=5点、B=3点、C=1点)、平均すると→(3 + 1 + 1)÷3=1.66 → 四捨五入で【2】になってしまいます。
だから、「テストは悪くなかったけど、提出物とかサボっちゃったな〜」という人は、思っていたより評価が下がってる…なんてこともあるのです。
成績2がつくのはどんなとき?タイプ別にチェックしてみよう!
ここでは、どの項目でつまずいているのかをチェックできるように、よくある3つのパターンを紹介します。
①テストの点が取れていない(知識・技能)
・テストの最初の基礎問題でつまずいている
・授業中のプリントや小テストでも点がとれない
・用語の意味や計算のやり方をあやふやに覚えている
こんな場合は、「知識・技能」が足りていないかもしれません。いきなり難しい問題に取り組むのではなくて、基本をていねいに見直すのがポイントです。
②応用問題や発表が苦手(思考・判断・表現)
・記述問題で「何を書けばいいのかわからない」
・発表やグループ活動がちょっと苦手
・レポートに「自分の考え」が書けない
これらに当てはまると、「思考・判断・表現」の評価が下がりがちです。自分の意見を言ったり、表現するのが苦手な人は、少しずつ練習しましょう。先生はお子さんたちの努力を見ています。
③やる気が見えにくい(主体性)
・宿題や課題をよく忘れてしまう
・授業中に眠そう、発言しない
・勉強への意欲が伝わってこない
先生に「やる気がないのかな?」と思われてしまうと、評価が下がってしまうことがあります。逆に言えば、ちょっとでもやる気を見せれば、評価がぐっと上がるかもしれません。普段からの心がけが大切です。

成績2のままだとどうなる?知っておきたい3つのこと
勉強の大変さを考えると、「2でもいいや」と思ってしまう気持ちも、ちょっとわかります。でも、後になればなるほど「もっと早くがんばればよかった…」と後悔する人が多いのも事実です。
ここでは、成績2のデメリットを正直にお伝えします。
高校受験のとき「内申点」に影響する
中3になると、通知表の成績は高校に提出する「内申点」として扱われます。この内申点で合否が決まることもあるので、1教科の「2」が全体に響いてしまうこともあるのです。
「受けたい高校があるけど、内申点が足りない…」なんてことにならないように、今から少しずつ対策しておきましょう。
②推薦がもらえない可能性がある
中学校によっては「通知表に2があると推薦NG」というルールを、高校との間で取り決めていることがあります。学校からの推薦があると、ほとんどの場合簡単な面接を受ければ合格が決まります。
テストを受験するのと比べ、かなり合格しやすい高校もあるので、推薦を希望しているお子さんにとっては、もったいないことになってしまうこともあります。
③放っておくと勉強がどんどん難しくなっていく
数学や英語などは「積み重ね教科」なので、1つわからないまま次に進むと、どんどん苦手がふくらんでしまいます。今「難しい」と感じているものは、1年後には「難しすぎてまったくわからない」状態になる可能性があります。「わからないところを放っておく」のは、とても危険です。
成績2から抜け出すために、今すぐできる5つのこと!
「ならどうすればいいの?」と思われるかも知れません。そこで、評価を上げるために今からできるおすすめの行動を紹介します。ひとつずつでもOKです。できそうなものから試してみてください。
①授業をちゃんと聞く・メモをとる
まずは授業をきちんと聞き、ノートを取る習慣をつけましょう。ノートをていねいに取ると、あとで見直しやすいですし、先生にも「がんばってるな」と伝わります。
ちょっとでも「わからないかも?」と思ったら、先生に質問する勇気も持てるとさらに良いです。
②宿題・提出物はしっかり出す
先生は「ちゃんと出したか」だけでなく、「どれだけ考えて取り組んだか」も見ています。記述問題や作文などの難しいものや、手間がかかるものは面倒かもしれません。でも、出さないのはNGです。
自分なりにがんばって書くことで、良い評価をもらえます。
③テスト前は計画を立てて2週間前からスタート!
・今日は数学を1ページ、明日は英語の単語練習…のように予定を立てる
・教科書やワークを使って、基礎から少しずつ復習する
これらを意識して取り組むことで、テストでの失敗を防げる可能性が上がります。勉強って、「ちょっとずつの努力」の積み重ねがとても大切だと思います。
④苦手な単元は前に戻って復習する
「今やってるところが全然わからない…」と思ったら、前の学年の内容があやしいかもしれません。たとえば、数学の連立方程式が苦手なら、方程式から少しずつやり直してみましょう。
「できた!」という体験を重ねていくことで、少しずつ苦手がなくなります。
⑤どうしてもダメなときは、大人に相談してみよう
自分だけで解決できないときは、先生・親・家庭教師・塾の先生など、相談できる人を見つけてください。話すことで気持ちもラクになるし、意外と近道が見つかることもあるかもしれません。
それでも難しいときは…「別の作戦」も考えよう!
がんばっても評価がなかなか上がらないときには、進路の選び方を工夫することも大切です。
内申点を重視しない高校を検討する
私立高校の中には、当日の入試の点数だけで合否が決まる学校もあります。こういった学校を目指すことで、今後の努力次第で十分にチャンスをつかむことができます。
得意な教科で点数を伸ばす
苦手な教科は最低限がんばり、得意な教科で高得点を目指す方法もありです。とくに中堅の高校までは、総合点で判断されることも多いので、得意教科をうまく使って苦手をカバーできる場合もあります。
3教科入試を実施している高校を選ぶ
理科や社会が苦手な場合は、英語・数学・国語の3教科だけで受験できる高校を探してみましょう。首都圏などでは3教科型の私立高校も多く存在します。
評価は変えられます。今できることから始めましょう
最後にもう一度、成績2から抜け出すために大切なことをまとめます。
・授業をきちんと受ける
・宿題や提出物をちゃんと出す
・勉強の計画を立てて、少しずつ進める
・苦手な単元は復習する
・困ったときは、大人に相談する
今はちょっとつらいかもしれませんが、努力は必ず実を結びます。「前よりできるようになった!」と思える日が、きっと来るはずです。
焦らず、あきらめず、一歩ずつ。今日からできることを、ひとつずつ始めていきましょう。
家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。