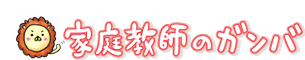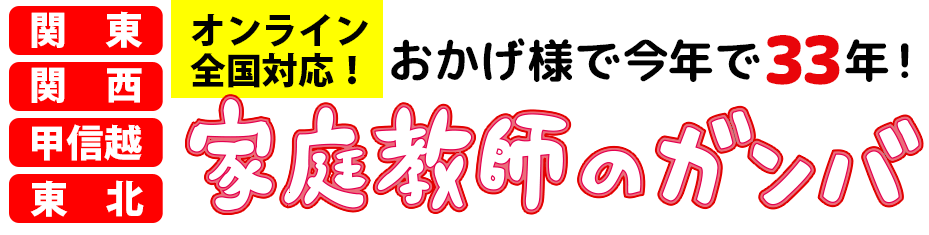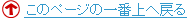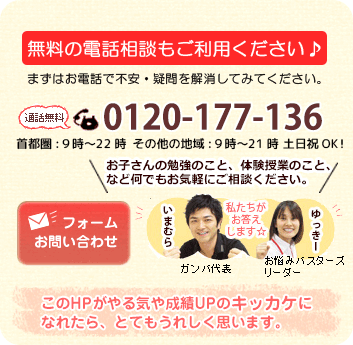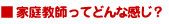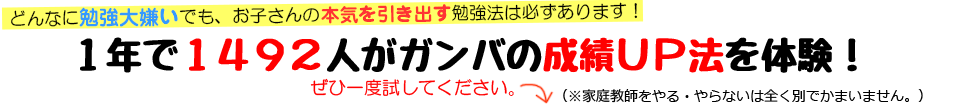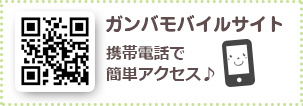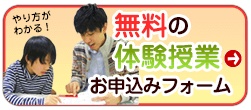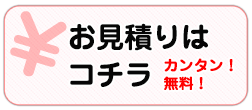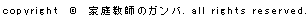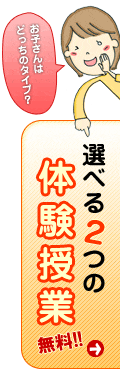なんで内申書ってあるの?
内申書とは
内申書とは、正式には調査書という名称で、
内容はおもに6つです。
1つ目は学習の記録。
第3学年の通知表の素点が5段階で記載されます。
2つ目は特別活動記録。
生徒会や学級会など、校内の活動についての状況が記載されます。
3つ目は特別活動以外の諸活動の記録及び特技。
運動や資格、社会的活動などで顕著な事柄がある場合記載されます。
4つ目は行動の記録。
こちらは12項目に分かれており、それぞれ3段階で評価されます。
5つ目は出欠の記録。
そして6つ目は身体の記録です。
何に使われるの?
内申書は、主に高校受験の際に必要になります。
公立高校の場合、この内申書の点数が合否の半分を決めるほど重要なものとなっています。
大学入試でも提出しますが、
AO入試などでは学習の記録にあたる内申点が一定以上である必要があるなどの
条件がある場合もあります。
ただし、学校によって成績分布の割合などに偏りがある場合などがあるという問題点が指摘されています。
なぜ内申点が重視されるの
高校入試で内申点が合否の半分という大きなウェイトを持つのは何故でしょう。
まず1つには、受験でのテスト一発にしてしまうのではなく、
日頃の勉強をしっかりしている人の負担を軽くするためと言われています。
もう一つには、中学校の秩序を維持するためと言われています。
中学生というのは心身ともに変化が大きく、不安定な時期です。
日ごろの行いも評価して受験に反映させることで、
学校の秩序の維持が期待できるということです。
- 勉強嫌いな中学生を勉強好きにさせるには
- 勉強が苦手な中学生に自信をつけさせるには
- やる気がない中学生の心に火をつけ本気にさせる
- 家庭教師と講習会の両方で中学生の苦手科目を克服する
- 中学生の家庭教師の上手な探し方
- 中学生の子どもは塾に行かせるべきか家庭教師をつけるべきか
- 高校入試必勝法!?
- 中学生の教材の選び方
- 中学生に勉強の癖をつけさせるには
- 部活と勉強を上手く両立させる方法
- 苦手な科目を克服する方法
- 高校受験の流れ
- 高校受験の問題の傾向
- 高校はどうしてみんな行くの?
- なんで内申書ってあるの?
- 中学校の定期テストの勉強方法
- 併願優遇のメリットとデメリット
- 総合高校のメリットとデメリット
- 単位制高校のメリットとデメリット
- 塾で教えてくれない副教科こそ大事
- 中三から学ぶ公民の効率的な学び方
- 中学英語の効率的な学び方
- 算数と数学の違いについて
- 不登校の子どもの勉強はどうしたらいい?
- 塾の補習勉強を家庭教師に見てもらうメリット
- 推薦入学のときの作文と小論文の違い
- 中学時に受ける模擬試験の重要性
- 高校受験の過去問題の重要性
- 中学一年生の学習のポイントについて
- 中学二年生の学習のポイントについて
- 中学三年生の学習のポイントについて
- 中学三年の夏休みの学習について
- 高校受験間近の勉強について
- スポーツ推薦制度と学習について
- 特待生制度と学習について
- 高校入学前にしておきたい勉強
- 高校選びのポイント
- 高校入試の面接でのポイント
- 高校入試の集団討論でのポイント
- 高校入試の国語勉強法
- 高校入試の数学勉強法
- 高校入試の英語勉強法
- 高校入試の理科勉強法
- 高校入試の社会勉強法
- ためになる中学生のノートの作り方
- 大学付属高校のメリット・デメリット